「青山なぎさ(Liella!)ちゃん、マジ可愛いっすよー!!」
って昨年買ったカレンダーですが、結局一枚もめくらずに、
ずっと壁にかかったまま気がついたら一年経っていました。

久しぶりに断捨離でもしようかと部屋を見回してみると、
このカレンダーが壁にあるのに気がついたのですよね。
思えばカレンダーも今となっては見るのはスマホの中で、
これもドンドン文明の利器に取り込まれていってるのですね。
大丈夫、カラオケはスマホには取り込まれないから!(多分)
さて、テレビにかなりの頻度で出演する料理研究家リュウジさん。
先日、YouTubeで『モスバーガー』レビューの動画を投稿し、
モスバーガー好きの私は、思わずその動画の全編を視聴。
その動画の前には『マクドナルド』のレビュー動画を投稿しており、
リュウジさんが望むと望まざると、両者を比べた感じの動画です。
こんなに忖度なく比べていいのか?と心配になるくらいで、
しかしだからこそ見ていて楽しかったりするのですけどね。
その中でモスの『フィッシュバーガー』が絶品というくだりがあり、
マック対抗の『フィレオフィッシュ』に比べて、安くて美味しいとの事。
個人的にフィッシュバーガーを食べたことが無かったので、
その動画を見てからというものどうしてもそれが食べたい。
こんなことを言うと怒られそうですが、モスバーガーのメニューは、
フィッシュバーガーを食べる必要があるのか?と思うほどに、
結構充実していると思うので、今まで選択肢にありませんでした。
それでも、この動画内でいろいろなハンバーガーのレビューをして、
わざわざフィッシュバーガーが美味しいというのですから、
これは一回食べてみる価値はあるかもしれないと思い始めます。
そうなってくると、今すぐにでも食べに行きたいという衝動で、
自宅近所のモスバーガーに時間を見つけて直行することに。
ゴールデンウイークだし、久しぶりに店内でモスを満喫します。
この動画内ではリュウジさんは、フィッシュバーガーを含めて、
もうひとつ『テリヤキバーガー』も絶賛していたので、
それに乗っかって、その2種類のハンバーガーを注文しました。
すると店員さんから、
「リュウジさんの動画、ごらんになられたのですか?」
と私に声をかけてくるではありませんか!
まさかこんなことを言われるなんて、微塵も思ってもおらず、
そして私がものすごいミーハーな人に見られているようです。
恥ずかしそうに返事をすると、余計恥ずかしくなりそうなので、
「リュウジさん、美味しそうだったので試しにきました!」と返答
すると、本当にフィッシュバーガーを頼む人が増えているようで、
直近の売上げにフィッシュバーガーが貢献しているそうです。
リュウジさんのモスバーガーの動画は案件ではないそうですが、
実際に売上げに動かせてしまっていることに感心しますよね。
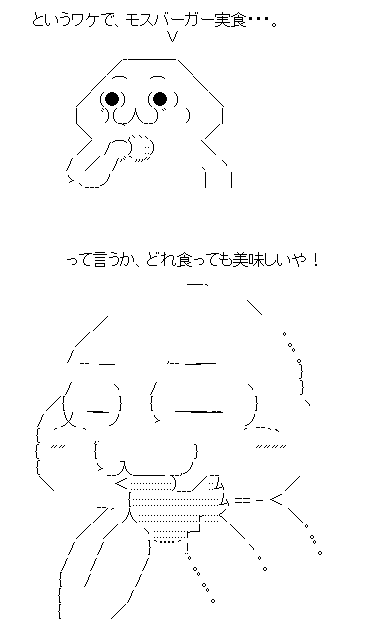
って昨年買ったカレンダーですが、結局一枚もめくらずに、
ずっと壁にかかったまま気がついたら一年経っていました。
久しぶりに断捨離でもしようかと部屋を見回してみると、
このカレンダーが壁にあるのに気がついたのですよね。
思えばカレンダーも今となっては見るのはスマホの中で、
これもドンドン文明の利器に取り込まれていってるのですね。
大丈夫、カラオケはスマホには取り込まれないから!(多分)
さて、テレビにかなりの頻度で出演する料理研究家リュウジさん。
先日、YouTubeで『モスバーガー』レビューの動画を投稿し、
モスバーガー好きの私は、思わずその動画の全編を視聴。
その動画の前には『マクドナルド』のレビュー動画を投稿しており、
リュウジさんが望むと望まざると、両者を比べた感じの動画です。
こんなに忖度なく比べていいのか?と心配になるくらいで、
しかしだからこそ見ていて楽しかったりするのですけどね。
その中でモスの『フィッシュバーガー』が絶品というくだりがあり、
マック対抗の『フィレオフィッシュ』に比べて、安くて美味しいとの事。
個人的にフィッシュバーガーを食べたことが無かったので、
その動画を見てからというものどうしてもそれが食べたい。
こんなことを言うと怒られそうですが、モスバーガーのメニューは、
フィッシュバーガーを食べる必要があるのか?と思うほどに、
結構充実していると思うので、今まで選択肢にありませんでした。
それでも、この動画内でいろいろなハンバーガーのレビューをして、
わざわざフィッシュバーガーが美味しいというのですから、
これは一回食べてみる価値はあるかもしれないと思い始めます。
そうなってくると、今すぐにでも食べに行きたいという衝動で、
自宅近所のモスバーガーに時間を見つけて直行することに。
ゴールデンウイークだし、久しぶりに店内でモスを満喫します。
この動画内ではリュウジさんは、フィッシュバーガーを含めて、
もうひとつ『テリヤキバーガー』も絶賛していたので、
それに乗っかって、その2種類のハンバーガーを注文しました。
すると店員さんから、
「リュウジさんの動画、ごらんになられたのですか?」
と私に声をかけてくるではありませんか!
まさかこんなことを言われるなんて、微塵も思ってもおらず、
そして私がものすごいミーハーな人に見られているようです。
恥ずかしそうに返事をすると、余計恥ずかしくなりそうなので、
「リュウジさん、美味しそうだったので試しにきました!」と返答
すると、本当にフィッシュバーガーを頼む人が増えているようで、
直近の売上げにフィッシュバーガーが貢献しているそうです。
リュウジさんのモスバーガーの動画は案件ではないそうですが、
実際に売上げに動かせてしまっていることに感心しますよね。
先日、仕事を終えて最寄り駅から自宅までの夜道を歩いていたら、自分の少し前から聞こえてくる人間のものではない足音と気配。走る緊張感。周囲に注意を払いつつ身構えながら出来るだけ音を立てずに歩いていたら、エンカウントしました。
カモシカと。
大人しい性格というのは知っていて、不用意に刺激しなければ問題無いと知ってはいても夜道かつ至近距離で出くわすとさすがにビビります。カモシカの方は私に気づいた途端に走り去って行きましたがしばらく心拍数が上がりっぱなしでした。
こんばんは、小島@監督です。
ところで今回の歌会に参加出来なくてすいません。次回は参加する予定。
さて、今回の映画は「オーメン:ザ・ファースト」です。
1971年、ローレンス枢機卿(ビル・ナイ)に導かれ、見習い修道女のマーガレット(ネル・タイガー・フリー)はアメリカからローマへやってきた。正式な修道服を纏う着衣式に向け、孤児院の教師として赴任するためだ。折しもローマでは左翼活動が活発化し教会の権威が失墜しつつあった。そんな中、マーガレットは不安定な情動で他の子どもたちから孤立している少女カルリータ(ニコール・ソラス)と出会う。
心なしか赤みがかった質感の色調と、古風なカメラワーク。新作であるにも関わらず非常にクラシックな雰囲気で、この映画は始まります。1976年に製作された伝説的ホラー映画「オーメン」、その後シリーズ化されリメイクも含めて5本の映画と1本のTVドラマが製作されました。2006年製作のリメイク版依頼18年ぶりとなる新作は、第1作へと繋がる前日譚。オリジナルへ多大なリスペクトを捧げた、極めて正統派のオカルトホラーです。
特に前半はじっくりとスローな語り口で物語、特に教会にまつわる世界観の描写に費やしています。主要場面の大半が荘厳な教会の中で展開し、悪魔的なモチーフをアクセントとして落とし込むゴシックな雰囲気の映像とこの語り口が良くマッチしているほか、ビル・ナイ、ソニア・ブラガ、チャールズ・ダンスと言った名優たちが脇を固めて重厚な演技を見せてくれ、グロテスクな描写もそれほど多くはないのが特徴です。ショッキングな映像よりもむしろ雰囲気で観客に恐怖を見せる手腕は近年のフランチャイズなホラー映画のスタイルとしては少し珍しいように思います。
この映画を手掛けたのはアルカシャ・スティーブンソン。なんとこれが長編デビュー作になります。今後が楽しみな監督がまた1人誕生しました。
それにしても興味深いのは劇中の背景やそして後半に明かされるある謎と言い、映画の向こうに本当に教会への信頼が揺らいでいるのが伺えるところで、敬虔な方にとってはいささか眉をひそめてしまうかも。この辺り、世界中の教会で神父や牧師による性的なスキャンダルが相次いでいる現状を踏まえたものかもしれません。
派手さに少し欠けるところがあるものの、プロが堅実にプロの仕事をしている作品で、個人的には結構お薦めの一本です。実のところ批評家筋の評価も高い出来栄えの良さとは裏腹に興行的には今ひとつらしく、続編を匂わせる描写があるものの実現するかどうかは不透明。なかなかままならないものですね。
カモシカと。
大人しい性格というのは知っていて、不用意に刺激しなければ問題無いと知ってはいても夜道かつ至近距離で出くわすとさすがにビビります。カモシカの方は私に気づいた途端に走り去って行きましたがしばらく心拍数が上がりっぱなしでした。
こんばんは、小島@監督です。
ところで今回の歌会に参加出来なくてすいません。次回は参加する予定。
さて、今回の映画は「オーメン:ザ・ファースト」です。
1971年、ローレンス枢機卿(ビル・ナイ)に導かれ、見習い修道女のマーガレット(ネル・タイガー・フリー)はアメリカからローマへやってきた。正式な修道服を纏う着衣式に向け、孤児院の教師として赴任するためだ。折しもローマでは左翼活動が活発化し教会の権威が失墜しつつあった。そんな中、マーガレットは不安定な情動で他の子どもたちから孤立している少女カルリータ(ニコール・ソラス)と出会う。
心なしか赤みがかった質感の色調と、古風なカメラワーク。新作であるにも関わらず非常にクラシックな雰囲気で、この映画は始まります。1976年に製作された伝説的ホラー映画「オーメン」、その後シリーズ化されリメイクも含めて5本の映画と1本のTVドラマが製作されました。2006年製作のリメイク版依頼18年ぶりとなる新作は、第1作へと繋がる前日譚。オリジナルへ多大なリスペクトを捧げた、極めて正統派のオカルトホラーです。
特に前半はじっくりとスローな語り口で物語、特に教会にまつわる世界観の描写に費やしています。主要場面の大半が荘厳な教会の中で展開し、悪魔的なモチーフをアクセントとして落とし込むゴシックな雰囲気の映像とこの語り口が良くマッチしているほか、ビル・ナイ、ソニア・ブラガ、チャールズ・ダンスと言った名優たちが脇を固めて重厚な演技を見せてくれ、グロテスクな描写もそれほど多くはないのが特徴です。ショッキングな映像よりもむしろ雰囲気で観客に恐怖を見せる手腕は近年のフランチャイズなホラー映画のスタイルとしては少し珍しいように思います。
この映画を手掛けたのはアルカシャ・スティーブンソン。なんとこれが長編デビュー作になります。今後が楽しみな監督がまた1人誕生しました。
それにしても興味深いのは劇中の背景やそして後半に明かされるある謎と言い、映画の向こうに本当に教会への信頼が揺らいでいるのが伺えるところで、敬虔な方にとってはいささか眉をひそめてしまうかも。この辺り、世界中の教会で神父や牧師による性的なスキャンダルが相次いでいる現状を踏まえたものかもしれません。
派手さに少し欠けるところがあるものの、プロが堅実にプロの仕事をしている作品で、個人的には結構お薦めの一本です。実のところ批評家筋の評価も高い出来栄えの良さとは裏腹に興行的には今ひとつらしく、続編を匂わせる描写があるものの実現するかどうかは不透明。なかなかままならないものですね。
ホームページリニューアルを機会にマスコットキャラを作り、
歌会でキャラの名前を募集をして、いよいよ本日投票。
帰宅して投票用紙にの内容を早速集計するのですが・・・
うーむ、めんどくさい(笑)
自分で進んでやっといてめんどくさいもないのですが、
どうも投票用紙のレイアウトが悪く集計し辛過ぎるのです。
もっと集計が楽になるようなレイアウトにとておけばと、
今さらながらに軽い後悔をしてうなだれている私がいます。
もちろん、次回歌会では結果発表をさせていただきます!
さて、車でテーマパークや大型ショッピングセンターに行くと、
やっぱり人が集まってくるところは、駐車は大変なもの。
駐車場に入るのに並んで、入って停める場所を探してと、
もうそういうのが大変なので、混みそうと予想できる時間に、
そういう場所へは行かないというのが私の中での基本です。
身近なところではイオンなどですが、そういうところは、
もう朝の開店か夜の閉店間際にしか行こうと思いません。
ってことはよっぽど用事がない限り行かないってことで。
そんな感じで人の少なそうな時間を狙ったりしていると、
当然のことのように、しっかり空いている駐車場ですが、
そうなると、その広い駐車場の好きなところに停め放題。
になると、それはそれで停める場所に迷ってしまう私。
突然、優柔不断になってしまって迷いまくってしまい、
なんとなくウロウロとしてなかなか停められないのです。
隣に停めた車にぶつけられないように端の方に止めたり、
店の入り口に近いところに停めたり自由自在なのに、
それを望んで開店に合わせて来ているのに全く変な話です。
ちなみに歌会の時はアスナル金山に駐車するのですが、
この時ばかりは何の迷いもなく、定位置に直行します。
やっぱり、慣れたところだと迷いはなくなるものですね。
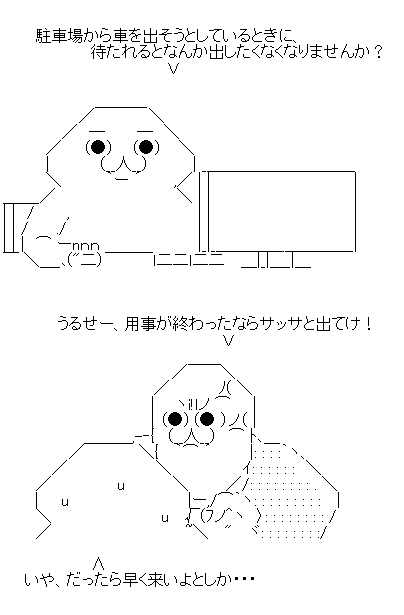
歌会でキャラの名前を募集をして、いよいよ本日投票。
帰宅して投票用紙にの内容を早速集計するのですが・・・
うーむ、めんどくさい(笑)
自分で進んでやっといてめんどくさいもないのですが、
どうも投票用紙のレイアウトが悪く集計し辛過ぎるのです。
もっと集計が楽になるようなレイアウトにとておけばと、
今さらながらに軽い後悔をしてうなだれている私がいます。
もちろん、次回歌会では結果発表をさせていただきます!
さて、車でテーマパークや大型ショッピングセンターに行くと、
やっぱり人が集まってくるところは、駐車は大変なもの。
駐車場に入るのに並んで、入って停める場所を探してと、
もうそういうのが大変なので、混みそうと予想できる時間に、
そういう場所へは行かないというのが私の中での基本です。
身近なところではイオンなどですが、そういうところは、
もう朝の開店か夜の閉店間際にしか行こうと思いません。
ってことはよっぽど用事がない限り行かないってことで。
そんな感じで人の少なそうな時間を狙ったりしていると、
当然のことのように、しっかり空いている駐車場ですが、
そうなると、その広い駐車場の好きなところに停め放題。
になると、それはそれで停める場所に迷ってしまう私。
突然、優柔不断になってしまって迷いまくってしまい、
なんとなくウロウロとしてなかなか停められないのです。
隣に停めた車にぶつけられないように端の方に止めたり、
店の入り口に近いところに停めたり自由自在なのに、
それを望んで開店に合わせて来ているのに全く変な話です。
ちなみに歌会の時はアスナル金山に駐車するのですが、
この時ばかりは何の迷いもなく、定位置に直行します。
やっぱり、慣れたところだと迷いはなくなるものですね。
今くらいの時期は恵那峡まで車を動かしてそこで散歩して帰る、というのが大抵の休日の行動パターン。で、昨日も行ってみたらクラシックカーのイベントやってました。


どこからやって来たのかポルシェやらGTRやらアルピーヌなど、数十台が集まっていて壮観。ほとんどの車にナンバープレートが付いていて、今でも現役なのに驚きます。
こんばんは、小島@監督です。
恵那峡はちょうど桜が散り際で、舞い散る花びらとクラシックカーというコントラストも美しかったですね。
さて、今回の映画は「青春ジャック 止められるか、俺たちを2」です。
1980年代初頭、名古屋でビデオカメラのセールスをしていた木全純治(東出昌大)の元に伝手を頼って映画監督若松孝二(井浦新)が尋ねてくる。若松は名古屋に映画館を作ろうとしており、木全にその館長になってもらいたいとオファーに来たのだ。映画への情熱が消えない木全はこの勧誘を受け館長に就任。映画館は「シネマスコーレ」と名付けられた。
開館後、スコーレに熱心に通い詰める青年・井上(杉田雷麟)がいた。若松に弟子入りしたい井上は、若松に会える可能性に賭けて通っていたのだ。ある日、たまたま来館した若松が木全に促され舞台挨拶することになる。そして客席には井上がいた…
ミニシアターから始まる、青春のドラマ。
名古屋の映画文化で大きな役割を担うミニシアター、シネマスコーレ。その黎明期の姿と共に映画に懸ける青年の痛い青春劇を描きます。脚本と監督を務めるのは故・若松孝二の弟子の一人であり、コロナ禍で苦しむミニシアターの応援団体「勝手にしゃべりやがれ!」の結成メンバーである井上淳一。前半こそシネマスコーレ館長の木全を中心に展開しますが次第に物語は井上の方へフォーカスしていき、この映画は井上監督自身の自伝的性格を持ち合わせていくことになります。
シネマスコーレが主舞台だけありスコーレで撮影も行われていて、良く知っている場所が良く知らないアングルと共にバンバン出てくるので何だか不思議な気分になります。余談ですが、木全純治さん本人と、スコーレの現支配人坪井篤史さんとスタッフ大浦奈都子さんが作中にカメオ出演しています。
私がシネマスコーレに行くようになった時には既に若松孝二監督は故人だったのでお見かけしたことは無く、井浦新が演じるその居住まいが本人と比べてどうかは良く分かりませんが、東出昌大演じる木全さんはさすが役者というか、仕草や雰囲気が本人と良く似ていて驚きます。腰は低いのに意志は強い、そして名古屋でインディペンデント映画の下地を築く一翼を担っていくことになる、そんな人物を好演しています。
映画を作りたい衝動に突き動かされる井上と対照的なのが芋生悠演じる金本法子。この方は実在の人物ではないようですが、映画を作りたいのに今一歩動けずにいる金本の存在が井上の青春をより重層的に描き出し映画に深みを与えます。
映画の中で語られるトピックとして少し説明が必要と思われるのは、作中で度々名前だけ登場する足立正生の存在。若松孝二の元でピンク映画などの制作に携わっていた人物ですが、その後パレスチナ解放人民戦線のゲリラ部隊に加わったあと日本赤軍に合流し、国際手配された人物です。1990年代終わりにレバノンで逮捕され、刑務所に収監。刑期満了後日本へ強制送還されました。帰国後は再び映画の世界へ戻っており、日本映画大学で非常勤講師を務めたりしています。2022年、安倍晋三襲撃事件の実行犯の半生を描いた映画「REVOLUTION +1」を監督し、大きなニュースとなりました。その「REVOLUTION+1」の脚本とプロデュースを手掛けたのが誰あろう井上淳一氏です。同映画は短期ながらシネマスコーレでもロードショーされました。
地元志向の強い映画、というだけでなく決して光溢れる場所ではないアングルから描かれる日本映画史の一幕としても興味深いものを見せてくれる作品です。大手メジャーのシネコンだけでは、この映画は生まれなかった。
ミニシアターだってまだ負けてない。
どこからやって来たのかポルシェやらGTRやらアルピーヌなど、数十台が集まっていて壮観。ほとんどの車にナンバープレートが付いていて、今でも現役なのに驚きます。
こんばんは、小島@監督です。
恵那峡はちょうど桜が散り際で、舞い散る花びらとクラシックカーというコントラストも美しかったですね。
さて、今回の映画は「青春ジャック 止められるか、俺たちを2」です。
1980年代初頭、名古屋でビデオカメラのセールスをしていた木全純治(東出昌大)の元に伝手を頼って映画監督若松孝二(井浦新)が尋ねてくる。若松は名古屋に映画館を作ろうとしており、木全にその館長になってもらいたいとオファーに来たのだ。映画への情熱が消えない木全はこの勧誘を受け館長に就任。映画館は「シネマスコーレ」と名付けられた。
開館後、スコーレに熱心に通い詰める青年・井上(杉田雷麟)がいた。若松に弟子入りしたい井上は、若松に会える可能性に賭けて通っていたのだ。ある日、たまたま来館した若松が木全に促され舞台挨拶することになる。そして客席には井上がいた…
ミニシアターから始まる、青春のドラマ。
名古屋の映画文化で大きな役割を担うミニシアター、シネマスコーレ。その黎明期の姿と共に映画に懸ける青年の痛い青春劇を描きます。脚本と監督を務めるのは故・若松孝二の弟子の一人であり、コロナ禍で苦しむミニシアターの応援団体「勝手にしゃべりやがれ!」の結成メンバーである井上淳一。前半こそシネマスコーレ館長の木全を中心に展開しますが次第に物語は井上の方へフォーカスしていき、この映画は井上監督自身の自伝的性格を持ち合わせていくことになります。
シネマスコーレが主舞台だけありスコーレで撮影も行われていて、良く知っている場所が良く知らないアングルと共にバンバン出てくるので何だか不思議な気分になります。余談ですが、木全純治さん本人と、スコーレの現支配人坪井篤史さんとスタッフ大浦奈都子さんが作中にカメオ出演しています。
私がシネマスコーレに行くようになった時には既に若松孝二監督は故人だったのでお見かけしたことは無く、井浦新が演じるその居住まいが本人と比べてどうかは良く分かりませんが、東出昌大演じる木全さんはさすが役者というか、仕草や雰囲気が本人と良く似ていて驚きます。腰は低いのに意志は強い、そして名古屋でインディペンデント映画の下地を築く一翼を担っていくことになる、そんな人物を好演しています。
映画を作りたい衝動に突き動かされる井上と対照的なのが芋生悠演じる金本法子。この方は実在の人物ではないようですが、映画を作りたいのに今一歩動けずにいる金本の存在が井上の青春をより重層的に描き出し映画に深みを与えます。
映画の中で語られるトピックとして少し説明が必要と思われるのは、作中で度々名前だけ登場する足立正生の存在。若松孝二の元でピンク映画などの制作に携わっていた人物ですが、その後パレスチナ解放人民戦線のゲリラ部隊に加わったあと日本赤軍に合流し、国際手配された人物です。1990年代終わりにレバノンで逮捕され、刑務所に収監。刑期満了後日本へ強制送還されました。帰国後は再び映画の世界へ戻っており、日本映画大学で非常勤講師を務めたりしています。2022年、安倍晋三襲撃事件の実行犯の半生を描いた映画「REVOLUTION +1」を監督し、大きなニュースとなりました。その「REVOLUTION+1」の脚本とプロデュースを手掛けたのが誰あろう井上淳一氏です。同映画は短期ながらシネマスコーレでもロードショーされました。
地元志向の強い映画、というだけでなく決して光溢れる場所ではないアングルから描かれる日本映画史の一幕としても興味深いものを見せてくれる作品です。大手メジャーのシネコンだけでは、この映画は生まれなかった。
ミニシアターだってまだ負けてない。
歯医者の定期検診の日が迫る中、その歯医者から電話が。
どうやら私を担当している方が、交通事故で入院したそうで、
今決まっている予約の日程を変更したいとのことでした。
変更後の予約日、私はいつも土曜日の昼以降が希望ですが、
なぜか数週間に渡ってその担当の方の土曜日の空きが、
なんとも極端なことに朝9時しか空いていないとのこと。
結局しかたがないので9時でいいやと諦めて予約。
私の通う歯医者は名古屋駅近くで、私の家から約1時間。
歯医者のために8時前に家を出なきゃいかんのかと思い、
今から次の定期検診をゲンナリしながら迎えようと思います。
さて、歌会で金山に行くついでにいつも一つ楽しみがあります。
それはアスナル金山にある週替わりのスイーツショップです。
love2sweets.com
3店舗のスペースの出店が2週間ごとに入れ替わるので、
毎回どれか1店くらいは私の気になるスイーツが入ります。
私は歌会の時はアスナル金山の駐車場に車を停めていて、
そのお店の前を歌会の荷物を引っ張って必ず通りかかります。
そして私自身、甘いものが好きなので毎回お店を覗きます。
店舗が入れ替わるということは、買い逃すと次は無いと思うと、
思わず買わずにはいられず衝動でつい買ってしまうのです。
そうしているうちに、歌会に来るたびに何かを買うようになり、
今では歌会で金山に来るついでに寄るのが楽しみになりました。
そのうちに店舗の入れ替わりのタイミングが分かってくると、
次は何かな?と次の出店すらも気になるようになってきます。
お店の横の壁には次回出店の告知がされているので、
今ではそれすらもチェックするようになっている私がいます。
しかし最近気が付いたことに、2週間で店舗が入れ替わると、
約4週ごとに開催される歌会の隙間に出店があることになり、
私が見ないうちに入れ替わる店舗があるということです。
入れ替わった店舗のスイーツが私にストライクだったらと思うと、
いよいよもって出展される店舗の内容が気になってきます。
別にスイーツを食べ歩くほどのスイーツ好きではないですが、
歌会のホームにお店があることが自分をそうさせるのでしょうね。
次回の歌会当日、どんなスイーツがあるか今から楽しみです!
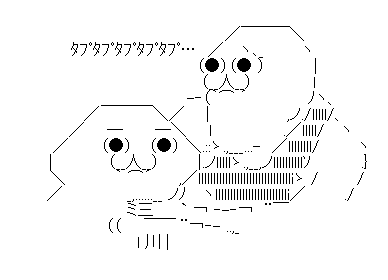
どうやら私を担当している方が、交通事故で入院したそうで、
今決まっている予約の日程を変更したいとのことでした。
変更後の予約日、私はいつも土曜日の昼以降が希望ですが、
なぜか数週間に渡ってその担当の方の土曜日の空きが、
なんとも極端なことに朝9時しか空いていないとのこと。
結局しかたがないので9時でいいやと諦めて予約。
私の通う歯医者は名古屋駅近くで、私の家から約1時間。
歯医者のために8時前に家を出なきゃいかんのかと思い、
今から次の定期検診をゲンナリしながら迎えようと思います。
さて、歌会で金山に行くついでにいつも一つ楽しみがあります。
それはアスナル金山にある週替わりのスイーツショップです。
love2sweets.com
3店舗のスペースの出店が2週間ごとに入れ替わるので、
毎回どれか1店くらいは私の気になるスイーツが入ります。
私は歌会の時はアスナル金山の駐車場に車を停めていて、
そのお店の前を歌会の荷物を引っ張って必ず通りかかります。
そして私自身、甘いものが好きなので毎回お店を覗きます。
店舗が入れ替わるということは、買い逃すと次は無いと思うと、
思わず買わずにはいられず衝動でつい買ってしまうのです。
そうしているうちに、歌会に来るたびに何かを買うようになり、
今では歌会で金山に来るついでに寄るのが楽しみになりました。
そのうちに店舗の入れ替わりのタイミングが分かってくると、
次は何かな?と次の出店すらも気になるようになってきます。
お店の横の壁には次回出店の告知がされているので、
今ではそれすらもチェックするようになっている私がいます。
しかし最近気が付いたことに、2週間で店舗が入れ替わると、
約4週ごとに開催される歌会の隙間に出店があることになり、
私が見ないうちに入れ替わる店舗があるということです。
入れ替わった店舗のスイーツが私にストライクだったらと思うと、
いよいよもって出展される店舗の内容が気になってきます。
別にスイーツを食べ歩くほどのスイーツ好きではないですが、
歌会のホームにお店があることが自分をそうさせるのでしょうね。
次回の歌会当日、どんなスイーツがあるか今から楽しみです!
本当に行ってきました、「タイトル未定」のフリーライブ。タイトル未定がメインアクトで他にもいくつかのアイドルユニットが登場する、そんなタイプのイベントでぶっちゃけこの手のライブイベントは初めてだから何もかも新鮮。どうせ観に来たのだしせっかくならばと終演後の特典会にまで参加してチェキ撮ったりサインもらったりしてました。参加してみて、とても妙な表現ですが「アイドルマスターシャイニーカラーズ」への解像度が上がったような気がします。なるほど、ノクチルやアンティーカたちはきっとこんな風に活動してるんですね。
こんばんは、小島@監督です。
驚いたことに、その日出演していたユニットの中には16時過ぎまでそこで特典会をやりながら夜に別の場所でもう1本ライブやった上に翌日も1ステージこなしていたり、タイトル未定も主催ライブの翌日には昼は名古屋でリリースイベント、夜は東京でライブみたいなスケジュールしていてそのタフさには頭が下がります。アイドルって体力勝負。
さて、今回の映画は「オッペンハイマー」です。
1950年代、ソ連との冷戦と赤狩りの風吹き荒ぶ中ロバート・オッペンハイマー(キリアン・マーフィー)はソ連へのスパイ行為の容疑をかけられアメリカ原子力委員会の聴聞に臨んでいた。
一方、原子力委員会の委員長を務めるルイス・ストローズ(ロバート・ダウニー・Jr)は公聴会に召喚される。そしてロスアラモスでのオッペンハイマーの「トリニティ実験」の詳細が明らかにされようとしていた。
巨匠クリストファー・ノーランの新作は、第二次大戦下において原爆開発の立役者となり一度は国の英雄となるもその後冷戦下ではスパイ容疑をかけられ公職を追放されたオッペンハイマーの半生を描く伝記映画。アメリカでは昨年7月に公開され大絶賛されたものの、日本にとっては非常にセンシティブなモチーフ故に公開は難航、本国に半年以上遅れてようやく公開となりました。
実際のところ、この映画は確かに広島や長崎を直接的に描きはしないものの、当初懸念されたようなアメリカの立場を強調し原爆投下を肯定するような内容ではありません。むしろ極めて優れたバランス感覚のもとに作られた映画です。そして激烈なまでに情報量の多い映画です。180分という上映時間ですが、最近のハリウッド大作が陥りがちな過剰な饒舌さは無いに等しく、1秒も余さず必要なシーンしかないと言っても過言ではありません。
次々に出てくる膨大な登場人物に対し説明などは全く無いのも特徴で、オッペンハイマーを筆頭に物理学者だけでもアインシュタイン、ハイゼンベルグ、ニールス・ボーア、エンリコ・フェルミ、デヴィッド・L・ヒルら当時の知の巨人たちが続々と登場。大半がノーベル賞受賞者だわ当人の名を冠した賞が設立されている人までいるわの軽くアベンジャーズ状態。そこに加えて彼らの家族、軍や政府の関係者が登場してきます。歴史的事実についても原子力開発史と同じくらい赤狩りやマッカーシズムについて知っておいた方がいい事は多く、濃密なダイアログとテリングで引き込んでくるタイプの作品故に予備知識が絶対に必要というわけではありませんが、見終わった後に「調べる」というアクションを起こすことはお薦めします。
IMAXやDolby cinemaなどラージフォーマットでも公開されている作品ですが、他のハリウッド映画やアニメと違い映像のスケール感で押すタイプではありません。むしろ重要視したいのは音響。この映画、オッペンハイマーの心象風景を音で表すようなシーンもあるほどかなり異様な音響デザインをしており、その迫力を十二分に味わえるかどうかが映画の印象に直結します。選べる範囲で良い音響のスクリーンを選びましょう。
あくまでもオッペンハイマーの半生とその意識と苦悩の変遷にフォーカスし続けるこの映画は、原爆投下の是非を問うような意識も赤狩りの不当さを告発するようなイデオロギーもありません。人類を滅ぼせる力を形にした男が、その存在に目の色を変える人々に恐怖する物語であり、むしろ極めてパーソナルであるが故に核の火を手にした人類のその後の不誠実さを浮き彫りにして見せていると言えましょう。
知識を持って楽しむというよりこの映画はむしろ知るためのきっかけ。この映画が何を見せて、何を見せないで語っているかは自身の手で調べてみてください。世界が均衡を崩しかけ、今また原子力政策や核抑止を意識せざるを得ない情勢だからこそ、観る価値のある作品と言えますね。他のクリストファー・ノーラン作品にも同様の傾向がありますが、後々自宅で観られるようになっても恐らく劇場鑑賞ほどに鮮烈な印象は残さないタイプなので、長いからと言わず気になっているならスクリーンで鑑賞することをお薦めします。
こんばんは、小島@監督です。
驚いたことに、その日出演していたユニットの中には16時過ぎまでそこで特典会をやりながら夜に別の場所でもう1本ライブやった上に翌日も1ステージこなしていたり、タイトル未定も主催ライブの翌日には昼は名古屋でリリースイベント、夜は東京でライブみたいなスケジュールしていてそのタフさには頭が下がります。アイドルって体力勝負。
さて、今回の映画は「オッペンハイマー」です。
1950年代、ソ連との冷戦と赤狩りの風吹き荒ぶ中ロバート・オッペンハイマー(キリアン・マーフィー)はソ連へのスパイ行為の容疑をかけられアメリカ原子力委員会の聴聞に臨んでいた。
一方、原子力委員会の委員長を務めるルイス・ストローズ(ロバート・ダウニー・Jr)は公聴会に召喚される。そしてロスアラモスでのオッペンハイマーの「トリニティ実験」の詳細が明らかにされようとしていた。
巨匠クリストファー・ノーランの新作は、第二次大戦下において原爆開発の立役者となり一度は国の英雄となるもその後冷戦下ではスパイ容疑をかけられ公職を追放されたオッペンハイマーの半生を描く伝記映画。アメリカでは昨年7月に公開され大絶賛されたものの、日本にとっては非常にセンシティブなモチーフ故に公開は難航、本国に半年以上遅れてようやく公開となりました。
実際のところ、この映画は確かに広島や長崎を直接的に描きはしないものの、当初懸念されたようなアメリカの立場を強調し原爆投下を肯定するような内容ではありません。むしろ極めて優れたバランス感覚のもとに作られた映画です。そして激烈なまでに情報量の多い映画です。180分という上映時間ですが、最近のハリウッド大作が陥りがちな過剰な饒舌さは無いに等しく、1秒も余さず必要なシーンしかないと言っても過言ではありません。
次々に出てくる膨大な登場人物に対し説明などは全く無いのも特徴で、オッペンハイマーを筆頭に物理学者だけでもアインシュタイン、ハイゼンベルグ、ニールス・ボーア、エンリコ・フェルミ、デヴィッド・L・ヒルら当時の知の巨人たちが続々と登場。大半がノーベル賞受賞者だわ当人の名を冠した賞が設立されている人までいるわの軽くアベンジャーズ状態。そこに加えて彼らの家族、軍や政府の関係者が登場してきます。歴史的事実についても原子力開発史と同じくらい赤狩りやマッカーシズムについて知っておいた方がいい事は多く、濃密なダイアログとテリングで引き込んでくるタイプの作品故に予備知識が絶対に必要というわけではありませんが、見終わった後に「調べる」というアクションを起こすことはお薦めします。
IMAXやDolby cinemaなどラージフォーマットでも公開されている作品ですが、他のハリウッド映画やアニメと違い映像のスケール感で押すタイプではありません。むしろ重要視したいのは音響。この映画、オッペンハイマーの心象風景を音で表すようなシーンもあるほどかなり異様な音響デザインをしており、その迫力を十二分に味わえるかどうかが映画の印象に直結します。選べる範囲で良い音響のスクリーンを選びましょう。
あくまでもオッペンハイマーの半生とその意識と苦悩の変遷にフォーカスし続けるこの映画は、原爆投下の是非を問うような意識も赤狩りの不当さを告発するようなイデオロギーもありません。人類を滅ぼせる力を形にした男が、その存在に目の色を変える人々に恐怖する物語であり、むしろ極めてパーソナルであるが故に核の火を手にした人類のその後の不誠実さを浮き彫りにして見せていると言えましょう。
知識を持って楽しむというよりこの映画はむしろ知るためのきっかけ。この映画が何を見せて、何を見せないで語っているかは自身の手で調べてみてください。世界が均衡を崩しかけ、今また原子力政策や核抑止を意識せざるを得ない情勢だからこそ、観る価値のある作品と言えますね。他のクリストファー・ノーラン作品にも同様の傾向がありますが、後々自宅で観られるようになっても恐らく劇場鑑賞ほどに鮮烈な印象は残さないタイプなので、長いからと言わず気になっているならスクリーンで鑑賞することをお薦めします。
先日、ロングラン上映中の「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」の応援上映に行って来ました。ちょっとお祭り感のある映画だったので初見でも応援上映とかと相性良いだろうな〜と思って臨んでみましたが、思った以上に好相性で滅茶苦茶楽しい。ズゴッグに歓声上げられる機会なぞそうそうありませんて(笑)
こんばんは、小島@監督です。
FREEDOMの応援上映、今のところ今週4日にも予定されています。たまには映画館で声を張り上げるスタイルで観るのも一興。居合わせた観客との運もあるので若干ギャンブルみもありますが。
さて、今回の映画は「荒野の用心棒」です。
アメリカ・メキシコ国境付近の小さな町に1人の名無しのガンマン(クリント・イーストウッド)がふらりと流れ着いた。その町ではドン・ミゲル(アントニオ・プリエート)らロホ兄弟と悪徳保安官バクスター(ウォルフガング・ルスキー)が抗争を繰り広げて死者が続出しており、儲かるのは棺桶屋だけと言われるほどの事態となっていた。名無しの男はバクスターの手下を早撃ちで倒すと自身をロホ兄弟に売り込むのだった。
1960〜70年代前半にかけて量産されたイタリア製西部劇、映画評論家淀川長治氏によって「マカロニ・ウェスタン」と名付けられたそのジャンルは、基本的にはアメリカ西部劇を踏襲しながらもアウトロー的な主人公像やハードなバイオレンス描写で、よりエンターテインメント色が強い作風が特徴です。マカロニ・ウェスタンが世界的に知られるようになったきっかけと言われているのが1964年に製作されアメリカでも大ヒットを博した「荒野の用心棒」です。黒澤明の「用心棒」を西部劇に仕立て直したこの作品は東宝や黒澤明の許可を得ないで作られたため、後年東宝と裁判にまでなった逸話もあります。この映画と後に製作されたクリント・イーストウッド主演の「夕陽のガンマン」「続・夕陽のガンマン」の2作品を合わせて「ドル箱三部作」と呼ばれています(多額の興行収益を叩き出した、ということではなく最初の2作の原題に「dollar」が入ってるから)。最近三部作揃って4Kリマスター版が製作され現在一挙上映が始まっています。TV放送やレンタルなどで観たことはあるものの劇場鑑賞はしたことなかったこの三部作の1作を先日観てきました。
冒頭いきなり観客を鷲掴みする口笛のテーマ曲を手掛けたのは映画音楽の巨匠エンニオ・モリコーネ。からりとしたドライなテイストと激しいガンファイトで物語に引き込む手腕を見せつけるのは監督セルジオ・レオーネ。いずれも後に世界的名声を得ることになる彼らの、その知名度を上げるきっかけとなった作品です。
ずっと昔にTVで観ているので内容は知っていたものの、ちゃんとスクリーンで観るとその凄みに震えます。以前に観てるからというだけでなくそこらじゅうで他作品からの既視感を覚えるのでついパロディだらけに錯覚してしまうくらいですが、でも出元はこっち。予備知識も無いままこれを直撃した方たちの衝撃はいかばかりか。後続に与えた影響の計り知れない大きさを実感します。
一つのジャンルを確立してみせた作品のパワーは数十年の時を経ても色褪せない。
「午前10時の映画祭」に限らずとも近年シネコンでも旧作の上映が増えたのはコロナ禍がもたらした影響の一つでしょうか。口笛一つに痺れる経験もなかなか無いので是非この機会を捕まえて欲しいですね。
なお、三部作とは言うけれど監督・主演・音楽が同じと言うだけで作品自体は全く連続していないので、どこから観てもOKですよ。
こんばんは、小島@監督です。
FREEDOMの応援上映、今のところ今週4日にも予定されています。たまには映画館で声を張り上げるスタイルで観るのも一興。居合わせた観客との運もあるので若干ギャンブルみもありますが。
さて、今回の映画は「荒野の用心棒」です。
アメリカ・メキシコ国境付近の小さな町に1人の名無しのガンマン(クリント・イーストウッド)がふらりと流れ着いた。その町ではドン・ミゲル(アントニオ・プリエート)らロホ兄弟と悪徳保安官バクスター(ウォルフガング・ルスキー)が抗争を繰り広げて死者が続出しており、儲かるのは棺桶屋だけと言われるほどの事態となっていた。名無しの男はバクスターの手下を早撃ちで倒すと自身をロホ兄弟に売り込むのだった。
1960〜70年代前半にかけて量産されたイタリア製西部劇、映画評論家淀川長治氏によって「マカロニ・ウェスタン」と名付けられたそのジャンルは、基本的にはアメリカ西部劇を踏襲しながらもアウトロー的な主人公像やハードなバイオレンス描写で、よりエンターテインメント色が強い作風が特徴です。マカロニ・ウェスタンが世界的に知られるようになったきっかけと言われているのが1964年に製作されアメリカでも大ヒットを博した「荒野の用心棒」です。黒澤明の「用心棒」を西部劇に仕立て直したこの作品は東宝や黒澤明の許可を得ないで作られたため、後年東宝と裁判にまでなった逸話もあります。この映画と後に製作されたクリント・イーストウッド主演の「夕陽のガンマン」「続・夕陽のガンマン」の2作品を合わせて「ドル箱三部作」と呼ばれています(多額の興行収益を叩き出した、ということではなく最初の2作の原題に「dollar」が入ってるから)。最近三部作揃って4Kリマスター版が製作され現在一挙上映が始まっています。TV放送やレンタルなどで観たことはあるものの劇場鑑賞はしたことなかったこの三部作の1作を先日観てきました。
冒頭いきなり観客を鷲掴みする口笛のテーマ曲を手掛けたのは映画音楽の巨匠エンニオ・モリコーネ。からりとしたドライなテイストと激しいガンファイトで物語に引き込む手腕を見せつけるのは監督セルジオ・レオーネ。いずれも後に世界的名声を得ることになる彼らの、その知名度を上げるきっかけとなった作品です。
ずっと昔にTVで観ているので内容は知っていたものの、ちゃんとスクリーンで観るとその凄みに震えます。以前に観てるからというだけでなくそこらじゅうで他作品からの既視感を覚えるのでついパロディだらけに錯覚してしまうくらいですが、でも出元はこっち。予備知識も無いままこれを直撃した方たちの衝撃はいかばかりか。後続に与えた影響の計り知れない大きさを実感します。
一つのジャンルを確立してみせた作品のパワーは数十年の時を経ても色褪せない。
「午前10時の映画祭」に限らずとも近年シネコンでも旧作の上映が増えたのはコロナ禍がもたらした影響の一つでしょうか。口笛一つに痺れる経験もなかなか無いので是非この機会を捕まえて欲しいですね。
なお、三部作とは言うけれど監督・主演・音楽が同じと言うだけで作品自体は全く連続していないので、どこから観てもOKですよ。

