本来なら休みやすい閑散期なのに色々とワケありで実質2週間休み無しというエグい期間をどうにか脱したら昨日は約半日眠り込んでました。実は無休3週目に突入する可能性も生じていたのですが、何とか回避できてホッとしています。
こんばんは、小島@監督です。
次に似たような事態になった時は絶対に1日だけでも休みを確保しようと心に決めました。
さて、そんなワケでしばらく映画を観に行くどころではなかったので今週は自宅で鑑賞した中から1本。今回の映画は「千年女優」です。
戦前から戦後にかけて長く使われてきた映画会社「銀映」のスタジオが老朽化のために取り壊されることになった。若い頃に銀映に所属し、今は映像制作会社「LOTUS」の社長を務める立花(声・飯塚昭三、佐藤政道(青年期))は、銀映のドキュメンタリー制作のために伝説の大女優・藤原千代子(声・荘司美代子、小山茉美(20~40代)、折笠富美子(10~20代))へのインタビューを企画する。約30年間表舞台に立たず、取材も一切受けなかった千代子に、立花はインタビュー前にある小箱を渡す。その小箱には古い鍵が入っていた。
2010年に46歳の若さで没したアニメーション監督今敏、生涯で手掛けた4本の劇場用長編は全てが代表作と言っていい唯一無二の存在感を放ったクリエイターです。その今敏監督が2001年に発表した長編が「千年女優」です。当時設立されてまだ日の浅かった文化庁メディア芸術祭アニメーション部門大賞に「千と千尋の神隠し」と同時受賞したほか、国内外で高い評価を得た作品です。ソフト化はもちろんされているものの案外サブスク系の配信からは縁遠かった1本ですが、今月からNetflixでの視聴が可能になり鑑賞のハードルがグッと下がりました。私もかなり長い間遠ざかっていたのですが今回を機に久しぶりの鑑賞です。
手掛けた4本の長編全てがオリジナル作品であった今敏監督、全てに通底して使われていたモチーフが「虚構と現実の混濁」です。次第に現実と虚構の境界が曖昧になっていく中で登場人物だけでなく観る者も翻弄していくのが特徴で、それはこの「千年女優」でも変わりません。立花の千代子へのインタビューが進むにつれ、現在と過去、そして千代子が出演した映画と言う虚構がシームレスに混じりあっていきます。「千年女優」の面白いところは、そういった虚実混交がただ観客を惑わす叙述トリックのように使われるのではなくユーモラスな冒険活劇として描き出し、その幻惑的な奔流に飲まれること自体を楽しませる作風をしている点です。
時代も虚構も行き来しながら描かれるのは幼い日に千代子が出会った「鍵の君」(声・山寺宏一)への恋心とそれに突き動かされる情熱的な姿です。故に、千代子は全編を通して良く走ります。駆け抜けていると言っても良い。恋しい人を追い求め走り続ける千代子の姿、ただそれだけに見事なまでの映画的快感が宿っているところにこの映画の凄みがあります。
また、「千年女優」は今敏監督作品と切り離して語れない要素の一つである平沢進の音楽が初めて使われた作品でもあります。作中のエピソードは時代も場所も変えながらも基本的には「追い、走り、時に転ぶ」を繰り返す物語であるものの、そのリフレインは平沢進のプログレッシブ・サウンドが彩ることでただの繰り返しではなくなり、前述の「ただ走るだけのシーンに映画的快感が宿る」ことをより確かなものにしています。
ラストシーンで千代子が言い放つセリフが小粋でありながらも衝撃的で、不思議な爽やかさと同時に「転ばされた」感覚を観客に残す見事な大団円。しかもそれでいて上映時間が87分というコンパクトさ。最初から最後まで高密度に楽しませてくれます。
アニメならではの表現と映画ならではの味わいが詰め込まれた、稀代のクリエイターであった今敏監督のテイストを存分に味わえるこの1本、Netflixでの配信を機により多くの方の目に触れて再確認と再評価が進むと嬉しいですね。
こんばんは、小島@監督です。
次に似たような事態になった時は絶対に1日だけでも休みを確保しようと心に決めました。
さて、そんなワケでしばらく映画を観に行くどころではなかったので今週は自宅で鑑賞した中から1本。今回の映画は「千年女優」です。
戦前から戦後にかけて長く使われてきた映画会社「銀映」のスタジオが老朽化のために取り壊されることになった。若い頃に銀映に所属し、今は映像制作会社「LOTUS」の社長を務める立花(声・飯塚昭三、佐藤政道(青年期))は、銀映のドキュメンタリー制作のために伝説の大女優・藤原千代子(声・荘司美代子、小山茉美(20~40代)、折笠富美子(10~20代))へのインタビューを企画する。約30年間表舞台に立たず、取材も一切受けなかった千代子に、立花はインタビュー前にある小箱を渡す。その小箱には古い鍵が入っていた。
2010年に46歳の若さで没したアニメーション監督今敏、生涯で手掛けた4本の劇場用長編は全てが代表作と言っていい唯一無二の存在感を放ったクリエイターです。その今敏監督が2001年に発表した長編が「千年女優」です。当時設立されてまだ日の浅かった文化庁メディア芸術祭アニメーション部門大賞に「千と千尋の神隠し」と同時受賞したほか、国内外で高い評価を得た作品です。ソフト化はもちろんされているものの案外サブスク系の配信からは縁遠かった1本ですが、今月からNetflixでの視聴が可能になり鑑賞のハードルがグッと下がりました。私もかなり長い間遠ざかっていたのですが今回を機に久しぶりの鑑賞です。
手掛けた4本の長編全てがオリジナル作品であった今敏監督、全てに通底して使われていたモチーフが「虚構と現実の混濁」です。次第に現実と虚構の境界が曖昧になっていく中で登場人物だけでなく観る者も翻弄していくのが特徴で、それはこの「千年女優」でも変わりません。立花の千代子へのインタビューが進むにつれ、現在と過去、そして千代子が出演した映画と言う虚構がシームレスに混じりあっていきます。「千年女優」の面白いところは、そういった虚実混交がただ観客を惑わす叙述トリックのように使われるのではなくユーモラスな冒険活劇として描き出し、その幻惑的な奔流に飲まれること自体を楽しませる作風をしている点です。
時代も虚構も行き来しながら描かれるのは幼い日に千代子が出会った「鍵の君」(声・山寺宏一)への恋心とそれに突き動かされる情熱的な姿です。故に、千代子は全編を通して良く走ります。駆け抜けていると言っても良い。恋しい人を追い求め走り続ける千代子の姿、ただそれだけに見事なまでの映画的快感が宿っているところにこの映画の凄みがあります。
また、「千年女優」は今敏監督作品と切り離して語れない要素の一つである平沢進の音楽が初めて使われた作品でもあります。作中のエピソードは時代も場所も変えながらも基本的には「追い、走り、時に転ぶ」を繰り返す物語であるものの、そのリフレインは平沢進のプログレッシブ・サウンドが彩ることでただの繰り返しではなくなり、前述の「ただ走るだけのシーンに映画的快感が宿る」ことをより確かなものにしています。
ラストシーンで千代子が言い放つセリフが小粋でありながらも衝撃的で、不思議な爽やかさと同時に「転ばされた」感覚を観客に残す見事な大団円。しかもそれでいて上映時間が87分というコンパクトさ。最初から最後まで高密度に楽しませてくれます。
アニメならではの表現と映画ならではの味わいが詰め込まれた、稀代のクリエイターであった今敏監督のテイストを存分に味わえるこの1本、Netflixでの配信を機により多くの方の目に触れて再確認と再評価が進むと嬉しいですね。
今年の夏は(も?)電力不足がかなり不安視されるようで、
政府や電力会社が使用量の抑制に力を入れ始めました。
とにかく、エアコンの温度を低くし過ぎないようにするとか、
家族が一つの部屋に集まるとかして節電に努めようと、
そんな要請ばかりが目に付くのですが、では対策は?
どうも展開されている電力供給の対策を見ている感じでは、
結局何もしないとしか認識できない案ばかりが目立ちます。
なんか気になるのはその中で原子力発電をするという、
選択は一切触れられていなかったりするのです。
送電が止まり、熱中症など死者が出たらどうするのでしょう。
さて、先日は会社の食堂で隣のテーブルに座っている、
顔しか知らないような社員の会話が聞こえてきました。
その社員、ファミリーマート限定のアイスにハマり、
毎日のように食べているということを言っています。
男性のその社員がやたらと同席の同僚に熱弁しており、
それを聞いた同僚も「買ってみるわ」みたいな返事。
もうお前はOLかと思わんばかりのスイーツ推しです。
まあ確かに、それだけ推されれば、アイスくらいは、
それほど高いものでもないし買ってみるかもですよね。
その時は他人の会話くらいにしか思っていなかったが、
帰宅時にファミリーマートに寄ったときに会話を思い出し、
そのアイスの銘柄もしっかり覚えていたので、つい購入。
「毎日のように食べ」られているアイスはどんなもんかと、
その時は勝手にとても美味しいと思い込んでいる私。
せっかくだからと一番美味しく食べられそうなのは、
やっぱり風呂上りですよねと判断しつつ帰宅しました。
家に帰って冷蔵庫に放り込み、風呂あがりに実食です。
さあ、どんなもんだとすでにハードルの上がり過ぎた、
そのアイスをついに食べる時がやってまいりました。
が、実際に食べてみるともう全然普通で美味しさも普通です。
毎日食べるほどに焚きつける何かに私は気が付けません
そんな、知らない社員のCM効果に乗せられた私でした。
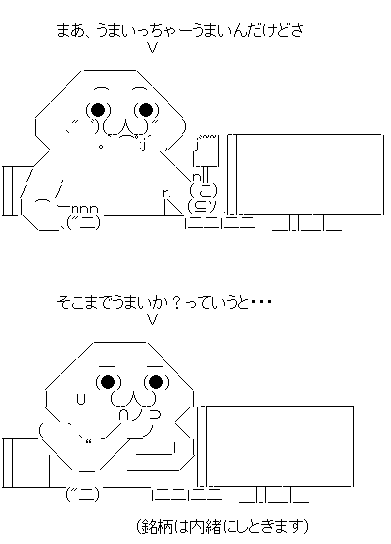
政府や電力会社が使用量の抑制に力を入れ始めました。
とにかく、エアコンの温度を低くし過ぎないようにするとか、
家族が一つの部屋に集まるとかして節電に努めようと、
そんな要請ばかりが目に付くのですが、では対策は?
どうも展開されている電力供給の対策を見ている感じでは、
結局何もしないとしか認識できない案ばかりが目立ちます。
なんか気になるのはその中で原子力発電をするという、
選択は一切触れられていなかったりするのです。
送電が止まり、熱中症など死者が出たらどうするのでしょう。
さて、先日は会社の食堂で隣のテーブルに座っている、
顔しか知らないような社員の会話が聞こえてきました。
その社員、ファミリーマート限定のアイスにハマり、
毎日のように食べているということを言っています。
男性のその社員がやたらと同席の同僚に熱弁しており、
それを聞いた同僚も「買ってみるわ」みたいな返事。
もうお前はOLかと思わんばかりのスイーツ推しです。
まあ確かに、それだけ推されれば、アイスくらいは、
それほど高いものでもないし買ってみるかもですよね。
その時は他人の会話くらいにしか思っていなかったが、
帰宅時にファミリーマートに寄ったときに会話を思い出し、
そのアイスの銘柄もしっかり覚えていたので、つい購入。
「毎日のように食べ」られているアイスはどんなもんかと、
その時は勝手にとても美味しいと思い込んでいる私。
せっかくだからと一番美味しく食べられそうなのは、
やっぱり風呂上りですよねと判断しつつ帰宅しました。
家に帰って冷蔵庫に放り込み、風呂あがりに実食です。
さあ、どんなもんだとすでにハードルの上がり過ぎた、
そのアイスをついに食べる時がやってまいりました。
が、実際に食べてみるともう全然普通で美味しさも普通です。
毎日食べるほどに焚きつける何かに私は気が付けません
そんな、知らない社員のCM効果に乗せられた私でした。
今日の昼ごろ突如流れてきた、湯川英一元SEGA専務の訃報がなかなかショック。それも昨年の内に亡くなられたと言うではないですか。「SEGAなんてダセーよな」という自虐的なCMに出演して反響を呼びドリームキャストの販促を担った来歴は、クリエイターではなかったにしろゲーム史の1ページに刻まれて然るべき方ではないかと思います。
謹んでお悔やみ申し上げます。
こんばんは、小島@監督です。
ドリームキャストはちょうど学生から社会人になろうかという頃にこれでもかとばかりに遊んだハードなので結構思い入れが深いです。SEGAは今年秋にメガドライブmini2の発売を予定していますが、いずれサターンminiとドリームキャストminiも製作して欲しいなとかなりマジに願っています。
さて、今回の映画は「トップガン マーヴェリック」です。
ピート・”マーヴェリック”・ミッチェル大佐(トム・クルーズ)は華々しい戦績を持つ伝説的なパイロットだったが、今は超音速実験機「ダークスター」のテストパイロットの任に就いていた。しかし、AIによるドローン戦闘機の開発を推し進めたいケイン少将(エド・ハリス)によりプログラムは中止させられようとしていることを知り、マーヴェリックはケインの前でダークスターを目標速度のマッハ10に到達させることに成功するが、ダークスターは空中分解してしまった。
懲罰を覚悟していたマーヴェリックだったが、思わぬ辞令が下る。高難度のミッションのために召集された「トップガン」たちに任務成功のための訓練教官を務めて欲しいと言うのだ。そうして集められたパイロットたちの中には、かつてマーヴェリックの相棒だったグースの息子ブラッドリー・“ルースター”・ブラッドショウ(マイルズ・テラー)もいた…
コロナ禍によって多くの映画が延期や上映中止の憂き目に遭いました。あるものは公開規模が大幅に縮小され、あるものはスクリーンでの上映を断念し配信に発表のフォーマットを移しました。そもそも映画館が営業できないという状況すら発生し、結果的に配信による収益が製作会社にとっても無視できないものになり、「映画館で映画を観る」行為そのものの存在意義すら揺らぎ始めたこの数年にあって、何度も延期を重ねながらも頑なに映画館での上映にこだわり続けた「トップガン マーヴェリック」が遂に公開されました。
1986年に製作され80年代カルチャーのアイコンの一つともいえる「トップガン」、実に36年越しの続編です。当時から既に人気の高かった作品であったにもかかわらずここまで続編が製作されなかったのは、安易な続編が製作されることを嫌ったトム・クルーズが続編製作権を自分で買い取ってしまったからです。その後2010年ごろに一度企画が立ち上がり、製作を担ったジェリー・ブラッカイマーとトニー・スコット監督、トム・クルーズの3人でシナリオハンティングが行われていたそうですが、2012年のトニー・スコット死去により頓挫。改めて仕切り直しとなったところに「ミッション・インポッシブル/フォールアウト」などでトム・クルーズと組んだ脚本家クリストファー・マッカリーと同じくトム・クルーズが主演した「オブリビオン」で監督を務めたジョセフ・コシンスキーが招聘されて本格的に製作が開始されました。
物語の大きな特徴として、前作からの30数年という時間が常に横たわっている所にあります。マーヴェリックは現役にこだわり頑なに昇進も引退も拒んでいますが、同期の仲間は将官に出世するか退官していたり、当時主力だったF-14トムキャットも空母エンタープライズも既に退役、80年代にはいなかった女性パイロットの台頭、AIと無人戦闘機がパイロットという存在自体を過去へと押しやろうとする気配すら現れます。マーヴェリック自身にもどこか「老い」の兆しが見え始めています。そういう中にあって戦闘機パイロットとしての「矜持」を描き出し、マーヴェリックとルースターの確執が軸として貫かれています。
そして何よりこの映画最大のポイントはもちろんスカイアクション。そこら辺のアクション映画のカーチェイスを超える激烈なボリュームで空戦が展開。CG全盛の世にあってガチで実機を飛ばし俳優たちがハイGの中で顔をゆがめながら演技をするというとんでもないシーンが頻発します。何なら「単座型の航空機に乗っているシーンなのにヘルメットのバイザーに前部座席が映り込んでて複座型の後部座席に乗り込んでるのが分かる」ショットもあったりするのですが結果的にマジで飛んでいることの証明になっているという、えげつない逆説がフィルムに焼き付けられています。
こんな無茶が通ってしまうのもトム・クルーズならではでしょう。彼以外ではありえない、そんな凄味が作品内に満ち溢れています。
映像と音響、全てが一体となり、観客が経験するのは映画を鑑賞することではなく「映画を体感する」こと。トム・クルーズが映画館での上映にこだわった理由がここにあります。作中パイロットが過去の遺物とされようとしているように、CGやAIが発達していつかこんな危険なスタイルで映画を作る必要が無くなるかもしれない。事実こんな80年代スタイルを突き詰めたような製作体制はある意味で時代遅れでしょう。配信というフォーマットの定着によってカリスマ的なムービースターという存在も過去のものとなってしまうかもしれない。時代の潮流は止められない。けれどまだ「映画を映画館で観る」という経験には何物にも代えがたい意味がある。この映画を観る事は、その「意味」を真正面で受け止める事に他なりません。まさに自身の存在全てを懸けて「映画を観る喜び」を追求するトム・クルーズの姿は最早「孤高」と呼べる存在感です。
観る者に忘れ得ぬ2時間の「非日常」をもたらすこの作品、10年後、20年後にこの映画を懐かしく思い返す日がきっと来る。時代の流れをものともせず屹立する誇り高きラスト・ボーイスカウトが魅せる輝きをどうかその目に焼き付けて欲しい。
「映画」が、ここにあります。
謹んでお悔やみ申し上げます。
こんばんは、小島@監督です。
ドリームキャストはちょうど学生から社会人になろうかという頃にこれでもかとばかりに遊んだハードなので結構思い入れが深いです。SEGAは今年秋にメガドライブmini2の発売を予定していますが、いずれサターンminiとドリームキャストminiも製作して欲しいなとかなりマジに願っています。
さて、今回の映画は「トップガン マーヴェリック」です。
ピート・”マーヴェリック”・ミッチェル大佐(トム・クルーズ)は華々しい戦績を持つ伝説的なパイロットだったが、今は超音速実験機「ダークスター」のテストパイロットの任に就いていた。しかし、AIによるドローン戦闘機の開発を推し進めたいケイン少将(エド・ハリス)によりプログラムは中止させられようとしていることを知り、マーヴェリックはケインの前でダークスターを目標速度のマッハ10に到達させることに成功するが、ダークスターは空中分解してしまった。
懲罰を覚悟していたマーヴェリックだったが、思わぬ辞令が下る。高難度のミッションのために召集された「トップガン」たちに任務成功のための訓練教官を務めて欲しいと言うのだ。そうして集められたパイロットたちの中には、かつてマーヴェリックの相棒だったグースの息子ブラッドリー・“ルースター”・ブラッドショウ(マイルズ・テラー)もいた…
コロナ禍によって多くの映画が延期や上映中止の憂き目に遭いました。あるものは公開規模が大幅に縮小され、あるものはスクリーンでの上映を断念し配信に発表のフォーマットを移しました。そもそも映画館が営業できないという状況すら発生し、結果的に配信による収益が製作会社にとっても無視できないものになり、「映画館で映画を観る」行為そのものの存在意義すら揺らぎ始めたこの数年にあって、何度も延期を重ねながらも頑なに映画館での上映にこだわり続けた「トップガン マーヴェリック」が遂に公開されました。
1986年に製作され80年代カルチャーのアイコンの一つともいえる「トップガン」、実に36年越しの続編です。当時から既に人気の高かった作品であったにもかかわらずここまで続編が製作されなかったのは、安易な続編が製作されることを嫌ったトム・クルーズが続編製作権を自分で買い取ってしまったからです。その後2010年ごろに一度企画が立ち上がり、製作を担ったジェリー・ブラッカイマーとトニー・スコット監督、トム・クルーズの3人でシナリオハンティングが行われていたそうですが、2012年のトニー・スコット死去により頓挫。改めて仕切り直しとなったところに「ミッション・インポッシブル/フォールアウト」などでトム・クルーズと組んだ脚本家クリストファー・マッカリーと同じくトム・クルーズが主演した「オブリビオン」で監督を務めたジョセフ・コシンスキーが招聘されて本格的に製作が開始されました。
物語の大きな特徴として、前作からの30数年という時間が常に横たわっている所にあります。マーヴェリックは現役にこだわり頑なに昇進も引退も拒んでいますが、同期の仲間は将官に出世するか退官していたり、当時主力だったF-14トムキャットも空母エンタープライズも既に退役、80年代にはいなかった女性パイロットの台頭、AIと無人戦闘機がパイロットという存在自体を過去へと押しやろうとする気配すら現れます。マーヴェリック自身にもどこか「老い」の兆しが見え始めています。そういう中にあって戦闘機パイロットとしての「矜持」を描き出し、マーヴェリックとルースターの確執が軸として貫かれています。
そして何よりこの映画最大のポイントはもちろんスカイアクション。そこら辺のアクション映画のカーチェイスを超える激烈なボリュームで空戦が展開。CG全盛の世にあってガチで実機を飛ばし俳優たちがハイGの中で顔をゆがめながら演技をするというとんでもないシーンが頻発します。何なら「単座型の航空機に乗っているシーンなのにヘルメットのバイザーに前部座席が映り込んでて複座型の後部座席に乗り込んでるのが分かる」ショットもあったりするのですが結果的にマジで飛んでいることの証明になっているという、えげつない逆説がフィルムに焼き付けられています。
こんな無茶が通ってしまうのもトム・クルーズならではでしょう。彼以外ではありえない、そんな凄味が作品内に満ち溢れています。
映像と音響、全てが一体となり、観客が経験するのは映画を鑑賞することではなく「映画を体感する」こと。トム・クルーズが映画館での上映にこだわった理由がここにあります。作中パイロットが過去の遺物とされようとしているように、CGやAIが発達していつかこんな危険なスタイルで映画を作る必要が無くなるかもしれない。事実こんな80年代スタイルを突き詰めたような製作体制はある意味で時代遅れでしょう。配信というフォーマットの定着によってカリスマ的なムービースターという存在も過去のものとなってしまうかもしれない。時代の潮流は止められない。けれどまだ「映画を映画館で観る」という経験には何物にも代えがたい意味がある。この映画を観る事は、その「意味」を真正面で受け止める事に他なりません。まさに自身の存在全てを懸けて「映画を観る喜び」を追求するトム・クルーズの姿は最早「孤高」と呼べる存在感です。
観る者に忘れ得ぬ2時間の「非日常」をもたらすこの作品、10年後、20年後にこの映画を懐かしく思い返す日がきっと来る。時代の流れをものともせず屹立する誇り高きラスト・ボーイスカウトが魅せる輝きをどうかその目に焼き付けて欲しい。
「映画」が、ここにあります。
最近、私のYouTubeへのオススメ動画の中にやたらと、
『きつねダンス』なるものが幅を利かせ始めました。
きつねダンスとは、プロ野球『日本ハムファイターズ』の、
チアガールである『ファイターズガール』が試合間に、
軽快なメロディで踊る、きつねっぽいダンスらしいです。
いくつかきつねダンスの動画を見ちゃったものだから、
現在、私の動画のオススメにやたら出てきてしまいます。
最初「何これ?」と思って再生した時の印象としては、
「また、あざとい事をやりだした」と言った感じでしたが、
そのうち、これはこれで可愛くクセになりそうな感じ。
さて、新型コロナウイルス感染者も、少し落ち着きました。
依然のように感染者一桁までの減少とはいきませんが、
そろそろ歌会再開に向けての準備もアリかなと思います。
ちゅうカラスタッフ同士でも、国や県の規制が無い以上、
歌会の再開に向けて話合いを進め始めたところです。
とは言え、カラオケをするのは今回のウイルスに対して、
矢面な案件だったりへするので気をつけたいところ。
開催する以上は守るべきところは、押さえておきたい。
そんなカラオケに対して、こんなニュースがありました。
これはちょっと参考になるので紹介したいと思います。
それは!日本が誇るスーパーコンピュータ『富岳』で、
カラオケ店での『飛沫シミュレーション』の実施です。
その感染リスクについての研究結果が紹介されました。
富岳での感染リスクシミュレーション
もちろんそれなりの感染対策をしてという前提ですが、
そこまで感染率が高いという結果は出ていなかったりします。
かと言って、カラオケを安心して楽しんでいいワケでなく、
やっぱりそれなりのリスクはどうしてもあるようですね。
緩やかではありますが、感染者の減少傾向となった今、
7月、もしくは8月の開催、みなさんの考えはどうでしょうか。
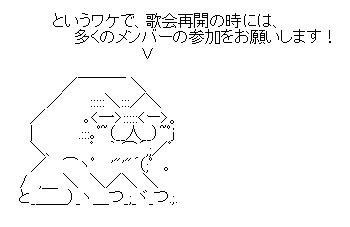
『きつねダンス』なるものが幅を利かせ始めました。
きつねダンスとは、プロ野球『日本ハムファイターズ』の、
チアガールである『ファイターズガール』が試合間に、
軽快なメロディで踊る、きつねっぽいダンスらしいです。
いくつかきつねダンスの動画を見ちゃったものだから、
現在、私の動画のオススメにやたら出てきてしまいます。
最初「何これ?」と思って再生した時の印象としては、
「また、あざとい事をやりだした」と言った感じでしたが、
そのうち、これはこれで可愛くクセになりそうな感じ。
さて、新型コロナウイルス感染者も、少し落ち着きました。
依然のように感染者一桁までの減少とはいきませんが、
そろそろ歌会再開に向けての準備もアリかなと思います。
ちゅうカラスタッフ同士でも、国や県の規制が無い以上、
歌会の再開に向けて話合いを進め始めたところです。
とは言え、カラオケをするのは今回のウイルスに対して、
矢面な案件だったりへするので気をつけたいところ。
開催する以上は守るべきところは、押さえておきたい。
そんなカラオケに対して、こんなニュースがありました。
これはちょっと参考になるので紹介したいと思います。
それは!日本が誇るスーパーコンピュータ『富岳』で、
カラオケ店での『飛沫シミュレーション』の実施です。
その感染リスクについての研究結果が紹介されました。
富岳での感染リスクシミュレーション
もちろんそれなりの感染対策をしてという前提ですが、
そこまで感染率が高いという結果は出ていなかったりします。
かと言って、カラオケを安心して楽しんでいいワケでなく、
やっぱりそれなりのリスクはどうしてもあるようですね。
緩やかではありますが、感染者の減少傾向となった今、
7月、もしくは8月の開催、みなさんの考えはどうでしょうか。
職場で私と組んで仕事している方が今週の半ばから10日間ほど入院する事になり、その影響で今来週は休み無しというちょいとハードスケジュールに突入。その前にやれるだけやっておこうと一昨日の土曜日は病院行ってカラオケ行って映画2本観るというちょっとやり過ぎた感のある予定の詰めっぷりで1日過ごしてました。
こんばんは、小島@監督です。
充実感も半端無かったけれど、もう少しゆったり日程組みたいかな、出来れば(笑)
さて、今109シネマズ名古屋にて「109シネマズ名古屋映画祭」と題してライブ向けの音響機材をセッティングして通常とは違う音響環境で映画を鑑賞する「ライブ音響上映」が31日まで実施されています。今回はその上映作品の中から一つ、「アイの歌声を聴かせて」です。
母一人子一人の家庭で暮らす高校生のサトミ(声・福原遥)は、ある事件から校内で「告げ口姫」と揶揄され疎外されていた。
AIの開発責任者を務める母のミツコ(声・大原さやか)は新型AIを搭載した人型アンドロイド・シオン(声・土屋太鳳)を開発し、その実地試験としてシオンをサトミの通うクラスに転校生として送り込んだ。期限は5日間、その間にシオンがアンドロイドと他の人間にバレなければ成功だ。
しかしシオンは何故かサトミを知っていて、サトミを見るなり駆け寄って歌い出してしまった。その後もおかしな行動を繰り返すシオンに振り回されるサトミは、ひょんなことからシオンがアンドロイドであることを知ってしまう。母ミツコのためにサトミはどうにかシオンの正体を隠し通そうとするが…
「イヴの時間」「サカサマのパテマ」など独創的な世界観のオリジナル・アニメーションを作り上げる吉浦康裕監督の最新作です。昨年10月に公開され、観客の口コミによって評判が広まり、既にレンタル配信なども始まりBlu-rayの発売も目前に迫っている状況にもかかわらず小規模ながら現在も上映が続いている作品です。伝え聞いた評判に、気になっていた作品だったのですが思いもかけない形で鑑賞の機会を掴みました。
牧歌的な田園都市の風景の中に目立つAIのための開発研究所であるツインタワーが建っていたり水田のように見える場所が実はメガソーラーだったりという実験都市的な性格を持つ地方都市を舞台に展開する青春SFミュージカル活劇です。
クラスに疎外されるサトミをはじめ、機械オタクで人づきあいが苦手なトウマ(声・工藤阿須加)、柔道部員で腕前は良いのだが本番に弱いサンダー(声・日野聡)、恋人同士だが現在喧嘩中で気まずい雰囲気が流れるゴっちゃん(声・興津和幸)とアヤ(声・小松未可子)ら青春の悩みを抱える高校生たちがシオンの登場と突拍子もない行動に振り回されながら次第に葛藤から解きほぐされていきます。
ミュージカルのお約束である「登場人物が前触れなく突然歌い出す」という振る舞いを「AIがずれた行動取ってるから」で説明づけるアイディアが秀逸。しかもシオン役土屋太鳳の歌声が絶品です。そしてその「突然歌い出す」ことも物語の主舞台である実験都市というロケーションも全てちゃんとクライマックスに活きてくる作劇の妙が素晴らしい。変にハードな方向に転がり込むことなくある種の楽天的な雰囲気を持たせながらの語り口が心地よく、「何故シオンは最初からサトミを知っていたのか?」「何故唐突に歌いたがるのか?」「そして何故サトミの幸せをひたすらに希求するのか?」これらの謎が明かされる頃には観る者の心に涼やかな風が吹いているはずです。その涼風に力強さも加わって突き進む終盤と、その後にたどり着く結末の余韻も実に爽やかです。
青春映画の新たな傑作の誕生と言って良く、現時点における吉浦康裕監督のキャリア・ベストじゃないでしょうか。長く支持を集める理由も観て分かるというものです。是非多くの方にご鑑賞いただきたい逸品ですね。
ところで109シネマズ名古屋などで不定期に開催される、音響機材をシアター内に設えての特別上映、敢えてやってみて分かりましたが通常の映画鑑賞では決して良い位置とは言えない最前列中央が恐らく一番醍醐味を堪能できるポジションです。いやもう音圧が凄いのなんの。没入度が半端じゃないです。機会を捕まえたら是非トライして頂きたい。
こんばんは、小島@監督です。
充実感も半端無かったけれど、もう少しゆったり日程組みたいかな、出来れば(笑)
さて、今109シネマズ名古屋にて「109シネマズ名古屋映画祭」と題してライブ向けの音響機材をセッティングして通常とは違う音響環境で映画を鑑賞する「ライブ音響上映」が31日まで実施されています。今回はその上映作品の中から一つ、「アイの歌声を聴かせて」です。
母一人子一人の家庭で暮らす高校生のサトミ(声・福原遥)は、ある事件から校内で「告げ口姫」と揶揄され疎外されていた。
AIの開発責任者を務める母のミツコ(声・大原さやか)は新型AIを搭載した人型アンドロイド・シオン(声・土屋太鳳)を開発し、その実地試験としてシオンをサトミの通うクラスに転校生として送り込んだ。期限は5日間、その間にシオンがアンドロイドと他の人間にバレなければ成功だ。
しかしシオンは何故かサトミを知っていて、サトミを見るなり駆け寄って歌い出してしまった。その後もおかしな行動を繰り返すシオンに振り回されるサトミは、ひょんなことからシオンがアンドロイドであることを知ってしまう。母ミツコのためにサトミはどうにかシオンの正体を隠し通そうとするが…
「イヴの時間」「サカサマのパテマ」など独創的な世界観のオリジナル・アニメーションを作り上げる吉浦康裕監督の最新作です。昨年10月に公開され、観客の口コミによって評判が広まり、既にレンタル配信なども始まりBlu-rayの発売も目前に迫っている状況にもかかわらず小規模ながら現在も上映が続いている作品です。伝え聞いた評判に、気になっていた作品だったのですが思いもかけない形で鑑賞の機会を掴みました。
牧歌的な田園都市の風景の中に目立つAIのための開発研究所であるツインタワーが建っていたり水田のように見える場所が実はメガソーラーだったりという実験都市的な性格を持つ地方都市を舞台に展開する青春SFミュージカル活劇です。
クラスに疎外されるサトミをはじめ、機械オタクで人づきあいが苦手なトウマ(声・工藤阿須加)、柔道部員で腕前は良いのだが本番に弱いサンダー(声・日野聡)、恋人同士だが現在喧嘩中で気まずい雰囲気が流れるゴっちゃん(声・興津和幸)とアヤ(声・小松未可子)ら青春の悩みを抱える高校生たちがシオンの登場と突拍子もない行動に振り回されながら次第に葛藤から解きほぐされていきます。
ミュージカルのお約束である「登場人物が前触れなく突然歌い出す」という振る舞いを「AIがずれた行動取ってるから」で説明づけるアイディアが秀逸。しかもシオン役土屋太鳳の歌声が絶品です。そしてその「突然歌い出す」ことも物語の主舞台である実験都市というロケーションも全てちゃんとクライマックスに活きてくる作劇の妙が素晴らしい。変にハードな方向に転がり込むことなくある種の楽天的な雰囲気を持たせながらの語り口が心地よく、「何故シオンは最初からサトミを知っていたのか?」「何故唐突に歌いたがるのか?」「そして何故サトミの幸せをひたすらに希求するのか?」これらの謎が明かされる頃には観る者の心に涼やかな風が吹いているはずです。その涼風に力強さも加わって突き進む終盤と、その後にたどり着く結末の余韻も実に爽やかです。
青春映画の新たな傑作の誕生と言って良く、現時点における吉浦康裕監督のキャリア・ベストじゃないでしょうか。長く支持を集める理由も観て分かるというものです。是非多くの方にご鑑賞いただきたい逸品ですね。
ところで109シネマズ名古屋などで不定期に開催される、音響機材をシアター内に設えての特別上映、敢えてやってみて分かりましたが通常の映画鑑賞では決して良い位置とは言えない最前列中央が恐らく一番醍醐味を堪能できるポジションです。いやもう音圧が凄いのなんの。没入度が半端じゃないです。機会を捕まえたら是非トライして頂きたい。
今の仕事の不満のなかにあるのが、あまりの会議の多さ。
会議やったら仕事やってる気になっている気がして、
満足しちゃってるんじゃないかと思ったりしています。
そんな気怠い会議ですからすぐに眠くなるのですが、
仕事中寝るワケにいかず、いつも『ミンティア』持参です。
ですが多く長い会議にゴリゴリと消費されるミンティアを、
最近は箱で買っておこうかと思ったりしています。
さて、以前のブログに抜歯予定があると書きましたが、
昨日はとうとうその抜歯をしてもらいに行ってきました。
20年以上ぶりに抜歯をするので、予定が決まってから、
もうこの日が来るのが憂鬱でしかたがありませんでした。
いい大人のクセにと言われようが怖いものは怖いです。
このネット社会ですから、抜歯についてググったりして、
『痛くない』『すぐ終わる』と安心するワードの数々に、
何度も救われてきましたが、ついに当日が来ました。
そのおかげでYouTubeの私へのオススメ動画一覧は、
歯医者関連の動画で埋め尽くされる事態となりました。
ネットにプライバシーなんてものはありませんね。
そんな不安いっぱいで臨んだ抜歯だったのですが、
終わってみれば本当に痛くないし、すぐ終わりました。
骨にゴリゴリ響くのだけはいただけませんでしたが。
抜歯が終わってガーゼを噛んだまま帰宅になるのですが、
鏡を見ると噛んでいるガーゼのせいで歪んだな顔の形。
え、こんなアホ顔で街を帰るの?と思いましたが、
このコロナ禍、マスクしてるんだから関係ないですね。
コロナ禍でマスクするのも鬱陶しいと思っていましたが、
マスクのおかげで美容整形や、歯科矯正も流行ってて、
これはこれでメリットがあるんだなぁと実感しました。
で、一日明けたら、顔が腫れてるじゃありませんか。
これはこれでやっぱりマスクがないと出かけられません!
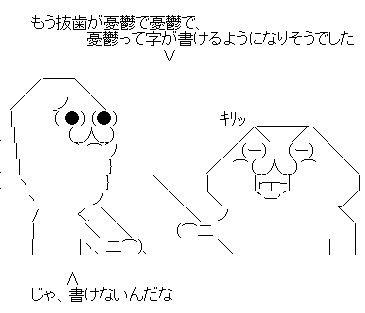
会議やったら仕事やってる気になっている気がして、
満足しちゃってるんじゃないかと思ったりしています。
そんな気怠い会議ですからすぐに眠くなるのですが、
仕事中寝るワケにいかず、いつも『ミンティア』持参です。
ですが多く長い会議にゴリゴリと消費されるミンティアを、
最近は箱で買っておこうかと思ったりしています。
さて、以前のブログに抜歯予定があると書きましたが、
昨日はとうとうその抜歯をしてもらいに行ってきました。
20年以上ぶりに抜歯をするので、予定が決まってから、
もうこの日が来るのが憂鬱でしかたがありませんでした。
いい大人のクセにと言われようが怖いものは怖いです。
このネット社会ですから、抜歯についてググったりして、
『痛くない』『すぐ終わる』と安心するワードの数々に、
何度も救われてきましたが、ついに当日が来ました。
そのおかげでYouTubeの私へのオススメ動画一覧は、
歯医者関連の動画で埋め尽くされる事態となりました。
ネットにプライバシーなんてものはありませんね。
そんな不安いっぱいで臨んだ抜歯だったのですが、
終わってみれば本当に痛くないし、すぐ終わりました。
骨にゴリゴリ響くのだけはいただけませんでしたが。
抜歯が終わってガーゼを噛んだまま帰宅になるのですが、
鏡を見ると噛んでいるガーゼのせいで歪んだな顔の形。
え、こんなアホ顔で街を帰るの?と思いましたが、
このコロナ禍、マスクしてるんだから関係ないですね。
コロナ禍でマスクするのも鬱陶しいと思っていましたが、
マスクのおかげで美容整形や、歯科矯正も流行ってて、
これはこれでメリットがあるんだなぁと実感しました。
で、一日明けたら、顔が腫れてるじゃありませんか。
これはこれでやっぱりマスクがないと出かけられません!
昔からアトピー持ちなので季節の変わり目に湿疹ができるのは良くあることだったのですが、春先に発疹ができた時には何故かいつもと違う気がしてかかりつけの皮膚科に相談したのが事の発端。
その時「これが効いたか効かなかったか次来た時に教えてください」と抗生剤を処方され、実際のところ薬は効いて発疹が治まったのでそのことを報告したら「鼻を悪くしている可能性がありますね。知り合いに腕のいい耳鼻科の先生がいます。紹介状を書きますのでそこに行ってみてください」と紹介状を渡されたので先日その耳鼻科へ行ってみたら「副鼻腔炎」と診断されました。それも昨日今日どころではなく子供の頃から数十年単位でやってるものが今また悪化してきているという可能性があるそうです。湿疹から副鼻腔炎が割り出されたのも驚きましたが、その耳鼻科で「今、鼻が詰まっているような感覚はありますか?」と聞かれたので「取り立てて不自由さは感じていませんけど」と答えたら「ろくに鼻が使えない状態に体が慣れてしまっていますね。治療が上手くいけばもっと通るようになりますよ」とサラッと言われたのが衝撃。ということはもうずっと、それこそソムリエ試験受けた時でさえ嗅覚にハンデを抱えた状態だったということか!?
こんばんは、小島@監督です。
まさか40代も半ばに差し掛かってから五感がパワーアップ(?)する可能性が出てくるとは。治療は面倒だけどちょっとワクワクして来てる自分がいます。
さて、今回の映画は「シン・ウルトラマン」です。
ある時を境に、謎の巨大不明生物「禍威獣(カイジュウ)」が頻出するようになった日本。政府は5名の専門家による特別機関・禍威獣特設対策室、通称「禍特対(カトクタイ)」を設置し、その対策に当たらせていた。
ある日、首都圏郊外にて自身を透明化できる禍威獣「ネロンガ」が出現し猛威を振るっていた。禍特対による対応が難航する中、禍特対の神永(斎藤工)は指定地域に怪獣の進路上で子供が逃げ遅れているのを確認する。子供の保護に急行する神永だったがまさにその時大気圏外から謎の光球が降着。神永は舞い上がる土砂から子供を庇うが、頭に岩石が衝突し意識を失った。その粉塵と土煙の中から銀色の巨人が姿を現し人々を驚愕させる。さらに巨人はネロンガを驚異的な強さで圧倒し、空に消えていった…
1966年に登場し、「巨大ヒーローアクション」という地平を切り拓いて以後半世紀を超えて支持を集め現在もシリーズが重ねられる「ウルトラマン」、「シン・ゴジラ」「シン・エヴァンゲリオン」を手掛けた庵野秀明が総監修・製作・脚本・編集(何ならモーションアクターも)を担い、盟友・樋口真嗣が監督を務め初代ウルトラマンへの多大なリスペクトを捧げた1本が誕生しました。
庵野秀明にしろ樋口真嗣にしろ、稀代のクリエイターであると同時に年季と気合の入ったオタクであることを存分に見せつける1本です。冒頭のタイトルの見せ方からこだわり全開。畳み掛けるような速度で世界観を紹介し、そのままネロンガとウルトラマンが次々と登場する序盤はそのスピード感も相まってまさに最初からクライマックスというノリです。CGを敢えて着ぐるみっぽく見せて昭和特撮の雰囲気を再現しつつも60年代当時の技術では為しえないショットも存分に織り込むカメラワークが堪りません。
物語が一旦落ち着く中盤にはザラブ星人や、山本耕史演じるメフィラス星人が登場し、ウルトラマンのもう一つの味わいであった日常の延長線上のSF感覚が作中に組み込まれ、当時のセンス・オブ・ワンダーを現代に復活・アップデートさせようとする試みがなされるのも興味深いところです。
「シン・ゴジラ」と同じく非常に多くの人物が出演する映画ですが、ウルトラマン=神永役斎藤工とメフィラス役山本耕史の二人の演技が取り分け絶品。どちらも姿形は人間と同じでも感覚と思考が地球人のそれとは決定的に違うという役柄を見事に演じ切っています。
一方でこの映画は欠点も多々目につきます。ウルトラマンや異星人(作中の表現では外星人)が魅力的に描かれている一方で登場人物の多くは類型的なキャラクターに終始してしまっていること、「シン・ゴジラ」ほどには強くスクラップ&ビルドしておらず、レガシーへの模倣以上にはなりえていないこと、ネタバレ無しでは具体的にどれとは言えないのですが、長澤まさみの描写に奇妙に下品なオヤジ臭さが漂うのもマイナスに作用しています。また、恐らくはアングルの面白さを優先していて撮影機材の雑多さには敢えて頓着しなかったのか、ショット単位で画面の質感に結構バラつきがあります。IMAXなどハイスペックな上映形態よりも一般のスクリーンで観た方がコレに限っては没入度は高くなるかもしれません。
作り手がオタク過ぎるということが良い方向にも悪い方向にも強固に作用したような1本。個人的にはとてもテンションがアガると同時にひどく冷静になって観てしまう二律背反じみた不思議な感覚が終始やってきました。とはいえ懐かしさと新しさが同居する、無邪気に観る分にはとても楽しいヒーローアクション映画です。ここからウルトラマンの世界に踏み込んでみたいと思う方もきっと出てくるはず。せっかくなら新鮮なうちに映画館で観てしまいましょう。多分「私の好きな言葉です」が癖になります(笑)
その時「これが効いたか効かなかったか次来た時に教えてください」と抗生剤を処方され、実際のところ薬は効いて発疹が治まったのでそのことを報告したら「鼻を悪くしている可能性がありますね。知り合いに腕のいい耳鼻科の先生がいます。紹介状を書きますのでそこに行ってみてください」と紹介状を渡されたので先日その耳鼻科へ行ってみたら「副鼻腔炎」と診断されました。それも昨日今日どころではなく子供の頃から数十年単位でやってるものが今また悪化してきているという可能性があるそうです。湿疹から副鼻腔炎が割り出されたのも驚きましたが、その耳鼻科で「今、鼻が詰まっているような感覚はありますか?」と聞かれたので「取り立てて不自由さは感じていませんけど」と答えたら「ろくに鼻が使えない状態に体が慣れてしまっていますね。治療が上手くいけばもっと通るようになりますよ」とサラッと言われたのが衝撃。ということはもうずっと、それこそソムリエ試験受けた時でさえ嗅覚にハンデを抱えた状態だったということか!?
こんばんは、小島@監督です。
まさか40代も半ばに差し掛かってから五感がパワーアップ(?)する可能性が出てくるとは。治療は面倒だけどちょっとワクワクして来てる自分がいます。
さて、今回の映画は「シン・ウルトラマン」です。
ある時を境に、謎の巨大不明生物「禍威獣(カイジュウ)」が頻出するようになった日本。政府は5名の専門家による特別機関・禍威獣特設対策室、通称「禍特対(カトクタイ)」を設置し、その対策に当たらせていた。
ある日、首都圏郊外にて自身を透明化できる禍威獣「ネロンガ」が出現し猛威を振るっていた。禍特対による対応が難航する中、禍特対の神永(斎藤工)は指定地域に怪獣の進路上で子供が逃げ遅れているのを確認する。子供の保護に急行する神永だったがまさにその時大気圏外から謎の光球が降着。神永は舞い上がる土砂から子供を庇うが、頭に岩石が衝突し意識を失った。その粉塵と土煙の中から銀色の巨人が姿を現し人々を驚愕させる。さらに巨人はネロンガを驚異的な強さで圧倒し、空に消えていった…
1966年に登場し、「巨大ヒーローアクション」という地平を切り拓いて以後半世紀を超えて支持を集め現在もシリーズが重ねられる「ウルトラマン」、「シン・ゴジラ」「シン・エヴァンゲリオン」を手掛けた庵野秀明が総監修・製作・脚本・編集(何ならモーションアクターも)を担い、盟友・樋口真嗣が監督を務め初代ウルトラマンへの多大なリスペクトを捧げた1本が誕生しました。
庵野秀明にしろ樋口真嗣にしろ、稀代のクリエイターであると同時に年季と気合の入ったオタクであることを存分に見せつける1本です。冒頭のタイトルの見せ方からこだわり全開。畳み掛けるような速度で世界観を紹介し、そのままネロンガとウルトラマンが次々と登場する序盤はそのスピード感も相まってまさに最初からクライマックスというノリです。CGを敢えて着ぐるみっぽく見せて昭和特撮の雰囲気を再現しつつも60年代当時の技術では為しえないショットも存分に織り込むカメラワークが堪りません。
物語が一旦落ち着く中盤にはザラブ星人や、山本耕史演じるメフィラス星人が登場し、ウルトラマンのもう一つの味わいであった日常の延長線上のSF感覚が作中に組み込まれ、当時のセンス・オブ・ワンダーを現代に復活・アップデートさせようとする試みがなされるのも興味深いところです。
「シン・ゴジラ」と同じく非常に多くの人物が出演する映画ですが、ウルトラマン=神永役斎藤工とメフィラス役山本耕史の二人の演技が取り分け絶品。どちらも姿形は人間と同じでも感覚と思考が地球人のそれとは決定的に違うという役柄を見事に演じ切っています。
一方でこの映画は欠点も多々目につきます。ウルトラマンや異星人(作中の表現では外星人)が魅力的に描かれている一方で登場人物の多くは類型的なキャラクターに終始してしまっていること、「シン・ゴジラ」ほどには強くスクラップ&ビルドしておらず、レガシーへの模倣以上にはなりえていないこと、ネタバレ無しでは具体的にどれとは言えないのですが、長澤まさみの描写に奇妙に下品なオヤジ臭さが漂うのもマイナスに作用しています。また、恐らくはアングルの面白さを優先していて撮影機材の雑多さには敢えて頓着しなかったのか、ショット単位で画面の質感に結構バラつきがあります。IMAXなどハイスペックな上映形態よりも一般のスクリーンで観た方がコレに限っては没入度は高くなるかもしれません。
作り手がオタク過ぎるということが良い方向にも悪い方向にも強固に作用したような1本。個人的にはとてもテンションがアガると同時にひどく冷静になって観てしまう二律背反じみた不思議な感覚が終始やってきました。とはいえ懐かしさと新しさが同居する、無邪気に観る分にはとても楽しいヒーローアクション映画です。ここからウルトラマンの世界に踏み込んでみたいと思う方もきっと出てくるはず。せっかくなら新鮮なうちに映画館で観てしまいましょう。多分「私の好きな言葉です」が癖になります(笑)

