秋のアニメの中で、全く思いがけず楽しんでしまっている作品があります。「16bitセンセーション」、弱小美少女ゲームメーカーでイラストレーターをしている女性がひょんなことから1990年代にタイムスリップし当時の美少女ソフトメーカーでバイトする、という話なのですが、アダルトゲームというアングルから90年代サブカルチャーを振り返るなどという題材のエンタメが登場するとはよもや思わず、その切り口に興味深く観ています。第3話で物語は1996年に移り、いよいよ自分が秋葉原に入り浸り始めた時期に近付いて来ていて、技術や製作環境だけでなく世情も目まぐるしく変遷して行ったあの頃をどうストーリーの中で表現してくれるのかホント楽しみ。
作中に当時発売されたタイトルが実名でパッケージデザインごと登場したり、エンドカードのイラストに当時の名作を手掛けたイラストレーターが寄稿していたりするのも良いですね。
こんばんは、小島@監督です。
まあある意味自分の黒歴史的引き出しを開けられてるようでもあるのでたまに変な汗出ますがね(笑)
さて、今回の映画は「旅するローマ教皇」です。
第266代ローマ教皇フランシスコ。史上初のラテンアメリカ、そしてイエズス会出身の教皇である。2013年に就任して以降2022年までの9年間で53カ国37回の海外訪問を行なった。学究の徒然としていた前教皇ベネディクト16世と異なる路線を打ち出し、明るく飾らない人柄で信者達に留まらない人気と支持を集め、2013年のブラジル訪問時には歓迎イベントに100万人が集まったという。その人気故に「ロックスター教皇」と呼ぶ者もいるフランシスコ。その旅先で彼はどんな表情を見せ、どんな言葉を発したのか。
ドキュメンタリーの名手ジャンフランコ・ロージ。「ローマ環状線、めぐりゆく人生たち」「海は燃えている〜イタリア最南端の小さな島〜」などで国際的評価を得た同氏が今作でその眼差しを向けるのは、第266代ローマ教皇フランシスコ。積極的に世界中を歴訪する教皇に密着し、その姿の向こうに世界のありようを浮かび上がらせようとします。
これまでのロージ監督作品と大きく違う点は、映画製作のほとんどは膨大な量のアーカイブ映像からの採録と編集に費やされ、実際に同行撮影を行なったのは2022年のカナダとマルタのみだそうです。
歴訪した先々で歓待を受け、演説を行う教皇。映画はその姿が繰り返し映し出されます。多くがアーカイブ映像で構成されたそれは、一見ただニュース映像が流れているだけのように思えますが、世俗に生きる市井の人々をこそ見つめて来たロージ監督はある意味で世界最高峰のアイドルに対し絶妙な距離感を保った映画に仕上げています。教皇としての近寄り難さと本人の人柄がなせる親しみやすさを見せつつ、重圧に沈み懊悩する一介の老人の姿を確かに捉えてみせます。映画のために撮られた映像ではないものを解体し紡ぎ直して作り上げた、という作品の性格上、この映画の肝は映像が捉えたトピックそのものよりも「編集」に見る必要があるでしょう。
興味深いのはロージ監督がそれを見出しているのは軽妙でいて熱のこもる演説の中、ではなく沈黙の中である点です。映画冒頭、最善の言葉を尽くそうとする教皇が沈思する姿を捉えます。本編中にはアルメニア人虐殺の歴史について批判した後の、トルコのエルドアン大統領との間に流れる沈黙も映し出します。政治と宗教が火花散らす瞬間はむしろ言葉の出ない時であるかのよう。
また、旅先での姿ばかりではなく移動中の映像も映画を構成する重要な要素です。機内の窓から外を覗くフランシスコ。VIP故にチャーター機には護衛の戦闘機が付くこともしばしば。パレードの際も見回せば武装した護衛兵が必ずいます。宗教的指導者として戦争を否定しながら、バチカン市国の元首でもあるが故に武力は否定できない。その矛盾。それを抱えながらもしかし困難の中にある人々に手を差し伸べる行き方をやめないフランシスコの在り方の向こうに、断絶が増していく世界の姿を映画を通して見せて行くのです。
2019年には日本へも訪れ東京ドームで大規模ミサを行ったニュースをご記憶の方もいるはず。その際には広島や長崎も歴訪しています。映画には日本訪問時の映像も使われていますが、残念ながらミサの様子は収められていません。
武力紛争への嗅覚と教皇としての使命感がそうさせるのか、フランシスコは度々緊張度の高い地域へも訪問しており、それこそイラクやイスラエルにも赴いています。苦悩し疲れ果てながらも諦めない。世界にはこういう戦いをしている人がいる。もう80代後半に差し掛かっていながらフランシスコの旅はまだ終わりません。その祈りで彼は世界に相対し続けるのです。旅路の果てで彼はどんな言葉を残すのでしょうか。
作中に当時発売されたタイトルが実名でパッケージデザインごと登場したり、エンドカードのイラストに当時の名作を手掛けたイラストレーターが寄稿していたりするのも良いですね。
こんばんは、小島@監督です。
まあある意味自分の黒歴史的引き出しを開けられてるようでもあるのでたまに変な汗出ますがね(笑)
さて、今回の映画は「旅するローマ教皇」です。
第266代ローマ教皇フランシスコ。史上初のラテンアメリカ、そしてイエズス会出身の教皇である。2013年に就任して以降2022年までの9年間で53カ国37回の海外訪問を行なった。学究の徒然としていた前教皇ベネディクト16世と異なる路線を打ち出し、明るく飾らない人柄で信者達に留まらない人気と支持を集め、2013年のブラジル訪問時には歓迎イベントに100万人が集まったという。その人気故に「ロックスター教皇」と呼ぶ者もいるフランシスコ。その旅先で彼はどんな表情を見せ、どんな言葉を発したのか。
ドキュメンタリーの名手ジャンフランコ・ロージ。「ローマ環状線、めぐりゆく人生たち」「海は燃えている〜イタリア最南端の小さな島〜」などで国際的評価を得た同氏が今作でその眼差しを向けるのは、第266代ローマ教皇フランシスコ。積極的に世界中を歴訪する教皇に密着し、その姿の向こうに世界のありようを浮かび上がらせようとします。
これまでのロージ監督作品と大きく違う点は、映画製作のほとんどは膨大な量のアーカイブ映像からの採録と編集に費やされ、実際に同行撮影を行なったのは2022年のカナダとマルタのみだそうです。
歴訪した先々で歓待を受け、演説を行う教皇。映画はその姿が繰り返し映し出されます。多くがアーカイブ映像で構成されたそれは、一見ただニュース映像が流れているだけのように思えますが、世俗に生きる市井の人々をこそ見つめて来たロージ監督はある意味で世界最高峰のアイドルに対し絶妙な距離感を保った映画に仕上げています。教皇としての近寄り難さと本人の人柄がなせる親しみやすさを見せつつ、重圧に沈み懊悩する一介の老人の姿を確かに捉えてみせます。映画のために撮られた映像ではないものを解体し紡ぎ直して作り上げた、という作品の性格上、この映画の肝は映像が捉えたトピックそのものよりも「編集」に見る必要があるでしょう。
興味深いのはロージ監督がそれを見出しているのは軽妙でいて熱のこもる演説の中、ではなく沈黙の中である点です。映画冒頭、最善の言葉を尽くそうとする教皇が沈思する姿を捉えます。本編中にはアルメニア人虐殺の歴史について批判した後の、トルコのエルドアン大統領との間に流れる沈黙も映し出します。政治と宗教が火花散らす瞬間はむしろ言葉の出ない時であるかのよう。
また、旅先での姿ばかりではなく移動中の映像も映画を構成する重要な要素です。機内の窓から外を覗くフランシスコ。VIP故にチャーター機には護衛の戦闘機が付くこともしばしば。パレードの際も見回せば武装した護衛兵が必ずいます。宗教的指導者として戦争を否定しながら、バチカン市国の元首でもあるが故に武力は否定できない。その矛盾。それを抱えながらもしかし困難の中にある人々に手を差し伸べる行き方をやめないフランシスコの在り方の向こうに、断絶が増していく世界の姿を映画を通して見せて行くのです。
2019年には日本へも訪れ東京ドームで大規模ミサを行ったニュースをご記憶の方もいるはず。その際には広島や長崎も歴訪しています。映画には日本訪問時の映像も使われていますが、残念ながらミサの様子は収められていません。
武力紛争への嗅覚と教皇としての使命感がそうさせるのか、フランシスコは度々緊張度の高い地域へも訪問しており、それこそイラクやイスラエルにも赴いています。苦悩し疲れ果てながらも諦めない。世界にはこういう戦いをしている人がいる。もう80代後半に差し掛かっていながらフランシスコの旅はまだ終わりません。その祈りで彼は世界に相対し続けるのです。旅路の果てで彼はどんな言葉を残すのでしょうか。
昨日の歌会に参加された皆さん、お疲れ様でした。
朝方は雨模様だったので厚手の格好で行ったらJOYSOUND金山に着く頃には結構暑くなっててちょっぴり服装を後悔したことと、久しぶりに名乗り出たじゃんけん大会で勝ち抜いてしまい缶チューハイとお漬物を頂いてしまったのが私の昨日のハイライト。おいおいご飯のお供にして楽しませてもらいますぞ〜。
こんばんは、小島@監督です。
カラオケの方もいろいろと歌えたので何のかのと満足でございました。
さて、今回の映画は「イコライザーTHE FINAL」です。
イタリア・シチリア。ある仕事を終えたロバート・マッコール(デンゼル・ワシントン)は、そこで図らずも瀕死の重傷を負ってしまう。マッコールの命を救ったのは医師のエンゾ(レモ・ジローネ)だった。自身の素性も聞かずに治療を施してくれたエンゾの計らいで、イタリアの小さな田舎町でのマッコールの療養生活が始まった。
一方、匿名を装ったマッコールからの通報を受け、CIAからエマ・コリンズ(ダコタ・ファニング)たちがイタリアへ派遣された。そこでエマらはテロリストへ流れていると目される薬物と資金を発見し、その大元を探るためエマは更なる捜査を開始する。
傷を癒しながらの街での生活を気に入り、そのまま静かに隠棲しようとするマッコール。しかし強硬にリゾート開発を推し進めるマフィアの手が街に迫ってきていた。
勤勉なホームセンターの職員が、実は元特殊工作員。そして最短最速で悪人を葬る暗殺者「イコライザー」、そんな男ロバート・マッコールをデンゼル・ワシントンが演じる人気シリーズの3作目が公開中です。監督はもちろんシリーズを通して手掛けてきたアントワン・フークア。デンゼル・ワシントンがアカデミー主演男優賞を獲得した「トレーニング・デイ」(2001年)からの二十年来に渡るタッグで今回も燻し銀の味わい深い作品に仕上げています。
「THE FINAL」と銘打っており、確かに完結を思わせるラストをしていますがこれはあくまで邦題で原題は単に「THE EQUALIZER 3」。「THE FINAL」という邦題が早とちりに終わらないと良いのですが。
「イコライザー」という作品、ジャンルとしてはアクションやスリラーの部類に入るのは間違い無いのですがそのボリュームはむしろかなり少ないのが大きな特色です。前半は名も無き市井の人達の生活や悩みに寄り添い助言をする心優しい男の姿を描いて行きます。気さくで人当たりも良いが強過ぎるくらいの正義感の持ち主。ウザいようなクサいようなこんなキャラクターもデンゼル・ワシントンが演じるとそこに「深み」が宿ります。その深みと、終盤悪人たちに容赦の無い鉄槌を下す姿の、オンオフの振り幅の極端な大きさがこのシリーズの醍醐味です。
同じ暗殺者を主人公にして奇しくも同時期に新作が公開されている「ジョン・ウィック」がクール&スタイリッシュなアクションとスタントのボリュームの中に作品の核と哲学を盛り込み、上映時間が長大化して行ったのと対照的に「イコライザー」ではアクションの過程の大半を省略することでロバート・マッコールの強さを表現してみせるので作を重ねる度に上映時間が短くなっているのもポイントです。主演のデンゼル・ワシントンが年齢の割に動きが機敏とは言え1作目の時点で既に59歳だったという事もあったかもしれませんが、この「省略」が作品をユニークなものにしています。
ジョン・ウィックのように多様な武器を使いこなすのではなく、ガラス瓶やコルク抜き、フォークなど身近なものを武器にして最短かつ全力で敵を抹殺するスタイルは、経過を省略し結果だけを見せるようになった作劇とシリーズで初めてR15+のレーティングとなったことが相まって「THE FINAL」のマッコールのバイオレンスは最早ホラーの領域。マフィアの視点から見たら無表情かつハイライトの無い瞳で鉛筆1本で頭をブチ抜くわマッチ棒でも折るかのように容易く腕をへし折るわするマッコールは「13日の金曜日」のジェイソンもかくやというシリアルキラーにしか見えないに違いない、というか最後の方はむしろマフィアたちに「超逃げて」と思わされてしまうこと必至。
そんなバイオレンスが映えるのも、ひとえに「名も無き普通の人たち」を描いているから。実は前2作まででマッコールは多くのものを失っています。それ故に心のどこかで安息の地を求めていたのでしょう。遠くイタリアの片田舎でささやかに生きる普通の人たちの喜びや優しさの中にそれを見出したからこそそれを踏みにじる者をマッコールは許さない。しかしその容赦の無さには哀愁も漂い復讐に安易なカタルシスを否定します。シンプルなプロットに宿る情感の複雑さとデンゼル・ワシントンの重厚な佇まいによって、この3作目にして「イコライザー」は文芸映画のような風格すら獲得しました。
現実は混沌としていて善悪の境界も曖昧。勧善懲悪はB級映画くらいのものと理解はしていてもせめてフィクションでくらいはそう言うのがあっても良いしあって欲しい。マッコールに討ち果たして欲しい「悪」はまだまだある、そう思う方も多いのでは。とは言えシリーズはこれで一区切り。ある意味で「親愛なる隣人」であるマッコールの最後の戦いとその行き着く先をどうぞ見届けてください。
朝方は雨模様だったので厚手の格好で行ったらJOYSOUND金山に着く頃には結構暑くなっててちょっぴり服装を後悔したことと、久しぶりに名乗り出たじゃんけん大会で勝ち抜いてしまい缶チューハイとお漬物を頂いてしまったのが私の昨日のハイライト。おいおいご飯のお供にして楽しませてもらいますぞ〜。
こんばんは、小島@監督です。
カラオケの方もいろいろと歌えたので何のかのと満足でございました。
さて、今回の映画は「イコライザーTHE FINAL」です。
イタリア・シチリア。ある仕事を終えたロバート・マッコール(デンゼル・ワシントン)は、そこで図らずも瀕死の重傷を負ってしまう。マッコールの命を救ったのは医師のエンゾ(レモ・ジローネ)だった。自身の素性も聞かずに治療を施してくれたエンゾの計らいで、イタリアの小さな田舎町でのマッコールの療養生活が始まった。
一方、匿名を装ったマッコールからの通報を受け、CIAからエマ・コリンズ(ダコタ・ファニング)たちがイタリアへ派遣された。そこでエマらはテロリストへ流れていると目される薬物と資金を発見し、その大元を探るためエマは更なる捜査を開始する。
傷を癒しながらの街での生活を気に入り、そのまま静かに隠棲しようとするマッコール。しかし強硬にリゾート開発を推し進めるマフィアの手が街に迫ってきていた。
勤勉なホームセンターの職員が、実は元特殊工作員。そして最短最速で悪人を葬る暗殺者「イコライザー」、そんな男ロバート・マッコールをデンゼル・ワシントンが演じる人気シリーズの3作目が公開中です。監督はもちろんシリーズを通して手掛けてきたアントワン・フークア。デンゼル・ワシントンがアカデミー主演男優賞を獲得した「トレーニング・デイ」(2001年)からの二十年来に渡るタッグで今回も燻し銀の味わい深い作品に仕上げています。
「THE FINAL」と銘打っており、確かに完結を思わせるラストをしていますがこれはあくまで邦題で原題は単に「THE EQUALIZER 3」。「THE FINAL」という邦題が早とちりに終わらないと良いのですが。
「イコライザー」という作品、ジャンルとしてはアクションやスリラーの部類に入るのは間違い無いのですがそのボリュームはむしろかなり少ないのが大きな特色です。前半は名も無き市井の人達の生活や悩みに寄り添い助言をする心優しい男の姿を描いて行きます。気さくで人当たりも良いが強過ぎるくらいの正義感の持ち主。ウザいようなクサいようなこんなキャラクターもデンゼル・ワシントンが演じるとそこに「深み」が宿ります。その深みと、終盤悪人たちに容赦の無い鉄槌を下す姿の、オンオフの振り幅の極端な大きさがこのシリーズの醍醐味です。
同じ暗殺者を主人公にして奇しくも同時期に新作が公開されている「ジョン・ウィック」がクール&スタイリッシュなアクションとスタントのボリュームの中に作品の核と哲学を盛り込み、上映時間が長大化して行ったのと対照的に「イコライザー」ではアクションの過程の大半を省略することでロバート・マッコールの強さを表現してみせるので作を重ねる度に上映時間が短くなっているのもポイントです。主演のデンゼル・ワシントンが年齢の割に動きが機敏とは言え1作目の時点で既に59歳だったという事もあったかもしれませんが、この「省略」が作品をユニークなものにしています。
ジョン・ウィックのように多様な武器を使いこなすのではなく、ガラス瓶やコルク抜き、フォークなど身近なものを武器にして最短かつ全力で敵を抹殺するスタイルは、経過を省略し結果だけを見せるようになった作劇とシリーズで初めてR15+のレーティングとなったことが相まって「THE FINAL」のマッコールのバイオレンスは最早ホラーの領域。マフィアの視点から見たら無表情かつハイライトの無い瞳で鉛筆1本で頭をブチ抜くわマッチ棒でも折るかのように容易く腕をへし折るわするマッコールは「13日の金曜日」のジェイソンもかくやというシリアルキラーにしか見えないに違いない、というか最後の方はむしろマフィアたちに「超逃げて」と思わされてしまうこと必至。
そんなバイオレンスが映えるのも、ひとえに「名も無き普通の人たち」を描いているから。実は前2作まででマッコールは多くのものを失っています。それ故に心のどこかで安息の地を求めていたのでしょう。遠くイタリアの片田舎でささやかに生きる普通の人たちの喜びや優しさの中にそれを見出したからこそそれを踏みにじる者をマッコールは許さない。しかしその容赦の無さには哀愁も漂い復讐に安易なカタルシスを否定します。シンプルなプロットに宿る情感の複雑さとデンゼル・ワシントンの重厚な佇まいによって、この3作目にして「イコライザー」は文芸映画のような風格すら獲得しました。
現実は混沌としていて善悪の境界も曖昧。勧善懲悪はB級映画くらいのものと理解はしていてもせめてフィクションでくらいはそう言うのがあっても良いしあって欲しい。マッコールに討ち果たして欲しい「悪」はまだまだある、そう思う方も多いのでは。とは言えシリーズはこれで一区切り。ある意味で「親愛なる隣人」であるマッコールの最後の戦いとその行き着く先をどうぞ見届けてください。
秋のアニメが色々とスタート。私としてはマストの「アイドルマスターミリオンライブ!」はもちろんですが、「葬送のフリーレン」「アンデッド・アンラック」あたりも好印象。あとはeスポーツをモチーフにした「僕らの雨いろプロトコル」が題材の新鮮さも相まってちょっと気になる感じでしたね。
こんばんは、小島@監督です。
たくさん観れる時間的余裕があるわけではないから初回だけチェックして、とか思っていたのに意外と面白いのが多いのが困りもの。
さて、今回の映画は「ジョン・ウィック:コンセクエンス」です。
ニューヨーク地下組織の王バワリー・キング(ローレンス・フィッシュバーン)のもとで傷を癒し、準備を整えたジョン・ウィック(キアヌ・リーブス)は主席連合との戦いへ向け行動を開始する。
一方、ニューヨーク・コンチネンタルホテルには主席連合から全権を委ねられた侯爵(ビル・スカルスガルド)により告知人(クランシー・ブラウン)が派遣された。ジョン・ウィックが主席連合へ叛旗を翻したことの責任を取らされホテルは廃棄、支配人ウィンストン(イアン・マクシェーン)は追放処分となる。
侯爵はジョン・ウィックへの刺客として白羽の矢を立てたのは、ジョンの旧友である盲目の男ケイン(ドニー・イェン)であった。
ユニークな世界観と殺意むき出しのアクション「ガン・フー」で唯一無二の存在感を放ち、「マトリックス」に匹敵するキアヌ・リーブスの代表作となった「ジョン・ウィック」シリーズ。その4作目にして完結編となる作品が公開されました。全作を通じて監督を手掛けたチャド・スタエルスキが今作でもキアヌ・リーブスとタッグを組み、シリーズを締めくくります。3作目「ジョン・ウィック:パラベラム」までで徹底的に追い詰められたジョンは今作で遂に反撃に転じ、その長い戦いの旅路に遂に終止符を打つことになります。
副題の「コンセクエンス」は「報い」という意味を持ちますが、実はこれ原題には無く邦題のみのもの。原題は単に「John Wick:Chapter4」。観ると分かるのですが、ストーリーでも重要な意味を持つ単語を持って来ていてかなり技ありのタイトルです。
凝りに凝った世界観は今作も健在。フランスのルーブル美術館やドイツのボーデ美術館をロケ地に使った映像は、詳細を語らずとも殺し屋たちの世界に横たわる重厚な歴史を感じさせることに一役買っています。また、殺し屋とその関係者しかフォーカスしないので一般人は登場しても無関係というのも相変わらずで、今作では特にドイツのクラブでのファイトやパリの凱旋門周辺でのアクションシークエンスに特に顕著に表れています。この、現実と地続きにしないスタイルが凄惨な復讐の連鎖に他には無い奇妙な清廉さをもたらし、作品世界のユニークさを獲得しました。
シリーズ最長の169分の大半はアクションに注ぎ込まれ、比喩ではなく満腹感を覚えるほどの尋常じゃないボリュームと驚異のバリエーションで展開されるそれは最早アートの領域です。アクションが物語を牽引する、同種の傾向を持つ作品としてはトム・クルーズ主演の「ミッション・インポッシブル/デッド・レコニングpart1」が挙げられますが、物語の着地点が定まっているというところに大きな違いがあると言えるでしょう。もう一つ違いがあるとすれば「ジョン・ウィック」の方には「殺意」をより強く感じられる、と言うところでしょうか。共演者にドニー・イェン、真田広之を迎えた今作では両者への多大なリスペクトと共に香港のカンフー、日本の殺陣を基調としたアクションも存分に盛り込まれ、映画を更に華やかにしています。
圧倒的な熱量をもって大団円へ向け爆走する、比類なき一本。これぞ圧巻。ジョン・ウィックの旅路の果てをどうぞ見届けてください。
なお、エンドクレジット後にエピローグがあります。場内が明るくなるまでお席をお立ちになりませんよう。
こんばんは、小島@監督です。
たくさん観れる時間的余裕があるわけではないから初回だけチェックして、とか思っていたのに意外と面白いのが多いのが困りもの。
さて、今回の映画は「ジョン・ウィック:コンセクエンス」です。
ニューヨーク地下組織の王バワリー・キング(ローレンス・フィッシュバーン)のもとで傷を癒し、準備を整えたジョン・ウィック(キアヌ・リーブス)は主席連合との戦いへ向け行動を開始する。
一方、ニューヨーク・コンチネンタルホテルには主席連合から全権を委ねられた侯爵(ビル・スカルスガルド)により告知人(クランシー・ブラウン)が派遣された。ジョン・ウィックが主席連合へ叛旗を翻したことの責任を取らされホテルは廃棄、支配人ウィンストン(イアン・マクシェーン)は追放処分となる。
侯爵はジョン・ウィックへの刺客として白羽の矢を立てたのは、ジョンの旧友である盲目の男ケイン(ドニー・イェン)であった。
ユニークな世界観と殺意むき出しのアクション「ガン・フー」で唯一無二の存在感を放ち、「マトリックス」に匹敵するキアヌ・リーブスの代表作となった「ジョン・ウィック」シリーズ。その4作目にして完結編となる作品が公開されました。全作を通じて監督を手掛けたチャド・スタエルスキが今作でもキアヌ・リーブスとタッグを組み、シリーズを締めくくります。3作目「ジョン・ウィック:パラベラム」までで徹底的に追い詰められたジョンは今作で遂に反撃に転じ、その長い戦いの旅路に遂に終止符を打つことになります。
副題の「コンセクエンス」は「報い」という意味を持ちますが、実はこれ原題には無く邦題のみのもの。原題は単に「John Wick:Chapter4」。観ると分かるのですが、ストーリーでも重要な意味を持つ単語を持って来ていてかなり技ありのタイトルです。
凝りに凝った世界観は今作も健在。フランスのルーブル美術館やドイツのボーデ美術館をロケ地に使った映像は、詳細を語らずとも殺し屋たちの世界に横たわる重厚な歴史を感じさせることに一役買っています。また、殺し屋とその関係者しかフォーカスしないので一般人は登場しても無関係というのも相変わらずで、今作では特にドイツのクラブでのファイトやパリの凱旋門周辺でのアクションシークエンスに特に顕著に表れています。この、現実と地続きにしないスタイルが凄惨な復讐の連鎖に他には無い奇妙な清廉さをもたらし、作品世界のユニークさを獲得しました。
シリーズ最長の169分の大半はアクションに注ぎ込まれ、比喩ではなく満腹感を覚えるほどの尋常じゃないボリュームと驚異のバリエーションで展開されるそれは最早アートの領域です。アクションが物語を牽引する、同種の傾向を持つ作品としてはトム・クルーズ主演の「ミッション・インポッシブル/デッド・レコニングpart1」が挙げられますが、物語の着地点が定まっているというところに大きな違いがあると言えるでしょう。もう一つ違いがあるとすれば「ジョン・ウィック」の方には「殺意」をより強く感じられる、と言うところでしょうか。共演者にドニー・イェン、真田広之を迎えた今作では両者への多大なリスペクトと共に香港のカンフー、日本の殺陣を基調としたアクションも存分に盛り込まれ、映画を更に華やかにしています。
圧倒的な熱量をもって大団円へ向け爆走する、比類なき一本。これぞ圧巻。ジョン・ウィックの旅路の果てをどうぞ見届けてください。
なお、エンドクレジット後にエピローグがあります。場内が明るくなるまでお席をお立ちになりませんよう。
私のいくつかの趣味の1つにプラモデルがあるのですが、
会社の一部の人にその私の趣味を知っている人がいます。
先日、その趣味を知る人にプラモの製作を依頼されました。
依頼は『ガンダムW』に登場する『ガンダムデスサイズ』。
なんとなく断りにくくて、製作を受けたのですのですが、
ガンダムWを観ていないのでデスサイズに思い入れが無く、
作っていても、なんか楽しんで作れないんですよね。
なので、今からガンダムWを観てやろうかと思ったのですが、
どうやら私の見られる動画サイトでは観られないようです。
というワケで、特に思い入れもなく製作進行中です。
さて、私は『頭文字D』という作品がアニメ・漫画の中で、
悩むことなく余裕でトップ3に入るほど好きだったりします。
よく私は好きな作品を聞かれると『STEINS;GATE』と答えて、
これの記憶を無くして、もう一回見たいなんていいますが、
頭文字Dは車好きでないと話が盛り上がらない気がして、
こうやって聞かれても頭文字Dって答えないんですよね。
それこそ頭文字Dが好きで、聖地巡礼に作品の舞台となる、
群馬のいくつか峠に行ったりなんかもしているくらいです。
そんな頭文字D好きの私ですが、その続編となる作品で、
『MFゴースト』という漫画が結構長い間連載されていますが、
実はこの漫画を一切読んだことがありませんでした。
友人にも「イニDが好きなのに読んでないの?」と言われても、
なんかそれでも読もうという重い腰があがりませんでした。
しかしながらMFゴーストがアニメ化されるとのことで、
いよいよそこまでなら読んでもいいかなと思い始めて、
この週末に単行本の何冊かをドカッと買ってまいりました。
「さあ、どんなもんか」とちょっと上から目線で読み始めると、
予想を裏切って思いのほか面白いじゃありませんか。
そんなアニメも、頭文字Dから登場するキャラについては、
テレビアニメ当時の声優陣がそのまま続投するようだし、
バトルシーンはSUPER EUROBEATだしで、期待ですね。
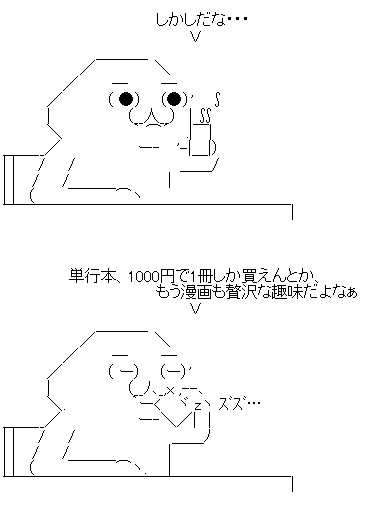
会社の一部の人にその私の趣味を知っている人がいます。
先日、その趣味を知る人にプラモの製作を依頼されました。
依頼は『ガンダムW』に登場する『ガンダムデスサイズ』。
なんとなく断りにくくて、製作を受けたのですのですが、
ガンダムWを観ていないのでデスサイズに思い入れが無く、
作っていても、なんか楽しんで作れないんですよね。
なので、今からガンダムWを観てやろうかと思ったのですが、
どうやら私の見られる動画サイトでは観られないようです。
というワケで、特に思い入れもなく製作進行中です。
さて、私は『頭文字D』という作品がアニメ・漫画の中で、
悩むことなく余裕でトップ3に入るほど好きだったりします。
よく私は好きな作品を聞かれると『STEINS;GATE』と答えて、
これの記憶を無くして、もう一回見たいなんていいますが、
頭文字Dは車好きでないと話が盛り上がらない気がして、
こうやって聞かれても頭文字Dって答えないんですよね。
それこそ頭文字Dが好きで、聖地巡礼に作品の舞台となる、
群馬のいくつか峠に行ったりなんかもしているくらいです。
そんな頭文字D好きの私ですが、その続編となる作品で、
『MFゴースト』という漫画が結構長い間連載されていますが、
実はこの漫画を一切読んだことがありませんでした。
友人にも「イニDが好きなのに読んでないの?」と言われても、
なんかそれでも読もうという重い腰があがりませんでした。
しかしながらMFゴーストがアニメ化されるとのことで、
いよいよそこまでなら読んでもいいかなと思い始めて、
この週末に単行本の何冊かをドカッと買ってまいりました。
「さあ、どんなもんか」とちょっと上から目線で読み始めると、
予想を裏切って思いのほか面白いじゃありませんか。
そんなアニメも、頭文字Dから登場するキャラについては、
テレビアニメ当時の声優陣がそのまま続投するようだし、
バトルシーンはSUPER EUROBEATだしで、期待ですね。
「アイドルマスターミリオンライブ!」先行上映の第3幕を観てきました。それもついさっき。
まだちょっと余韻でふわふわしています。基本がTVフォーマットで作られているものを敢えてスクリーンで観せる、それを観ることの意義を雄弁に語りかける映像と音響の迫力に酔いしれました。難産の末のアニメ化となったタイトルですが、10周年というメモリアルイヤーに相応しい作品になったと断言して良いでしょう。
こんばんは、小島@監督です。
もちろん本放送開始の暁には普通に自宅でも観ますがね!
さて先日、名古屋能楽堂まで「能狂言鬼滅の刃」を観てきました。人生で初めての能楽鑑賞です。
能楽師観世流シテ方で人間国宝の大槻文蔵、和泉流狂言方の野村萬斎、囃子方葛野流亀井広忠という第一人者たちがチームを組み、今や説明の必要も無くなった吾峠呼世晴の傑作「鬼滅の刃」を新作能として仕立てました。昨年東京と京都で初演され大反響を呼んだ舞台が今回名古屋初上演です。漫画を原作とした能楽の演目は極めて異例で、美内すずえ原作「ガラスの仮面」の劇中劇「紅天女」以来だとか。
物語は原作1巻の狭霧山のエピソードと5巻の那田蜘蛛山編を中心とした二幕構成。能楽でいう「五番立」に沿った形で進行していきます。
五番立とは即ち、
・翁(おきな。五番立は必ず「翁」「千歳」「三番艘」という祝祭儀礼から始まる。「鬼滅の刃」ではこれに代わり竈門炭治郎の父・炭十郎が炭治郎へヒノカミ神楽を相伝する姿が描かれる。)
・脇能(わきのう。神々や精霊が登場し世の安寧を祈り社寺の縁起を語る。「高砂」「養老」「竹生島」など。ここでは炭治郎は錆兎と真菰との特訓を経て鬼狩りの力を得るまでが描かれる。)
・修羅能(しゅらのう。主に「平家物語」の登場人物が現れ、自身の最期や死後の苦しみを語る。「敦盛」「清経」「八島」など。ここでは藤襲山で炭治郎が鬼殺隊の最終選別に挑む。)
・鬘能(かづらのう。「源氏物語」の登場人物など女性が主役となり恋の物語とその苦悩が優雅な舞と謡の中で展開する。「松風」「羽衣」「西行桜」など。ここでは眠り続ける竈門禰豆子が夢の中で遠き日を追想する。ここまでが前場。)
・雑能(ざつのう。他に分類しにくい演目は皆ここに振り分けられる。「隅田川」「道成寺」「安宅」など。休憩を挟みここから後場。任務中の負傷で療養していた炭治郎、我妻善逸、嘴平伊之助が復帰して那田蜘蛛山へ向かうまでが前段の狂言から地続きで語られる。)
・切能(きりのう。鬼や天狗などの異能が登場する。「鵺」「土蜘蛛」「殺生石」など。那田蜘蛛山で炭治郎達は下弦の伍・累との戦いに挑む。)
という流れで展開し、各番の合間にコメディ色の強い狂言が入るほか、前場と後場の合間には「アイ(間)狂言」が入ります。アイ狂言では時を平安時代に遡り不老不死の身体を得るも陽光の下に出られなくなった鬼舞辻無惨が生への渇望と死への恐怖に押されながら千年の彷徨に出る様が語られます。
シテ方の大槻文蔵氏は下弦の伍・累を、狂言方の野村萬斎氏は鬼舞辻無惨のほか炭治郎の父・竈門炭十郎、鱗滝左近次、更に鎹烏まで4役を演じています。
鑑賞して思うのはこちらの想像を遥かに超える原作と能楽との相性の良さ。
蜘蛛の力を持つ累には「土蜘蛛」が、水の呼吸の表現には「船弁慶」からの引用が見受けられるだけでなく、炭治郎を始めとして主要人物の多くは顔つきよりも着物の柄でキャラクターを印象付けていることも客席からの視認性の高さに直結していますし、鱗滝だったり鋼鐡塚だったり能面を付けたキャラクターが多数登場することや、ヒノカミ神楽という神楽舞が物語の重要なピースだったりする、そういう様々な要素ももちろんですがそれ以上に根幹のところで強烈な親和性を見せます。能舞台で「橋がかり」と呼ばれる長い通路は、ただの通路ではなく常世と現世を結ぶ道でもあります。その道を通り本舞台に現れる鬼達は炭治郎達に討たれ、その道を戻ることで黄泉の国へと還っていきます。常世へ帰る鬼の魂、それに思いを馳せられる炭治郎の舞と謡が鎮めるのです。
恐らく古典と比べたら演出も現代的であり盛っている方だとは思いますが、それでもアニメや2.5次元とは根本が違う抽象画や水墨画のような引き算の美が観る者のイマジネーションに作用して力強い印象を刻みつけてくれます。何より能舞台で舞われるヒノカミ神楽の姿はそれだけで強烈な説得力。なるほど鬼も調伏できようやという神気のようなものすら感じ入る程でした。
現代の漫画をベースにしながら既に古典のような風格を持ち合わせていて、再演を重ねて遥か先の未来で古典として息づいていてほしいとふと思っていました。伝統芸能への入り口としてこれほどのものもなかなか無いでしょう。良い経験ができました。これから古典能もいろいろ観てみたいなぁ。
なお、今回の文章を書くにあたり、「能狂言鬼滅の刃」パンフレット、「日本芸術文化振興会」ホームページなどを参考に致しました。
まだちょっと余韻でふわふわしています。基本がTVフォーマットで作られているものを敢えてスクリーンで観せる、それを観ることの意義を雄弁に語りかける映像と音響の迫力に酔いしれました。難産の末のアニメ化となったタイトルですが、10周年というメモリアルイヤーに相応しい作品になったと断言して良いでしょう。
こんばんは、小島@監督です。
もちろん本放送開始の暁には普通に自宅でも観ますがね!
さて先日、名古屋能楽堂まで「能狂言鬼滅の刃」を観てきました。人生で初めての能楽鑑賞です。
能楽師観世流シテ方で人間国宝の大槻文蔵、和泉流狂言方の野村萬斎、囃子方葛野流亀井広忠という第一人者たちがチームを組み、今や説明の必要も無くなった吾峠呼世晴の傑作「鬼滅の刃」を新作能として仕立てました。昨年東京と京都で初演され大反響を呼んだ舞台が今回名古屋初上演です。漫画を原作とした能楽の演目は極めて異例で、美内すずえ原作「ガラスの仮面」の劇中劇「紅天女」以来だとか。
物語は原作1巻の狭霧山のエピソードと5巻の那田蜘蛛山編を中心とした二幕構成。能楽でいう「五番立」に沿った形で進行していきます。
五番立とは即ち、
・翁(おきな。五番立は必ず「翁」「千歳」「三番艘」という祝祭儀礼から始まる。「鬼滅の刃」ではこれに代わり竈門炭治郎の父・炭十郎が炭治郎へヒノカミ神楽を相伝する姿が描かれる。)
・脇能(わきのう。神々や精霊が登場し世の安寧を祈り社寺の縁起を語る。「高砂」「養老」「竹生島」など。ここでは炭治郎は錆兎と真菰との特訓を経て鬼狩りの力を得るまでが描かれる。)
・修羅能(しゅらのう。主に「平家物語」の登場人物が現れ、自身の最期や死後の苦しみを語る。「敦盛」「清経」「八島」など。ここでは藤襲山で炭治郎が鬼殺隊の最終選別に挑む。)
・鬘能(かづらのう。「源氏物語」の登場人物など女性が主役となり恋の物語とその苦悩が優雅な舞と謡の中で展開する。「松風」「羽衣」「西行桜」など。ここでは眠り続ける竈門禰豆子が夢の中で遠き日を追想する。ここまでが前場。)
・雑能(ざつのう。他に分類しにくい演目は皆ここに振り分けられる。「隅田川」「道成寺」「安宅」など。休憩を挟みここから後場。任務中の負傷で療養していた炭治郎、我妻善逸、嘴平伊之助が復帰して那田蜘蛛山へ向かうまでが前段の狂言から地続きで語られる。)
・切能(きりのう。鬼や天狗などの異能が登場する。「鵺」「土蜘蛛」「殺生石」など。那田蜘蛛山で炭治郎達は下弦の伍・累との戦いに挑む。)
という流れで展開し、各番の合間にコメディ色の強い狂言が入るほか、前場と後場の合間には「アイ(間)狂言」が入ります。アイ狂言では時を平安時代に遡り不老不死の身体を得るも陽光の下に出られなくなった鬼舞辻無惨が生への渇望と死への恐怖に押されながら千年の彷徨に出る様が語られます。
シテ方の大槻文蔵氏は下弦の伍・累を、狂言方の野村萬斎氏は鬼舞辻無惨のほか炭治郎の父・竈門炭十郎、鱗滝左近次、更に鎹烏まで4役を演じています。
鑑賞して思うのはこちらの想像を遥かに超える原作と能楽との相性の良さ。
蜘蛛の力を持つ累には「土蜘蛛」が、水の呼吸の表現には「船弁慶」からの引用が見受けられるだけでなく、炭治郎を始めとして主要人物の多くは顔つきよりも着物の柄でキャラクターを印象付けていることも客席からの視認性の高さに直結していますし、鱗滝だったり鋼鐡塚だったり能面を付けたキャラクターが多数登場することや、ヒノカミ神楽という神楽舞が物語の重要なピースだったりする、そういう様々な要素ももちろんですがそれ以上に根幹のところで強烈な親和性を見せます。能舞台で「橋がかり」と呼ばれる長い通路は、ただの通路ではなく常世と現世を結ぶ道でもあります。その道を通り本舞台に現れる鬼達は炭治郎達に討たれ、その道を戻ることで黄泉の国へと還っていきます。常世へ帰る鬼の魂、それに思いを馳せられる炭治郎の舞と謡が鎮めるのです。
恐らく古典と比べたら演出も現代的であり盛っている方だとは思いますが、それでもアニメや2.5次元とは根本が違う抽象画や水墨画のような引き算の美が観る者のイマジネーションに作用して力強い印象を刻みつけてくれます。何より能舞台で舞われるヒノカミ神楽の姿はそれだけで強烈な説得力。なるほど鬼も調伏できようやという神気のようなものすら感じ入る程でした。
現代の漫画をベースにしながら既に古典のような風格を持ち合わせていて、再演を重ねて遥か先の未来で古典として息づいていてほしいとふと思っていました。伝統芸能への入り口としてこれほどのものもなかなか無いでしょう。良い経験ができました。これから古典能もいろいろ観てみたいなぁ。
なお、今回の文章を書くにあたり、「能狂言鬼滅の刃」パンフレット、「日本芸術文化振興会」ホームページなどを参考に致しました。
よく、YouTubeで昔のゲームミュージックを聞いています。
老害と思われて結構、やっぱり昔のゲームミュージックは、
当時の思い出補正もあって、心に染みるものがあります。
でも思い出補正と言うだけあって、そのゲームだけでなく、
その頃の思い出も同時に脳裏によぎったりしてしまうので、
実は、ちょっとセンチな気分にもなったりするのですよね。
当時に一緒にゲームしていた友達や、通ったゲーセン、
もうその時の体験はできないかと思うと、ちょっと寂しいです。
でもそれも含めて、ゲームミュージックを楽しむのですよね。
『DanceDanceRevolution Classic Mini』、ちょっと欲しいな。
さて、会社での休憩時間に、おやつを食べている時、
「『虎屋』の羊羹(ようかん)は美味しいのか」との話題に。
虎屋というのは羊羹が有名なメーカーらしいのですが、
その値段が結構強気なので、余程の自身がありそうです。
今時は、もらい物でも羊羹を見ないし食べないので、
ここまで強気の値段設定をすることができるくらいなら、
さぞかし美味しいのでは、とみんなで話あったのです。
とはいっても、作っている人には申し訳ないのですが、
どんな食べ物にも美味しさに限界はあると思っています。
例えばゆで卵をどんなに美味しい卵で良い調理をしても、
結局、ゆで卵の美味しさの限界って見えませんか?
なので、たとえ美味しくても、羊羹で感動までしないし、
言ってみれば、「羊羹としては美味しいかな」くらいの予想。
そんな虎屋の羊羹の話題が割と連日にあがったので、
そろそろここで答え合わせをしてみたくなってきました。
強くの値段設定が正しいのかどうかを見極めるべく、
とうとうやってまいりました、名古屋駅高島屋のデパ地下。
基本はノーマルな羊羹を選ぶべきだとは思いますが、
店員さんに一応、今のオススメを聞くとこれだというのが、
やはり季節柄なのか『栗蒸し羊羹』を強く推してきます。
そしてせっかくだから、『栗蒸し羊羹』を購入することにし、
翌日会社でとうとう実食するタイミングが訪れました。
みんなで「美味しいといっても所詮は羊羹だしな」と言いつつ、
切り分けた栗蒸し羊羹を、順番に頬張り始めます。
いくら『所詮は羊羹』と言えども、お金を出したのは私。
美味しくないと納得いかないなぁ、と思ったのも束の間、
「これ、美味しくね?」とみんなが連呼するではないですか。
私もすぐに食べ始めましたが、これが本当に美味しい。
私が想像していた羊羹のレベルを簡単に超えてきました。
羊羹によくある甘過ぎることなく食べ易くも、味はしっかり。
値段が高いので、ちょっと買っていこうとはならないですが、
これはリピートしてもいいかもしれないという美味しさでした。
とりあえず試してみるのも大事かもしれない出来事でした。
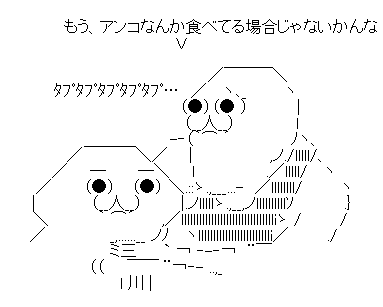
老害と思われて結構、やっぱり昔のゲームミュージックは、
当時の思い出補正もあって、心に染みるものがあります。
でも思い出補正と言うだけあって、そのゲームだけでなく、
その頃の思い出も同時に脳裏によぎったりしてしまうので、
実は、ちょっとセンチな気分にもなったりするのですよね。
当時に一緒にゲームしていた友達や、通ったゲーセン、
もうその時の体験はできないかと思うと、ちょっと寂しいです。
でもそれも含めて、ゲームミュージックを楽しむのですよね。
『DanceDanceRevolution Classic Mini』、ちょっと欲しいな。
さて、会社での休憩時間に、おやつを食べている時、
「『虎屋』の羊羹(ようかん)は美味しいのか」との話題に。
虎屋というのは羊羹が有名なメーカーらしいのですが、
その値段が結構強気なので、余程の自身がありそうです。
今時は、もらい物でも羊羹を見ないし食べないので、
ここまで強気の値段設定をすることができるくらいなら、
さぞかし美味しいのでは、とみんなで話あったのです。
とはいっても、作っている人には申し訳ないのですが、
どんな食べ物にも美味しさに限界はあると思っています。
例えばゆで卵をどんなに美味しい卵で良い調理をしても、
結局、ゆで卵の美味しさの限界って見えませんか?
なので、たとえ美味しくても、羊羹で感動までしないし、
言ってみれば、「羊羹としては美味しいかな」くらいの予想。
そんな虎屋の羊羹の話題が割と連日にあがったので、
そろそろここで答え合わせをしてみたくなってきました。
強くの値段設定が正しいのかどうかを見極めるべく、
とうとうやってまいりました、名古屋駅高島屋のデパ地下。
基本はノーマルな羊羹を選ぶべきだとは思いますが、
店員さんに一応、今のオススメを聞くとこれだというのが、
やはり季節柄なのか『栗蒸し羊羹』を強く推してきます。
そしてせっかくだから、『栗蒸し羊羹』を購入することにし、
翌日会社でとうとう実食するタイミングが訪れました。
みんなで「美味しいといっても所詮は羊羹だしな」と言いつつ、
切り分けた栗蒸し羊羹を、順番に頬張り始めます。
いくら『所詮は羊羹』と言えども、お金を出したのは私。
美味しくないと納得いかないなぁ、と思ったのも束の間、
「これ、美味しくね?」とみんなが連呼するではないですか。
私もすぐに食べ始めましたが、これが本当に美味しい。
私が想像していた羊羹のレベルを簡単に超えてきました。
羊羹によくある甘過ぎることなく食べ易くも、味はしっかり。
値段が高いので、ちょっと買っていこうとはならないですが、
これはリピートしてもいいかもしれないという美味しさでした。
とりあえず試してみるのも大事かもしれない出来事でした。
先日、お誘いを受け珍しく歌会以外でもカラオケを楽しんできました。今回は「90年代以前の曲」縛り、出来ればアニソンも少なめで、というレギュレーション。いや〜久しく使ってない錆び付いた鍵付きの引き出しを開けるような感じで楽しかったすね(笑)!
昭和歌謡もたまに聞いてみると結構カッコいいのもあったりして、何かの時のために覚えておいても良いかと思うものもあったり。
こんばんは、小島@監督です。
たまにはこういうのも楽しい。また何かの折にやれたら良いなぁ。
さて、今回の映画は「パーフェクトブルー」です。
アイドルグループ「CHAM」に所属していた霧越未麻(声・岩男潤子)は、あるミニライブを最後にグループを脱退し女優への転身を図った。しかし本人の思いとは裏腹にヌードグラビアやレイプシーンもあるドラマの撮影などアイドル時代には考えられなかったような仕事が続いた。アイドルの頃からのファンは未麻の現状を嘆くものの、未麻の仕事は次第に軌道に乗っていく。獲得した人気と裏腹に心をすり減らす未麻はやがてアイドル時代の自分の幻影まで見るようになる。そんな折、未麻の仕事の関係者が惨殺される事件が相次いで発生した。果たしてそれは自分自身が起こした事なのか?虚構と現実の境界が曖昧になる中で未麻は更に追い詰められていく。
2010年に46歳の若さで病没した夭折のアニメーション作家・今敏。一線で活躍したのは15年程度、寡作ゆえに手掛けた作品数も少ないながら日本のアニメ史、映像史に残した足跡は極めて大きい人物です。その今敏の初監督作品が1997年に製作されたこの「パーフェクトブルー」(なお劇場公開は翌1998年)です。先頃公開25周年を記念して4Kリマスター版が製作され、只今限定公開中です。当初1週間限定と告知されていましたが、平日でも満席になるなど人気の根強さを伺わせて、公開館では軒並み上映期間が1週間延長される事になりました。客層がてっきり自分と同世代かそれ以上の方達ばかりだろうと思っていたのですが、見渡すと結構若い方もいるのに驚き。どういう経緯でこの作品を知り得たのか、興味が湧きますね。
今敏が生涯にわたりモチーフにし続けた「虚構と現実の混淆」という命題は、この初監督作品で既に主題とされています。未麻は自身の意に沿わぬ仕事をこなし続けるうちに精神がすり減り現実との境が曖昧になっていきます。アイドル時代の幻影を見るようになると同時に出演しているドラマの内容も現実と酷似していき、今展開しているのは現実か劇中劇のシーンなのかが混然としていき観客を幻惑します。
写実的なビジュアルをしていますが、だからと言って実写でこれをやったら絶対にチープになってしまうであろうアニメならではの映像表現がふんだんに盛り込まれているところにこの作品の凄みがあります。しかもかなり入り組んだ構図をしていながら上映時間は81分。この余剰の少なさが高いテンションと集中力を最後まで保ちつつ物語を展開するのに成功しています。
全くの余談ですが、内容はともかく作中登場するツールはさすがに今見ると古く懐かしいものになっています。特に未麻が使うネットのブラウザが「Netscape Navigator」だったのは当時を知る者としてはちょっと胸が熱くなりましたね(笑)。1990年代も最早レトロの域に入りつつあることを思えば若い方にはかなり新鮮に映る箇所かもしれません。
今でこそ珍しくなくなりましたが1997年当時、こういうサイコホラーはアニメではほぼ前例が無く、この作品がジャンルを切り拓いたと言っても過言ではないでしょう。
「考察系」と呼ばれるドラマや映画も相次いで製作されている近年を思えばその先駆者とも言える「パーフェクトブルー」は今こそ再発見の好機。早すぎた天才の傑作をどうぞご堪能あれ。
昭和歌謡もたまに聞いてみると結構カッコいいのもあったりして、何かの時のために覚えておいても良いかと思うものもあったり。
こんばんは、小島@監督です。
たまにはこういうのも楽しい。また何かの折にやれたら良いなぁ。
さて、今回の映画は「パーフェクトブルー」です。
アイドルグループ「CHAM」に所属していた霧越未麻(声・岩男潤子)は、あるミニライブを最後にグループを脱退し女優への転身を図った。しかし本人の思いとは裏腹にヌードグラビアやレイプシーンもあるドラマの撮影などアイドル時代には考えられなかったような仕事が続いた。アイドルの頃からのファンは未麻の現状を嘆くものの、未麻の仕事は次第に軌道に乗っていく。獲得した人気と裏腹に心をすり減らす未麻はやがてアイドル時代の自分の幻影まで見るようになる。そんな折、未麻の仕事の関係者が惨殺される事件が相次いで発生した。果たしてそれは自分自身が起こした事なのか?虚構と現実の境界が曖昧になる中で未麻は更に追い詰められていく。
2010年に46歳の若さで病没した夭折のアニメーション作家・今敏。一線で活躍したのは15年程度、寡作ゆえに手掛けた作品数も少ないながら日本のアニメ史、映像史に残した足跡は極めて大きい人物です。その今敏の初監督作品が1997年に製作されたこの「パーフェクトブルー」(なお劇場公開は翌1998年)です。先頃公開25周年を記念して4Kリマスター版が製作され、只今限定公開中です。当初1週間限定と告知されていましたが、平日でも満席になるなど人気の根強さを伺わせて、公開館では軒並み上映期間が1週間延長される事になりました。客層がてっきり自分と同世代かそれ以上の方達ばかりだろうと思っていたのですが、見渡すと結構若い方もいるのに驚き。どういう経緯でこの作品を知り得たのか、興味が湧きますね。
今敏が生涯にわたりモチーフにし続けた「虚構と現実の混淆」という命題は、この初監督作品で既に主題とされています。未麻は自身の意に沿わぬ仕事をこなし続けるうちに精神がすり減り現実との境が曖昧になっていきます。アイドル時代の幻影を見るようになると同時に出演しているドラマの内容も現実と酷似していき、今展開しているのは現実か劇中劇のシーンなのかが混然としていき観客を幻惑します。
写実的なビジュアルをしていますが、だからと言って実写でこれをやったら絶対にチープになってしまうであろうアニメならではの映像表現がふんだんに盛り込まれているところにこの作品の凄みがあります。しかもかなり入り組んだ構図をしていながら上映時間は81分。この余剰の少なさが高いテンションと集中力を最後まで保ちつつ物語を展開するのに成功しています。
全くの余談ですが、内容はともかく作中登場するツールはさすがに今見ると古く懐かしいものになっています。特に未麻が使うネットのブラウザが「Netscape Navigator」だったのは当時を知る者としてはちょっと胸が熱くなりましたね(笑)。1990年代も最早レトロの域に入りつつあることを思えば若い方にはかなり新鮮に映る箇所かもしれません。
今でこそ珍しくなくなりましたが1997年当時、こういうサイコホラーはアニメではほぼ前例が無く、この作品がジャンルを切り拓いたと言っても過言ではないでしょう。
「考察系」と呼ばれるドラマや映画も相次いで製作されている近年を思えばその先駆者とも言える「パーフェクトブルー」は今こそ再発見の好機。早すぎた天才の傑作をどうぞご堪能あれ。

