1日乗車券を片手に地下鉄を乗り回し謎解きを街歩きを楽しむ、「地下迷宮に眠る謎2023」友人と連れ立って挑戦して来ました。街の観光とのタイアップなので難易度はそんなに高くないだろうと思っていたら甘かった(苦笑)。昼過ぎから始めたのですが、日没までに解き切れず最後の部分は解散後に自宅に持ち帰って解く始末。割とガチめのヤツなのでこれからトライする方はだんだん日も短くなりますし午前中から始めることをお薦めします。それと結構歩くので歩きやすい履き物で。あと、途中で一つでもピースを失くすと詰むので都度都度ご確認をお忘れなく。
こんばんは、小島@監督です。
とは言え久しぶりの謎解きゲームは楽しかった。次は屋内でやれるヤツにしたいかな(笑)
さて、今回の映画は「ちびねこトムの大冒険 地球を救え!なかまたち」です。
夏休み最初の日、トム(声・藤田淑子)と仲間たちは最近山頂で謎の発光が目撃されたり奇妙な音が聞こえたりと怪現象が相次いだピント山へ探検に向かう事にした。山頂にたどり着いたトム達は、そこで突如発光した巨石に飲み込まれてしまう。そこには地球の精霊チキ(声・坂本千夏)がいた。チキが言うには分裂した自身のかけらと一つにならなければ地球が滅びてしまうと言うのだが。
2013年に58歳で死去したアニメ作家、中村隆太郎。出崎統監督作品の原画や佐藤順一監督作品の絵コンテなどを手掛け、1994年に宮沢賢治の小説をアニメ化した「グスコーブドリの伝記」で監督デビュー。「serial experiment lain」(1996年)で国内外で高い評価を集めました。先鋭的な映像表現の担い手で、作家色の強い作品を生み出すアニメーターだったと言えるでしょう。その同氏が「グスコーブドリの伝記」より前の1992年に完成させながらお蔵入りとなった本当の意味での初監督作品、それが「ちびねこトムの大冒険」です。「アニメ関係者ですら観た者は少ない」と言われるほどの幻の1本で、ミニシアターでの限定上映とは言え劇場公開にまで漕ぎ着けたのは中村隆太郎没後の2014年。その後もソフト化や配信にも乗ることはなく、鑑賞するには散発的なTV放送かミニシアターなどでの単独上映を期待するしかないという代物です。今回、大須シネマにて2週間ロードショーされる事になり、それを利用してこの幻の作品を観てきました。
飯野真澄の手による児童文学を原作にしたこのアニメは、80分とそれほど長くない上映時間ですが、実に60,000枚という作画枚数を投入して作られました。キャラクターデザインは後年中村と共にPSソフト「ポポロクロイス物語」のアニメシーンにも参加した大橋学、作画に参加したアニメーターの中には後に「人狼」を手掛けた沖浦啓之などもいます。音楽に川井憲次、音響監督に斯波重治、美術監督に小倉宏昌と「機動警察パトレイバー」の主要スタッフが並び、キャストも藤田淑子、坂本千夏以下は野沢雅子、高山みなみ、かないみか、中尾隆聖、大塚明夫、飛田展男ら錚々たるメンバーです。これでもお蔵入りとなって20年以上日の目を見ることなく埋もれていたあたりに時の運の難しさを感じさせます。
子供向けファンタジーらしい穏やかな語り口のイントロから、突如地球の命運を懸けた冒険へ出ることになるトムたち。作画の妙は前半は細かなキャラクターの芝居に、後半はダイナミックなアクションに、それぞれふんだんに投入された枚数でもって画面の迫力を支えます。後に「lain」で見せるアバンギャルドな映像表現の片鱗も既に現れているほか、終盤にはまるで「名探偵コナン」を先取りしたようなスケボーアクションまで登場します。どのシーンもそれほど主張は強くないのですが、少し注意して観るだけで実に贅沢な作りをしていることが分かるはず。
メッセージ性が強すぎて今観るには少し気恥ずかしさもありますが、声優陣の見事な演技も手伝って重厚さすら漂う余韻を残す一本です。
この出来栄えでも埋もれることがある、という時の不思議さを噛み締めてしまう一本。これを逃すと次はいつになるか分からないのでお時間のある方は是非どうぞ。
こんばんは、小島@監督です。
とは言え久しぶりの謎解きゲームは楽しかった。次は屋内でやれるヤツにしたいかな(笑)
さて、今回の映画は「ちびねこトムの大冒険 地球を救え!なかまたち」です。
夏休み最初の日、トム(声・藤田淑子)と仲間たちは最近山頂で謎の発光が目撃されたり奇妙な音が聞こえたりと怪現象が相次いだピント山へ探検に向かう事にした。山頂にたどり着いたトム達は、そこで突如発光した巨石に飲み込まれてしまう。そこには地球の精霊チキ(声・坂本千夏)がいた。チキが言うには分裂した自身のかけらと一つにならなければ地球が滅びてしまうと言うのだが。
2013年に58歳で死去したアニメ作家、中村隆太郎。出崎統監督作品の原画や佐藤順一監督作品の絵コンテなどを手掛け、1994年に宮沢賢治の小説をアニメ化した「グスコーブドリの伝記」で監督デビュー。「serial experiment lain」(1996年)で国内外で高い評価を集めました。先鋭的な映像表現の担い手で、作家色の強い作品を生み出すアニメーターだったと言えるでしょう。その同氏が「グスコーブドリの伝記」より前の1992年に完成させながらお蔵入りとなった本当の意味での初監督作品、それが「ちびねこトムの大冒険」です。「アニメ関係者ですら観た者は少ない」と言われるほどの幻の1本で、ミニシアターでの限定上映とは言え劇場公開にまで漕ぎ着けたのは中村隆太郎没後の2014年。その後もソフト化や配信にも乗ることはなく、鑑賞するには散発的なTV放送かミニシアターなどでの単独上映を期待するしかないという代物です。今回、大須シネマにて2週間ロードショーされる事になり、それを利用してこの幻の作品を観てきました。
飯野真澄の手による児童文学を原作にしたこのアニメは、80分とそれほど長くない上映時間ですが、実に60,000枚という作画枚数を投入して作られました。キャラクターデザインは後年中村と共にPSソフト「ポポロクロイス物語」のアニメシーンにも参加した大橋学、作画に参加したアニメーターの中には後に「人狼」を手掛けた沖浦啓之などもいます。音楽に川井憲次、音響監督に斯波重治、美術監督に小倉宏昌と「機動警察パトレイバー」の主要スタッフが並び、キャストも藤田淑子、坂本千夏以下は野沢雅子、高山みなみ、かないみか、中尾隆聖、大塚明夫、飛田展男ら錚々たるメンバーです。これでもお蔵入りとなって20年以上日の目を見ることなく埋もれていたあたりに時の運の難しさを感じさせます。
子供向けファンタジーらしい穏やかな語り口のイントロから、突如地球の命運を懸けた冒険へ出ることになるトムたち。作画の妙は前半は細かなキャラクターの芝居に、後半はダイナミックなアクションに、それぞれふんだんに投入された枚数でもって画面の迫力を支えます。後に「lain」で見せるアバンギャルドな映像表現の片鱗も既に現れているほか、終盤にはまるで「名探偵コナン」を先取りしたようなスケボーアクションまで登場します。どのシーンもそれほど主張は強くないのですが、少し注意して観るだけで実に贅沢な作りをしていることが分かるはず。
メッセージ性が強すぎて今観るには少し気恥ずかしさもありますが、声優陣の見事な演技も手伝って重厚さすら漂う余韻を残す一本です。
この出来栄えでも埋もれることがある、という時の不思議さを噛み締めてしまう一本。これを逃すと次はいつになるか分からないのでお時間のある方は是非どうぞ。
プロレスラーになりたい人、身近にはいたりしませんか。
これを読む人にそういう人がいるとは思えませんが、
プロレスラーになるには、やっぱりテストがあったりします。
それを『入門テスト』とか『入団テスト』などと言いますが、
なぜかこれが不思議なことに女子プロレスだったりすると、
言い方が変わって『オーディション』になるんですよね。
オーディションも意味的にテストとあまり変わらないですが、
どことなくヒロインを決めるような感覚に聞こえますよね。
なんか、どことない不公平感・・・。
さて、『機動戦士ガンダムSEED』劇場版放映の発表から、
じゃあ誰がその作品の主題歌を唄うのかという期待。
その期待というのはやっぱり『T.M.Revolution』でして、
もうそれ以外はありえないとずっと思っていました。
それなのに、いつまで経っても主題歌の情報が出ず、
この感じはいよいよ、実は別のアーティストでは?と、
T.M.Revolutionの歌唱に私はちょっと諦めている感じ。
もっともここ最近のガンダムシリーズの続編モノは、
いちいちその期待を悪い意味で裏切るのが得意です。
それもあり、ここまで主題歌について発表されないのは、
もうこれはT.M.Revolutionじゃないと結論付けていました。
むしろ、ここからはそれ以外のアーティストが発表されて、
ズッコケ呆れるのをちょっと楽しみにするまでありました。
そんな先日、アーティストの発表さえも忘れていた先週、
突然に主題歌についての情報が飛び込んできました。
タイトル『FREEDOM』/アーティスト 西川貴教 with t.komuro
お、やったじゃないですか、主題歌が西川貴教アニキっす!
そして作曲は小室哲哉さんと、なんとも豪華でステキ!
・・・いや、そうじゃないんですよ。それだと半分正解。
私が期待していたのは、T.M.Revolutionなのであって、
浅倉大介プロデュースの歌だったりするのですよ。
そこまでやっての、機動戦士ガンダムSEEDだと思います。
とは言え、それでも西川貴教アニキであってくれたことに、
やっぱり安心したファンも多いのではないでしょうか。
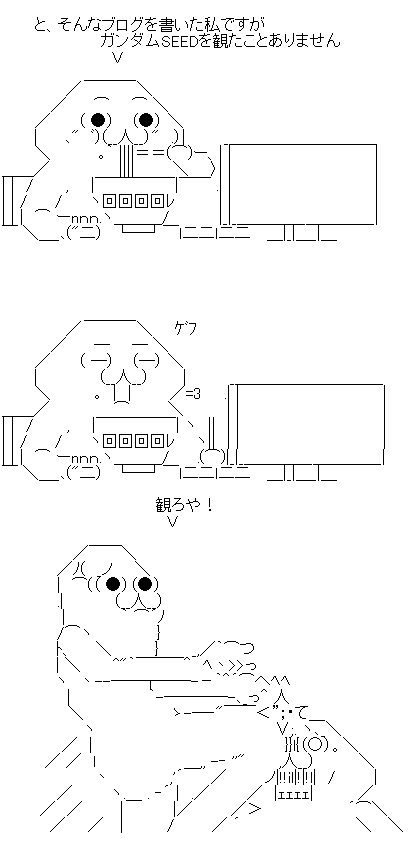
これを読む人にそういう人がいるとは思えませんが、
プロレスラーになるには、やっぱりテストがあったりします。
それを『入門テスト』とか『入団テスト』などと言いますが、
なぜかこれが不思議なことに女子プロレスだったりすると、
言い方が変わって『オーディション』になるんですよね。
オーディションも意味的にテストとあまり変わらないですが、
どことなくヒロインを決めるような感覚に聞こえますよね。
なんか、どことない不公平感・・・。
さて、『機動戦士ガンダムSEED』劇場版放映の発表から、
じゃあ誰がその作品の主題歌を唄うのかという期待。
その期待というのはやっぱり『T.M.Revolution』でして、
もうそれ以外はありえないとずっと思っていました。
それなのに、いつまで経っても主題歌の情報が出ず、
この感じはいよいよ、実は別のアーティストでは?と、
T.M.Revolutionの歌唱に私はちょっと諦めている感じ。
もっともここ最近のガンダムシリーズの続編モノは、
いちいちその期待を悪い意味で裏切るのが得意です。
それもあり、ここまで主題歌について発表されないのは、
もうこれはT.M.Revolutionじゃないと結論付けていました。
むしろ、ここからはそれ以外のアーティストが発表されて、
ズッコケ呆れるのをちょっと楽しみにするまでありました。
そんな先日、アーティストの発表さえも忘れていた先週、
突然に主題歌についての情報が飛び込んできました。
タイトル『FREEDOM』/アーティスト 西川貴教 with t.komuro
お、やったじゃないですか、主題歌が西川貴教アニキっす!
そして作曲は小室哲哉さんと、なんとも豪華でステキ!
・・・いや、そうじゃないんですよ。それだと半分正解。
私が期待していたのは、T.M.Revolutionなのであって、
浅倉大介プロデュースの歌だったりするのですよ。
そこまでやっての、機動戦士ガンダムSEEDだと思います。
とは言え、それでも西川貴教アニキであってくれたことに、
やっぱり安心したファンも多いのではないでしょうか。
昨日の歌会に参加された皆さん、お疲れ様でした。
今回は数年ぶりに会えて話せた人たちが何人もいて何だか嬉しくなりました。こういう時間は良いですね。
後はお笑いユニットの「東京03」を熱心に薦められました。お笑い、興味はあるもののイマイチ取っ掛かりを掴めずにいたのでまずはそこから行ってみましょうか(笑)
こんばんは、小島@監督です。
とかやってたら今期イチオシの「16bitセンセーション」をあまり布教できずに終わってしまったのが若干の心残り(苦笑)。
さて、今回の映画は「SISU/不死身の男」です。
第二次世界大戦末期、ソ連やナチス・ドイツの侵攻により国中が焦土と化しつつあったフィンランド。そこに愛犬と共に旅する1人の老人がいた。掘り当てた金塊を抱えて旅する老人はその道中でナチスの戦車隊と遭遇してしまう。老人が金塊を持っていることを知ったナチスたちは老人を殺して金塊を手にしようとする。しかし老人の予想外の反撃により兵士たちは次々と葬り去られて行った。やがて戦車隊の者たちは知る。その老人がかつてたった1人で300人以上のソ連兵を抹殺した伝説の兵士アアタミ・コルピ(ヨルマ・トンミラ)であることを。
アクションだったりホラーだったり料理の仕方次第でジャンルとしては分けられるものの、ストーリーの基本骨子が「絶対に怒らせちゃいけない人をキレさせた」系映画は洋の東西を問わず広く作られています。最近では「ジョン・ウィック」や「イコライザー」もこの部類に入るでしょう。北欧の雄フィンランドから、そんな映画の新たな傑作が登場しました。
「荒野・金塊・軍隊・アウトロー」と西部劇のようなキーワードが並ぶプロットはあくまでシンプル、唸ったり叫んだりはあれど主人公アアタミの本編中のセリフは僅か二言という切り詰められた脚本、過ぎるくらいに単純明快な物語です。
この映画がひと味違うのはその単純明快さに迷いが無いこと、映画としての味わいをバイオレンス描写に振り切ったことにあります。地雷を食らっても火あぶりになっても首を吊られても死なない老人アアタミの超人ぶりと一緒にいるのにこちらもやっぱり何だかんだ死なない愛犬ウッコ、しかもアアタミは武器をその場その場で調達したりはするもののメインに使うのはツルハシ1本。そんなアアタミが軍隊相手に無双する姿を激烈なほどスピーディーに見せる異様なドライブ感こそこの映画の最大の魅力です。振り返る暇などありません。良く思いついたなコレ!?と言いたくなるアクションとシチュエーションの数々を全く出し惜しみする気の無いボリュームで畳みかけ、それは最早高度なギャグの領域。興奮と笑いが同時波状攻撃で襲い掛かってくる90分を観客は目撃する事になります。
アアタミの問答無用の殺戮ぶりにちょっと快感すら覚えてしまう、このアドレナリン全開ぶりはもう観てもらわないと伝わりそうにありません。気になっている方は何とか時間捕まえて観に行ってしまいましょう。
コイツはヤバい。
あとせっかくなら応援上映もプリーズ。
今回は数年ぶりに会えて話せた人たちが何人もいて何だか嬉しくなりました。こういう時間は良いですね。
後はお笑いユニットの「東京03」を熱心に薦められました。お笑い、興味はあるもののイマイチ取っ掛かりを掴めずにいたのでまずはそこから行ってみましょうか(笑)
こんばんは、小島@監督です。
とかやってたら今期イチオシの「16bitセンセーション」をあまり布教できずに終わってしまったのが若干の心残り(苦笑)。
さて、今回の映画は「SISU/不死身の男」です。
第二次世界大戦末期、ソ連やナチス・ドイツの侵攻により国中が焦土と化しつつあったフィンランド。そこに愛犬と共に旅する1人の老人がいた。掘り当てた金塊を抱えて旅する老人はその道中でナチスの戦車隊と遭遇してしまう。老人が金塊を持っていることを知ったナチスたちは老人を殺して金塊を手にしようとする。しかし老人の予想外の反撃により兵士たちは次々と葬り去られて行った。やがて戦車隊の者たちは知る。その老人がかつてたった1人で300人以上のソ連兵を抹殺した伝説の兵士アアタミ・コルピ(ヨルマ・トンミラ)であることを。
アクションだったりホラーだったり料理の仕方次第でジャンルとしては分けられるものの、ストーリーの基本骨子が「絶対に怒らせちゃいけない人をキレさせた」系映画は洋の東西を問わず広く作られています。最近では「ジョン・ウィック」や「イコライザー」もこの部類に入るでしょう。北欧の雄フィンランドから、そんな映画の新たな傑作が登場しました。
「荒野・金塊・軍隊・アウトロー」と西部劇のようなキーワードが並ぶプロットはあくまでシンプル、唸ったり叫んだりはあれど主人公アアタミの本編中のセリフは僅か二言という切り詰められた脚本、過ぎるくらいに単純明快な物語です。
この映画がひと味違うのはその単純明快さに迷いが無いこと、映画としての味わいをバイオレンス描写に振り切ったことにあります。地雷を食らっても火あぶりになっても首を吊られても死なない老人アアタミの超人ぶりと一緒にいるのにこちらもやっぱり何だかんだ死なない愛犬ウッコ、しかもアアタミは武器をその場その場で調達したりはするもののメインに使うのはツルハシ1本。そんなアアタミが軍隊相手に無双する姿を激烈なほどスピーディーに見せる異様なドライブ感こそこの映画の最大の魅力です。振り返る暇などありません。良く思いついたなコレ!?と言いたくなるアクションとシチュエーションの数々を全く出し惜しみする気の無いボリュームで畳みかけ、それは最早高度なギャグの領域。興奮と笑いが同時波状攻撃で襲い掛かってくる90分を観客は目撃する事になります。
アアタミの問答無用の殺戮ぶりにちょっと快感すら覚えてしまう、このアドレナリン全開ぶりはもう観てもらわないと伝わりそうにありません。気になっている方は何とか時間捕まえて観に行ってしまいましょう。
コイツはヤバい。
あとせっかくなら応援上映もプリーズ。
たまたま観たテレビで流れてきた、風邪薬『ルル』のCM。
すっかり風邪薬と言えばお馴染みの『ルル』なのですが、
そういえば、昔の我が家の風邪薬はルルばかりでした。
そのCMで観たルルの名前は『新ルルAゴールドDXα』。
は?
『新』しくて『A』で『ゴールド』で『DX』で『α』なの?
もうありったけのバージョンアップが詰め込まれてますが、
命名時に会議で止める冷静な人はいなかったのでしょうか?
とは言え、このまま名前が付与されるのも見守りたいですね。
さて、カップ焼きそば『UFO』、突然食べたくなりませんか。
ノーマルサイズだとちょっと小さくて物足りないですので、
食べるならやっぱり四角いパッケージの大盛りですよね。
小学校くらいからお世話になっているUFOは今も現役です。
当時のパッケージも未だになんとなく覚えていたりします。
そんなUFO、食べている最中はもちろん美味しいのですが、
食べた後の容器は部屋に放置すると、これがなぜか臭い!
カップ麺とかってやっぱり手軽で持ち運びやすいせいか、
食べる時になんとなく自分の部屋に持ち込みがちですよね。
そして食べた後のカップは洗わなくていいこともあって、
食べ終わった後は、なんとなくそのまま部屋に放置しがち。
そしてその放置したカップからは悪臭を放ち始めます。
これ、UFOの1番のウリであるソースの匂いなんですが、
なんで食べている最中は香ばしい食欲をそそる匂いなのに、
放置した容器単体では、こんなに悪臭になるんですかね?
正直、この瞬間だけは「こんな臭いもん食べてたのか?」と、
なんか変な感じに冷静になってしまう自分がいたりします。
これってUFOに限らずあることで、最もコーヒーなんかも、
飲んでいる時はいい香りと思っているはずなのに、
こぼした後のコーヒーとかはやっぱりなぜか悪臭なのです。
なぜ、好んでいた匂いが悪臭になってしまうのでしょうね。
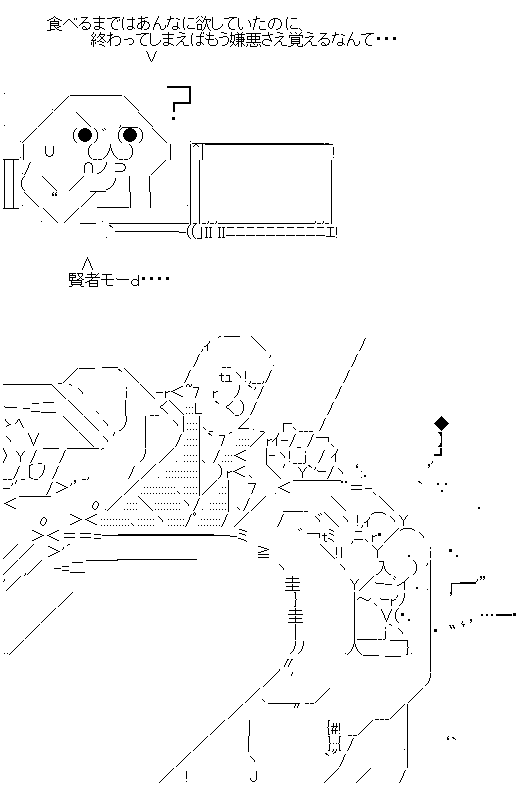
すっかり風邪薬と言えばお馴染みの『ルル』なのですが、
そういえば、昔の我が家の風邪薬はルルばかりでした。
そのCMで観たルルの名前は『新ルルAゴールドDXα』。
は?
『新』しくて『A』で『ゴールド』で『DX』で『α』なの?
もうありったけのバージョンアップが詰め込まれてますが、
命名時に会議で止める冷静な人はいなかったのでしょうか?
とは言え、このまま名前が付与されるのも見守りたいですね。
さて、カップ焼きそば『UFO』、突然食べたくなりませんか。
ノーマルサイズだとちょっと小さくて物足りないですので、
食べるならやっぱり四角いパッケージの大盛りですよね。
小学校くらいからお世話になっているUFOは今も現役です。
当時のパッケージも未だになんとなく覚えていたりします。
そんなUFO、食べている最中はもちろん美味しいのですが、
食べた後の容器は部屋に放置すると、これがなぜか臭い!
カップ麺とかってやっぱり手軽で持ち運びやすいせいか、
食べる時になんとなく自分の部屋に持ち込みがちですよね。
そして食べた後のカップは洗わなくていいこともあって、
食べ終わった後は、なんとなくそのまま部屋に放置しがち。
そしてその放置したカップからは悪臭を放ち始めます。
これ、UFOの1番のウリであるソースの匂いなんですが、
なんで食べている最中は香ばしい食欲をそそる匂いなのに、
放置した容器単体では、こんなに悪臭になるんですかね?
正直、この瞬間だけは「こんな臭いもん食べてたのか?」と、
なんか変な感じに冷静になってしまう自分がいたりします。
これってUFOに限らずあることで、最もコーヒーなんかも、
飲んでいる時はいい香りと思っているはずなのに、
こぼした後のコーヒーとかはやっぱりなぜか悪臭なのです。
なぜ、好んでいた匂いが悪臭になってしまうのでしょうね。
昨日一昨日と福岡で開催されていた「THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 10thLIVE TOUR Act-3 R@ISE THE DREAM!!!」をDay2のみ配信で観ていました。現在放送中のアニメでクライマックスに展開する1stライブと同じタイトルを冠したこのイベントでは、アニメをコンセプトに文字通り「このシアターでこのアイドル達が1stライブをするならこんな感じ」という印象で、セットリストの半分は先輩達である765ASのカバーという、もう良い加減古参になって来た私を一直線で狙い撃ちにくる並びに見事に撃沈されておりました。
こんばんは、小島@監督です。
10周年を締め括る来年2月のツアーファイナルでは遂に39人全員が出演することが発表され、これは何としても観に行かねばなるまいて。
さて、今回の映画は「ゴジラ-1.0」です。
1945年、大戸島の守備隊基地に敷島(神木隆之介)が駆る零戦が着陸した。機体の不調を訴えてのものだったが、整備士長の橘(青木崇高)は機体にどこも不具合を見つけられず、敷島が何かを隠していることを勘付く。
その日の夜、基地が突如恐竜に似た怪獣「呉爾羅」の襲撃を受け敷島と橘を残して全滅してしまった。
戦後、心に傷を負った敷島は給料は良いが危険度の高い残存機雷掃海の仕事に就いていた。その頃、太平洋上で米国の船舶が正体不明の巨大な生物に襲撃される事故が相次いで発生していた…
圧巻。まさにその言葉が相応しい。
来年シリーズ70周年というメモリアルイヤーを迎える「ゴジラ」、更に国内製作30本目のアニバーサリーとなる作品が遂に公開です。これまでゴジラシリーズは第1作が製作された1954年を起点にしていることがほとんどでしたが、今作ではそれより前の時代を舞台に描かれる初めての作品となります。監督はVFXを駆使した映画を第一線で作り続けてきた山崎貴。「ALWAYS三丁目の夕日」「永遠の0」などで度々昭和の時代を舞台として来たこと、「DESTINY鎌倉ものがたり」「ゴーストブックおばけずかん」などで超自然的なものを描いて来たこと、そして「ゴジラTHE RIDE」で短編ながらゴジラを描いた経験、それらフィルモグラフィーの全てを注ぎ込んだかのような一本となっています。
何を置いても映像の迫力が尋常じゃない1本です。
予算規模で行ったら1/10にも満たないでしょうがハリウッドの大作映画にもタメを張れる画が全編に渡り展開します。中でもゴジラ登場シーンの大半を占める海洋でのシークエンスの数々はちょっとどうかしている出来の良さで、CGが変に浮いたようなところなど微塵も無くVFXの技術の進歩と熟練のスタッフがそれを扱うことの凄みを如実に見せてくれます。
「シン・ゴジラ」では東日本大震災に代表される天災の象徴であり、それ故に生存本能以外の意思を感じない無機質さでやって来てただ街に踏み入りただ破壊して行く恐ろしさがありましたが、今作のゴジラは戦争の呪いの化身そのもので、人間に対し憎悪や殺意を感じさせる存在です。人間を遥かに超越した存在が明確な殺意を持って破壊の限りを尽くし街を蹂躙する。「シン・ゴジラ」とは別種の恐怖を描いています。これが、トラウマとサバイバーズギルトに苦しむ青年・敷島を軸とする人間ドラマと絶妙に噛み合うことで物語をダイナミックなものにしています。
その人間ドラマ、一見するとベタでもあり陳腐に映ってしまう瞬間もあったり、変なところで穴というかツッコミどころみたいなものも多いのですが、主演神木隆之介の演技がとにかく素晴らしいの一言で、強い説得力でもって映画の魅力を底上げしてくれていて、決して怪獣のただの添え物になっていません。物語やセリフへの解釈、演技プランを含め、監督の予想を超えて来た部分もあったのではないでしょうか。浜辺美波、佐々木蔵之介、吉岡秀隆、安藤サクラ、山田裕貴ら共演陣の演技も見事で、ゴジラが出てきていない部分は良くできた王道の日本映画という印象です。現代日本を舞台にしたポリティカルフィクションで「官」が戦う物語でもあった「シン・ゴジラ」とここでも好対照で、国家が機能不全状態に陥り軍も力を失っていた戦後すぐを舞台に、心も体も傷を負ったボロボロの「個」がそれでも奮起し「生」を希求する物語が、ゴジラという絶対的な絶望を前に輝きを放つのです。
伏線の張り方も分かりやすく、容易に結末が予想できてしまうのも難点とは言えますが、王道とは裏を返せばそれだけ観るためのハードルが低い証拠です。予想を裏切るのではなく予想の先を行く。最も難しい道をこの映画は選び、そして最高の場所へ辿り着きました。何よりこの圧倒的なスペクタクルはスクリーンで味わなければ勿体無い。
これは怪獣映画の一つの到達点だ。
こんばんは、小島@監督です。
10周年を締め括る来年2月のツアーファイナルでは遂に39人全員が出演することが発表され、これは何としても観に行かねばなるまいて。
さて、今回の映画は「ゴジラ-1.0」です。
1945年、大戸島の守備隊基地に敷島(神木隆之介)が駆る零戦が着陸した。機体の不調を訴えてのものだったが、整備士長の橘(青木崇高)は機体にどこも不具合を見つけられず、敷島が何かを隠していることを勘付く。
その日の夜、基地が突如恐竜に似た怪獣「呉爾羅」の襲撃を受け敷島と橘を残して全滅してしまった。
戦後、心に傷を負った敷島は給料は良いが危険度の高い残存機雷掃海の仕事に就いていた。その頃、太平洋上で米国の船舶が正体不明の巨大な生物に襲撃される事故が相次いで発生していた…
圧巻。まさにその言葉が相応しい。
来年シリーズ70周年というメモリアルイヤーを迎える「ゴジラ」、更に国内製作30本目のアニバーサリーとなる作品が遂に公開です。これまでゴジラシリーズは第1作が製作された1954年を起点にしていることがほとんどでしたが、今作ではそれより前の時代を舞台に描かれる初めての作品となります。監督はVFXを駆使した映画を第一線で作り続けてきた山崎貴。「ALWAYS三丁目の夕日」「永遠の0」などで度々昭和の時代を舞台として来たこと、「DESTINY鎌倉ものがたり」「ゴーストブックおばけずかん」などで超自然的なものを描いて来たこと、そして「ゴジラTHE RIDE」で短編ながらゴジラを描いた経験、それらフィルモグラフィーの全てを注ぎ込んだかのような一本となっています。
何を置いても映像の迫力が尋常じゃない1本です。
予算規模で行ったら1/10にも満たないでしょうがハリウッドの大作映画にもタメを張れる画が全編に渡り展開します。中でもゴジラ登場シーンの大半を占める海洋でのシークエンスの数々はちょっとどうかしている出来の良さで、CGが変に浮いたようなところなど微塵も無くVFXの技術の進歩と熟練のスタッフがそれを扱うことの凄みを如実に見せてくれます。
「シン・ゴジラ」では東日本大震災に代表される天災の象徴であり、それ故に生存本能以外の意思を感じない無機質さでやって来てただ街に踏み入りただ破壊して行く恐ろしさがありましたが、今作のゴジラは戦争の呪いの化身そのもので、人間に対し憎悪や殺意を感じさせる存在です。人間を遥かに超越した存在が明確な殺意を持って破壊の限りを尽くし街を蹂躙する。「シン・ゴジラ」とは別種の恐怖を描いています。これが、トラウマとサバイバーズギルトに苦しむ青年・敷島を軸とする人間ドラマと絶妙に噛み合うことで物語をダイナミックなものにしています。
その人間ドラマ、一見するとベタでもあり陳腐に映ってしまう瞬間もあったり、変なところで穴というかツッコミどころみたいなものも多いのですが、主演神木隆之介の演技がとにかく素晴らしいの一言で、強い説得力でもって映画の魅力を底上げしてくれていて、決して怪獣のただの添え物になっていません。物語やセリフへの解釈、演技プランを含め、監督の予想を超えて来た部分もあったのではないでしょうか。浜辺美波、佐々木蔵之介、吉岡秀隆、安藤サクラ、山田裕貴ら共演陣の演技も見事で、ゴジラが出てきていない部分は良くできた王道の日本映画という印象です。現代日本を舞台にしたポリティカルフィクションで「官」が戦う物語でもあった「シン・ゴジラ」とここでも好対照で、国家が機能不全状態に陥り軍も力を失っていた戦後すぐを舞台に、心も体も傷を負ったボロボロの「個」がそれでも奮起し「生」を希求する物語が、ゴジラという絶対的な絶望を前に輝きを放つのです。
伏線の張り方も分かりやすく、容易に結末が予想できてしまうのも難点とは言えますが、王道とは裏を返せばそれだけ観るためのハードルが低い証拠です。予想を裏切るのではなく予想の先を行く。最も難しい道をこの映画は選び、そして最高の場所へ辿り着きました。何よりこの圧倒的なスペクタクルはスクリーンで味わなければ勿体無い。
これは怪獣映画の一つの到達点だ。
やっと土曜日になり「ヘイ!連休だぜ!」と思うのも束の間、
なんか喉がいがらっぽい気がする・・・となんか不安な感じ。
日曜日になると、気がするどころか、なんか寒気を感じて、
いがらっぽいだけではなく、しっかり咳が出てしまう始末。
いよいよもって熱でも出してしまったかと体温計を脇に挟み、
「ピーッ!ピーッ!」となるそれを恐る恐る見てみると・・・
『37度8分』
あー、またも発熱症状です、測らなきゃ分からなかったのに。
コロナなのか、インフルエンザなのか、まだわからないですが、
月頭に私がやらないと会社がうるさい仕事が残っているので、
月曜日は無理やり出勤して、終わったら帰ろうと思います。
しかし、熱を出すと節々が痛かったり、寒気が酷かったりと、
若かったころってこんなにも、苦しんだりしましたっけ??
さて、ゲーム『ストリートファイター6』のオンライン対戦で、
かなり精度の高いチート(不正行為)が出てきました。
この精度が高いというのは、人間が操作しているような、
かなり自然な動き(プレイ)に見えてしまうようなのです。
プロゲーマーが何度もそのチートキャラと戦って検証し、
人間がプレイする部分が僅かしかないと判断したようです。
その発覚したチート、世界ランク1位となっていましたが
すでにそのチートに対する処分はされてはいますが、
個人的には今回の騒動って怖いなと思うところがあります。
しっかり検証したからこそチートと判断された感じですが、
ただ対戦をしていたら気が付かなかったかもしれません。
そう思うと、これからのゲームのオンライン対戦などは、
知らない間に人間と思っていた相手がAIなのかも知れません。
相手が、同じ人間だからこそ夢中で取り組んでいたのに、
実はオンライン対戦と勘違いしているのかもしれません。
AIの技術などが進んでくると、自分の技量に合わせた強さの、
適当に負けたり勝ったりしてくれるようになったりし、
このゲーム、賑わってると思って夢中でやっていると、
実はものすごく過疎っていたりするのかもしれません。
オンラインゲームで人気が無くなってきてしまうと、
対戦相手や協力するプレイヤーがマッチングしなくなります。
それなのにAIが人間っぽい動きをしてしまうようになると、
「私は人間とプレイしている」と勘違いをしていまいます。
メーカー自らこのような優秀なAIを実装していくことで、
このゲームは賑わっていると錯覚させることもできます。
するとプレイヤーも戻ってくるかもしれないですからね。
そのうちチャットなどの会話などもやってくれそうですし、
本当にゲーム上にAIが席巻する日が来るかもしれませんね。
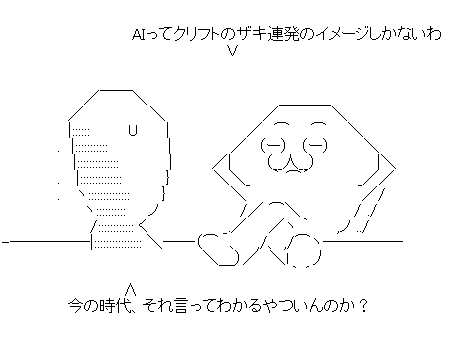
なんか喉がいがらっぽい気がする・・・となんか不安な感じ。
日曜日になると、気がするどころか、なんか寒気を感じて、
いがらっぽいだけではなく、しっかり咳が出てしまう始末。
いよいよもって熱でも出してしまったかと体温計を脇に挟み、
「ピーッ!ピーッ!」となるそれを恐る恐る見てみると・・・
『37度8分』
あー、またも発熱症状です、測らなきゃ分からなかったのに。
コロナなのか、インフルエンザなのか、まだわからないですが、
月頭に私がやらないと会社がうるさい仕事が残っているので、
月曜日は無理やり出勤して、終わったら帰ろうと思います。
しかし、熱を出すと節々が痛かったり、寒気が酷かったりと、
若かったころってこんなにも、苦しんだりしましたっけ??
さて、ゲーム『ストリートファイター6』のオンライン対戦で、
かなり精度の高いチート(不正行為)が出てきました。
この精度が高いというのは、人間が操作しているような、
かなり自然な動き(プレイ)に見えてしまうようなのです。
プロゲーマーが何度もそのチートキャラと戦って検証し、
人間がプレイする部分が僅かしかないと判断したようです。
その発覚したチート、世界ランク1位となっていましたが
すでにそのチートに対する処分はされてはいますが、
個人的には今回の騒動って怖いなと思うところがあります。
しっかり検証したからこそチートと判断された感じですが、
ただ対戦をしていたら気が付かなかったかもしれません。
そう思うと、これからのゲームのオンライン対戦などは、
知らない間に人間と思っていた相手がAIなのかも知れません。
相手が、同じ人間だからこそ夢中で取り組んでいたのに、
実はオンライン対戦と勘違いしているのかもしれません。
AIの技術などが進んでくると、自分の技量に合わせた強さの、
適当に負けたり勝ったりしてくれるようになったりし、
このゲーム、賑わってると思って夢中でやっていると、
実はものすごく過疎っていたりするのかもしれません。
オンラインゲームで人気が無くなってきてしまうと、
対戦相手や協力するプレイヤーがマッチングしなくなります。
それなのにAIが人間っぽい動きをしてしまうようになると、
「私は人間とプレイしている」と勘違いをしていまいます。
メーカー自らこのような優秀なAIを実装していくことで、
このゲームは賑わっていると錯覚させることもできます。
するとプレイヤーも戻ってくるかもしれないですからね。
そのうちチャットなどの会話などもやってくれそうですし、
本当にゲーム上にAIが席巻する日が来るかもしれませんね。
ある意味これも「ウマ娘」の影響と言って間違い無いのですが、G1レースだけたまに馬券を買って観るようになりました。毎回じゃないのは単に土日がスケジュール的に買いに行く暇が無いことも多いからで、買ってもせいぜい500円くらいの本当に気楽な遊びという程度。
買うようになって日が浅いのでどこら辺を見て予想立てるべきかまだ分かるような分からないような感じで大抵は当たりませんが、昨日の天皇賞(秋)では初めて3連複を当てることができてこれがなかなか嬉しい。倍率は20倍ちょっとなので大したことはないのですけれど。
こんばんは、小島@監督です。
しかし昨日のイクイノックスのあまりの強さにはさすがに観てて震えました。しかも2,000mレースのワールドレコードだとか。とんでもない馬がいたものです。
さて、今回の映画は「シン・ゴジラ:オルソ」です。
今回は粗筋については割愛します。
「色彩」がもたらす情報量は自分たちが思っているより遥かに多い。それを削ぎ落とした時、見えるものが大きく変わります。
2016年に公開された庵野秀明監督の傑作「シン・ゴジラ」、11月3日に「ゴジラー⒈0」が公開されるのに合わせてモノクロ版が製作され全国で僅か7館、それも3日間だけのごく限定的なものながらスクリーン上映されました。
タイトルの「オルソ」とはオルソクロマチックフィルム(青と緑の色調にのみ反応し赤色に対して感度を持たないフィルム)のことだそうです。映像を観た感覚では単に色彩を落としただけではなく陰影を強調しているような印象でした。「オルソ」はモノクロ化に当たっての方針のようなものでしょう。また今年11月30日を以て事業終了を決定している東京現像所がDCP(デジタルシネマパッケージ)を手掛けた最後の作品となりました。
もともとカラーだった映像をモノクロにする、というのがどの映画にもハマるものではありませんが、こと「シン・ゴジラ」に至っては驚くほどにマッチし作品が「何を見せたいか」が鮮明に浮き彫りになりました。
まずゴジラ第二形態(いわゆる「蒲田くん」と俗称されるアレ)や終盤の「在来線爆弾」などCG臭さが抜けなかった箇所で画面に統一感が生まれている上、どことなくスーツアクトやミニチュアワークを見ているような質感になり往年の「東宝特撮映画」的テイストが割増になっています。何よりゴジラが熱線を吐き首都を焼き払うあのシーンの恐ろしさの際立ちは特筆もの。
人物についても陰影を強調した画面は特にクローズアップでの緊張感を増幅させていて、会議の場面が多い本編と絶妙な親和性を生み出しています。雰囲気としては岡本喜八監督の名作「日本のいちばん長い日」に近い印象。観ていて思った以上にセリフを集中して聴いている自分に気付いたのも発見でした。色彩が無くなったぶん、脳のリソースに余裕ができたんでしょうか。
映像が全体的にクラシックな風格を持ち得たことは音声面でも好影響を与えており、劇中で使われている伊福部昭の音楽やもともと最近の映画にしては3.1chとチャンネルが少なく、外に広がるというより内に閉じていくような音響設計とも相性が良くなっていて、総じて作品そのものの純度が上がった格好です。
何度も観ていて慣れているはずの映画を実に新鮮な気分で楽しむことができました。
2016年当時、封切りから少し遅れてIMAX版も公開されていてそれも観に行っているのですが、正直なところ画面も音響もIMAXのハイスペックさを持て余しているような印象でこう言っては何ですが「ただ追加料金を払って普段より大きなスクリーンで観た」以外の付加価値を感じられなかったのですが、今回のモノクロ版はむしろこの映画に必要なのは引き算だったと実感させてくれる稀有な映像体験でした。
せっかくの代物なのに公開規模が小さ過ぎるのがホント勿体無い。いずれBlu-rayや配信で観られる機会もできると思いますが、その時は是非その目で確かめていただきたいですね。
買うようになって日が浅いのでどこら辺を見て予想立てるべきかまだ分かるような分からないような感じで大抵は当たりませんが、昨日の天皇賞(秋)では初めて3連複を当てることができてこれがなかなか嬉しい。倍率は20倍ちょっとなので大したことはないのですけれど。
こんばんは、小島@監督です。
しかし昨日のイクイノックスのあまりの強さにはさすがに観てて震えました。しかも2,000mレースのワールドレコードだとか。とんでもない馬がいたものです。
さて、今回の映画は「シン・ゴジラ:オルソ」です。
今回は粗筋については割愛します。
「色彩」がもたらす情報量は自分たちが思っているより遥かに多い。それを削ぎ落とした時、見えるものが大きく変わります。
2016年に公開された庵野秀明監督の傑作「シン・ゴジラ」、11月3日に「ゴジラー⒈0」が公開されるのに合わせてモノクロ版が製作され全国で僅か7館、それも3日間だけのごく限定的なものながらスクリーン上映されました。
タイトルの「オルソ」とはオルソクロマチックフィルム(青と緑の色調にのみ反応し赤色に対して感度を持たないフィルム)のことだそうです。映像を観た感覚では単に色彩を落としただけではなく陰影を強調しているような印象でした。「オルソ」はモノクロ化に当たっての方針のようなものでしょう。また今年11月30日を以て事業終了を決定している東京現像所がDCP(デジタルシネマパッケージ)を手掛けた最後の作品となりました。
もともとカラーだった映像をモノクロにする、というのがどの映画にもハマるものではありませんが、こと「シン・ゴジラ」に至っては驚くほどにマッチし作品が「何を見せたいか」が鮮明に浮き彫りになりました。
まずゴジラ第二形態(いわゆる「蒲田くん」と俗称されるアレ)や終盤の「在来線爆弾」などCG臭さが抜けなかった箇所で画面に統一感が生まれている上、どことなくスーツアクトやミニチュアワークを見ているような質感になり往年の「東宝特撮映画」的テイストが割増になっています。何よりゴジラが熱線を吐き首都を焼き払うあのシーンの恐ろしさの際立ちは特筆もの。
人物についても陰影を強調した画面は特にクローズアップでの緊張感を増幅させていて、会議の場面が多い本編と絶妙な親和性を生み出しています。雰囲気としては岡本喜八監督の名作「日本のいちばん長い日」に近い印象。観ていて思った以上にセリフを集中して聴いている自分に気付いたのも発見でした。色彩が無くなったぶん、脳のリソースに余裕ができたんでしょうか。
映像が全体的にクラシックな風格を持ち得たことは音声面でも好影響を与えており、劇中で使われている伊福部昭の音楽やもともと最近の映画にしては3.1chとチャンネルが少なく、外に広がるというより内に閉じていくような音響設計とも相性が良くなっていて、総じて作品そのものの純度が上がった格好です。
何度も観ていて慣れているはずの映画を実に新鮮な気分で楽しむことができました。
2016年当時、封切りから少し遅れてIMAX版も公開されていてそれも観に行っているのですが、正直なところ画面も音響もIMAXのハイスペックさを持て余しているような印象でこう言っては何ですが「ただ追加料金を払って普段より大きなスクリーンで観た」以外の付加価値を感じられなかったのですが、今回のモノクロ版はむしろこの映画に必要なのは引き算だったと実感させてくれる稀有な映像体験でした。
せっかくの代物なのに公開規模が小さ過ぎるのがホント勿体無い。いずれBlu-rayや配信で観られる機会もできると思いますが、その時は是非その目で確かめていただきたいですね。

