同じ年度の夏と冬にオリンピックが開催されるという、
もうこんなことはないだろうなという不思議な年ですね。
始まる時はあんまりオリンピックに興味ない感じですが、
始まってみると意外と応援しちゃったりするのですが、
今年はいちいちケチがついて楽しめないんですよね。
不可解な選手の失格の多さに、ネガティブな報道など、
なんでこんか状況になってしまったのでしょうね。
政治的なものを介入せずに楽しむものだと思いますが、
最近は本当にスポーツ部分が蔑ろにされていると思います。
さて、こんなコロナ禍で不謹慎かとの懸念もありますが、
昨日土曜日は『Aqours』のライブに行って参りました。
もちろんAqoursとなったら会場はドームと言うことで、
ナゴヤドームで・・いや、今はバンテリンドームですね。
チケットは取れたもののこんな時期に開催できるのかと、
不安ではありましたが、何とか開催されるようで一安心。
『ラブライブ』は大好きなのコンテンツなのですが、
『μ's』含めラブライブに関するライブは行ったことがなく、
今回のAqoursのライブは大変楽しみにしていました。
ブルーレイなどでライブ何度か見てはいたのですが、
実際の会場でのパフォーマンスに大変興味がありました。
そして、いざ会場で見るとそのクオリティの高さに感心。
Aqoursのメンバーのパフォーマンスは当然なのですが、
会場に複数あるスクリーン映像が本当に驚きました。
今、パフォーマンスしている声優を撮影カメラ映像が、
作品中のキャラクターの歌唱シーンのアニメ映像と、
シンクロするように横並びで展開されているのです。
目まぐるしいカットでの歌唱シーンとシンクロして、
声優を追っかけるカメラに、ホントに驚きしかありません。
声優のパフォーマンスのみならず、スタッフ全員が、
ものすごい仕事で作り上げていて、まさに職人の仕事です。
そんなライブでしたが、実は今日の日曜日の2日目も、
チケットを取っちゃったりしてるんですよね!
では、行ってきます!
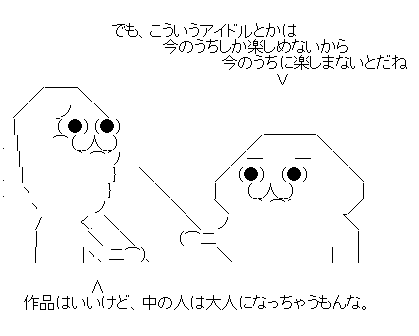
もうこんなことはないだろうなという不思議な年ですね。
始まる時はあんまりオリンピックに興味ない感じですが、
始まってみると意外と応援しちゃったりするのですが、
今年はいちいちケチがついて楽しめないんですよね。
不可解な選手の失格の多さに、ネガティブな報道など、
なんでこんか状況になってしまったのでしょうね。
政治的なものを介入せずに楽しむものだと思いますが、
最近は本当にスポーツ部分が蔑ろにされていると思います。
さて、こんなコロナ禍で不謹慎かとの懸念もありますが、
昨日土曜日は『Aqours』のライブに行って参りました。
もちろんAqoursとなったら会場はドームと言うことで、
ナゴヤドームで・・いや、今はバンテリンドームですね。
チケットは取れたもののこんな時期に開催できるのかと、
不安ではありましたが、何とか開催されるようで一安心。
『ラブライブ』は大好きなのコンテンツなのですが、
『μ's』含めラブライブに関するライブは行ったことがなく、
今回のAqoursのライブは大変楽しみにしていました。
ブルーレイなどでライブ何度か見てはいたのですが、
実際の会場でのパフォーマンスに大変興味がありました。
そして、いざ会場で見るとそのクオリティの高さに感心。
Aqoursのメンバーのパフォーマンスは当然なのですが、
会場に複数あるスクリーン映像が本当に驚きました。
今、パフォーマンスしている声優を撮影カメラ映像が、
作品中のキャラクターの歌唱シーンのアニメ映像と、
シンクロするように横並びで展開されているのです。
目まぐるしいカットでの歌唱シーンとシンクロして、
声優を追っかけるカメラに、ホントに驚きしかありません。
声優のパフォーマンスのみならず、スタッフ全員が、
ものすごい仕事で作り上げていて、まさに職人の仕事です。
そんなライブでしたが、実は今日の日曜日の2日目も、
チケットを取っちゃったりしてるんですよね!
では、行ってきます!
大体いつもアッパーでどんな深刻な状況でも絶対にしんみりさせたままにはしておかない作風が印象的だった「トロピカル〜ジュ!プリキュア」が終了し、その余韻も冷めやらぬ中、新シリーズ「デリシャスパーティ♡プリキュア」がスタート。物語の導き手がオネエキャラと言うのも当世らしい感じですが、何より「500Kcalパンチ」の語感のインパクトが最高。また1年間楽しませてもらえそうです。
こんばんは、小島@監督です。
「食」がテーマの一つだけあり初回の料理作画のシズル感はどれもかなりのものでしたが、あのクオリティで1年間やり切れるのかしら。
さて、今回の映画は「大怪獣のあとしまつ」です。
突如襲来し、首都圏を蹂躙して人々を恐怖に陥れた大怪獣。しかし、突如として発現した原因不明の光により怪獣は死んだ。人々は歓喜に沸いたが一方で大きな問題が残された。
「この死体、誰が後始末するの?」
新たな観光資源として利用することも試みられたが巨大な死体は腐敗により徐々に膨張が進みいずれ大爆発を起こして周囲を汚染しかねないことが判明する。
巨大怪獣の死体処理というミッションを任されたのは首相直轄組織・特務隊の帯刀アラタ(山田涼介)だった。果たしてアラタは大爆発を阻止し怪獣の死体を後始末できるのか?
「映画」と言うのはやはり魔物。そしてある意味でギャンブルと言うのを迂闊にも忘れていました。特にコメディというのは結構難しい代物で、観る側のセンスと作り手のセンスが上手く噛み合えば爆発しますが相性によっては地獄を見ます。自宅で観ている分には合わなければさっさと止めてしまえば良いだけの話ですが、映画館で観るとなるとそうもいきません。だからコメディを観る時はそれなりに選んでるつもりだったんですが今回は思いっきり掴んでしまいました(苦笑)
倒した、あるいは倒れた怪獣をどうするか、という主題は一見ユニークに思えますが全く前例が無いわけでは無くむしろ結構使われてきたモチーフです。例えば「パシフィック・リム」(2013年)では怪獣の死体を始末する建設車両群やその死体を利用して漢方薬を作るブローカーなどが登場したりします。他にも「ウルトラマンティガ」(1996年)に漂着した怪獣の腐乱死体をどう対処するか、というエピソードがありますし「ゴジラxメカゴジラ」(2002年)ではゴジラの遺骸をベースにメカゴジラ「機龍」が建造されます。ただ、大抵は世界観をより掘り下げるためであったりTVシリーズの1エピソードのように短編で使われることが多いため、今作みたいにそれを長編映画の主題として製作されたのは初めてではないかと思います。なかなか攻めた着眼点を「インスタント沼」(2009年)「俺俺」(2013年)などシュールなシチュエーションの不条理劇を得意とする三木聡監督がどう料理するのか、という期待で鑑賞しました。
世界観の詰めがいささか甘くは感じたもののシナリオがどうしようもないほど破綻しているワケではありません。山田涼介、土屋太鳳、西田敏行、濱田岳を筆頭とした俳優陣の演技も悪くなく、小道具なども凝っていて映像やサウンドデザインも結構ちゃんと迫力があります。ですが、私には作中繰り出されるギャグとの相性が致命的に最悪でした。例えて言うならそう「職場の飲み会で上司が周囲が引いてるのも気づかず時代遅れでセクハラ紛いの下ネタを延々と喋り続けるのを聞く羽目に陥っている」というところでしょうか。しかもかなり冗長。この内容で上映時間115分は長すぎる。と言うかこの企画で良くこれだけの予算規模とキャストを獲得できたものと心底感心します。もっとずっとチープに出来ていればまだ納得出来る部分が多く、そのギャップの凄まじさに困惑しました。
また、恐らくある程度意識的にやっているのでしょうが、この映画、「パシフィック・リム」や「シン・ゴジラ」のパロディと思しきシーンも登場します。ですが結果的にそれが笑いに繋がるというよりこの2作が何を作品からオミットすることで評価を得るに至ったかを鮮明に浮き彫りにします。そんな映画が東宝ではなく松竹と東映の共同出資で製作・配給されているのも何とも皮肉めいています。
主題に対するアプローチの濃度がシーン単位で大きく乱高下するが故の観る側のスタンスの掴み辛さも手伝って、自分は映画については結構悪食だと思っていたのですが、観てるのがあまりに苦痛になり途中で席を立ちたい欲求に駆られるなどまだまだ修行が甘かったようです。これも経験と言い聞かせて何とか最後まで観ましたけれども。
公開直後からかなりの酷評に晒され炎上気味のこの映画、全国300館規模の公開作品にしてはかなり尖っていることとこれまでの特撮や怪獣映画をパロディ、というより下品に揶揄していると取れてしまうくだりがいくつも散見されるためそりゃあ脊髄反射的にキレる人も出てきてしまうだろうとは思います。が、一方で滅多に観られないタイプの作品であることも確か。もともと三木聡監督の作風が気に入ってる方なら尚更楽しめるでしょう。そうでない方も劇物扱いの映画がどういうものかを確かめてみたい人は鑑賞料金と2時間を投げ捨てるくらいのつもりで行けば、話のネタになるだけの映像体験ができるかもしれません。
こんばんは、小島@監督です。
「食」がテーマの一つだけあり初回の料理作画のシズル感はどれもかなりのものでしたが、あのクオリティで1年間やり切れるのかしら。
さて、今回の映画は「大怪獣のあとしまつ」です。
突如襲来し、首都圏を蹂躙して人々を恐怖に陥れた大怪獣。しかし、突如として発現した原因不明の光により怪獣は死んだ。人々は歓喜に沸いたが一方で大きな問題が残された。
「この死体、誰が後始末するの?」
新たな観光資源として利用することも試みられたが巨大な死体は腐敗により徐々に膨張が進みいずれ大爆発を起こして周囲を汚染しかねないことが判明する。
巨大怪獣の死体処理というミッションを任されたのは首相直轄組織・特務隊の帯刀アラタ(山田涼介)だった。果たしてアラタは大爆発を阻止し怪獣の死体を後始末できるのか?
「映画」と言うのはやはり魔物。そしてある意味でギャンブルと言うのを迂闊にも忘れていました。特にコメディというのは結構難しい代物で、観る側のセンスと作り手のセンスが上手く噛み合えば爆発しますが相性によっては地獄を見ます。自宅で観ている分には合わなければさっさと止めてしまえば良いだけの話ですが、映画館で観るとなるとそうもいきません。だからコメディを観る時はそれなりに選んでるつもりだったんですが今回は思いっきり掴んでしまいました(苦笑)
倒した、あるいは倒れた怪獣をどうするか、という主題は一見ユニークに思えますが全く前例が無いわけでは無くむしろ結構使われてきたモチーフです。例えば「パシフィック・リム」(2013年)では怪獣の死体を始末する建設車両群やその死体を利用して漢方薬を作るブローカーなどが登場したりします。他にも「ウルトラマンティガ」(1996年)に漂着した怪獣の腐乱死体をどう対処するか、というエピソードがありますし「ゴジラxメカゴジラ」(2002年)ではゴジラの遺骸をベースにメカゴジラ「機龍」が建造されます。ただ、大抵は世界観をより掘り下げるためであったりTVシリーズの1エピソードのように短編で使われることが多いため、今作みたいにそれを長編映画の主題として製作されたのは初めてではないかと思います。なかなか攻めた着眼点を「インスタント沼」(2009年)「俺俺」(2013年)などシュールなシチュエーションの不条理劇を得意とする三木聡監督がどう料理するのか、という期待で鑑賞しました。
世界観の詰めがいささか甘くは感じたもののシナリオがどうしようもないほど破綻しているワケではありません。山田涼介、土屋太鳳、西田敏行、濱田岳を筆頭とした俳優陣の演技も悪くなく、小道具なども凝っていて映像やサウンドデザインも結構ちゃんと迫力があります。ですが、私には作中繰り出されるギャグとの相性が致命的に最悪でした。例えて言うならそう「職場の飲み会で上司が周囲が引いてるのも気づかず時代遅れでセクハラ紛いの下ネタを延々と喋り続けるのを聞く羽目に陥っている」というところでしょうか。しかもかなり冗長。この内容で上映時間115分は長すぎる。と言うかこの企画で良くこれだけの予算規模とキャストを獲得できたものと心底感心します。もっとずっとチープに出来ていればまだ納得出来る部分が多く、そのギャップの凄まじさに困惑しました。
また、恐らくある程度意識的にやっているのでしょうが、この映画、「パシフィック・リム」や「シン・ゴジラ」のパロディと思しきシーンも登場します。ですが結果的にそれが笑いに繋がるというよりこの2作が何を作品からオミットすることで評価を得るに至ったかを鮮明に浮き彫りにします。そんな映画が東宝ではなく松竹と東映の共同出資で製作・配給されているのも何とも皮肉めいています。
主題に対するアプローチの濃度がシーン単位で大きく乱高下するが故の観る側のスタンスの掴み辛さも手伝って、自分は映画については結構悪食だと思っていたのですが、観てるのがあまりに苦痛になり途中で席を立ちたい欲求に駆られるなどまだまだ修行が甘かったようです。これも経験と言い聞かせて何とか最後まで観ましたけれども。
公開直後からかなりの酷評に晒され炎上気味のこの映画、全国300館規模の公開作品にしてはかなり尖っていることとこれまでの特撮や怪獣映画をパロディ、というより下品に揶揄していると取れてしまうくだりがいくつも散見されるためそりゃあ脊髄反射的にキレる人も出てきてしまうだろうとは思います。が、一方で滅多に観られないタイプの作品であることも確か。もともと三木聡監督の作風が気に入ってる方なら尚更楽しめるでしょう。そうでない方も劇物扱いの映画がどういうものかを確かめてみたい人は鑑賞料金と2時間を投げ捨てるくらいのつもりで行けば、話のネタになるだけの映像体験ができるかもしれません。
新規にゲームを始める時に聞かれがちなのが難易度設定。
小さな頃からゲームをプレイし続けている私としては!
『イージー』を選ぶのは、なんかプライドが許さず、
なんとなくノーマルを選んでしまう傾向があります。
そんな中、何度も同じ場所でミスしてしまったところ、
「難易度をイージーにしますか?」
と聞いてきて、いらんお世話じゃボケェ!とツッコミ。
ところで最近の任天堂のゲームの中にはクリアできないと、
「クリアしたことにして、次のステージに進みますか?」
と、プライドをズタズタにしてくるらしいですね。
さて、最近私が悶絶しているのはガソリンの価格です。
現在、レギュラーガソリンの日本の平均価格が170円ほど。
そして私はハイオクの人なので、もっと高価格です。
愛知県では日本の中ではガソリンが安い地域に入るため、
170円を実感している人は少ないかもしれませんが、
とは言えやっぱりガソリンの価格上昇は実感しますよね。
で、最近のガソリン価格がなぜ上昇するかを調べていたら、
その理由よりビックリするような事実に怒り心頭です。
それは、ガソリンに掛かっている税金でした。
ガソリン価格はよく「税金の2重取り」と言われます。
それは『ガソリン税』と『消費税』のことを言います。
税金の2重取りということで不満も爆発するところですが、
もっと調べるとガソリン価格の内訳は、
1.ガソリン本体価格
2.ガソリン税
3.石油石炭税
4.温暖化対策税
5.消費税
と、なんと実は4重取りをしているようなのです。
そして、税率は合計するとガソリン価格の約100%で、
1リットル平均170円ならば、単価は85円で税金85円!
なんだそれ?!バカじゃねえの??
日本の自動車業界はトヨタの豊田章男社長が言うには、
550万人ほどが働いている大変大きな業種と言います。
日本の人口が少子化が進んだとはいえ1億2千万人なので
20人に1人ものが自動車業界で働いていることになります。
これだけ多くの人が自動車業界で働いているのですから、
日本では自動車はもっと優遇されてもいいと思います。
もっと車に乗りたい、車を所有したいと思えるようにして、
自動車業界が潤い、そして国全体が潤うと思います。
車にはガソリンだけでなく、購入時も所持するだけでも、
すごい税金が掛かっているのにガソリンもこの有り様。
日本の主な業種である自動車産業を発展させるためにも、
もうちょっとガソリン税はなんとかしたほうがと思います。
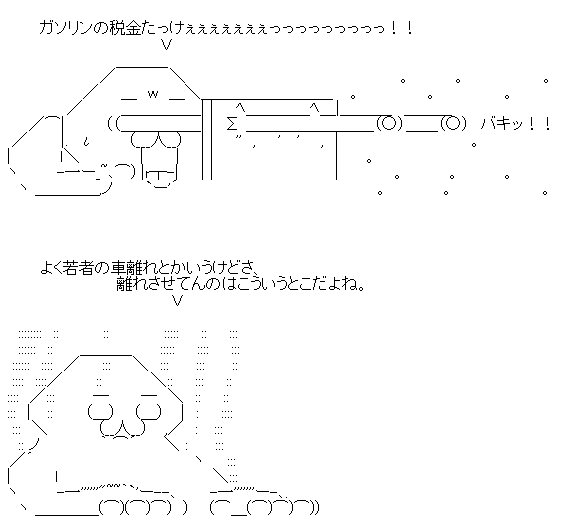
小さな頃からゲームをプレイし続けている私としては!
『イージー』を選ぶのは、なんかプライドが許さず、
なんとなくノーマルを選んでしまう傾向があります。
そんな中、何度も同じ場所でミスしてしまったところ、
「難易度をイージーにしますか?」
と聞いてきて、いらんお世話じゃボケェ!とツッコミ。
ところで最近の任天堂のゲームの中にはクリアできないと、
「クリアしたことにして、次のステージに進みますか?」
と、プライドをズタズタにしてくるらしいですね。
さて、最近私が悶絶しているのはガソリンの価格です。
現在、レギュラーガソリンの日本の平均価格が170円ほど。
そして私はハイオクの人なので、もっと高価格です。
愛知県では日本の中ではガソリンが安い地域に入るため、
170円を実感している人は少ないかもしれませんが、
とは言えやっぱりガソリンの価格上昇は実感しますよね。
で、最近のガソリン価格がなぜ上昇するかを調べていたら、
その理由よりビックリするような事実に怒り心頭です。
それは、ガソリンに掛かっている税金でした。
ガソリン価格はよく「税金の2重取り」と言われます。
それは『ガソリン税』と『消費税』のことを言います。
税金の2重取りということで不満も爆発するところですが、
もっと調べるとガソリン価格の内訳は、
1.ガソリン本体価格
2.ガソリン税
3.石油石炭税
4.温暖化対策税
5.消費税
と、なんと実は4重取りをしているようなのです。
そして、税率は合計するとガソリン価格の約100%で、
1リットル平均170円ならば、単価は85円で税金85円!
なんだそれ?!バカじゃねえの??
日本の自動車業界はトヨタの豊田章男社長が言うには、
550万人ほどが働いている大変大きな業種と言います。
日本の人口が少子化が進んだとはいえ1億2千万人なので
20人に1人ものが自動車業界で働いていることになります。
これだけ多くの人が自動車業界で働いているのですから、
日本では自動車はもっと優遇されてもいいと思います。
もっと車に乗りたい、車を所有したいと思えるようにして、
自動車業界が潤い、そして国全体が潤うと思います。
車にはガソリンだけでなく、購入時も所持するだけでも、
すごい税金が掛かっているのにガソリンもこの有り様。
日本の主な業種である自動車産業を発展させるためにも、
もうちょっとガソリン税はなんとかしたほうがと思います。
昨日開催された「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!! Tropical Land」day2を配信で鑑賞。本来なら初めての沖縄公演になる予定でしたが昨今の情勢がそれを許さず別会場(どうやら幕張メッセだった様子)からの無観客配信ライブとなりました。
思わず見惚れてしまうようなパフォーマンスがバンバン飛び出す熱いライブで、実に見応えがありました。出演陣の中に最近声優としてよりもプロ雀士としての活躍が目覚ましい伊達朱里紗さんがいたのも多士済々なデレマスらしくて面白い。
こんばんは、小島@監督です。
ところでこのライブ、もともと落ち着いて観られるday2だけに絞るつもりでいたのですがday1の評判があまりに良かったのでそちらのチケットも買ってしまいました。ライブだけでなく一定期間のアーカイブ配信も常態化したお陰で公演のチケットを後追いでも買えると言うのは考えてみれば何だか不思議な気分。
さて、今回の映画は「バイオハザード:ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ」です。
1998年、アメリカ中西部ラクーンシティ。そこにはかつて製薬会社アンブレラ社の工場が存在したが今ではほとんどの施設が移転してしまい、残ったのは少ないスタッフと貧困層だけになっている。
かつてラクーンシティの養護施設で育ったクレア(カヤ・スコデラリオ)は、アンブレラ社が秘密裏に研究していた「何か」が街の住民に健康被害を及ぼしているというメッセージを受け取り、一度は飛び出したラクーンシティへ帰ってきた。今ではラクーン市警に所属する兄・クリス(ロビー・アメル)を訪ねるが、クリスはクレアの言うことを一笑に付して取り合わない。その時、街中に大きなサイレンが鳴り響いた…
ホラーゲームの金字塔「バイオハザード」、2002年から2016年までポール・W・S・アンダーソン監督、ミラ・ジョヴォヴィッチ主演のコンビで実写映画が6作品製作されました。ゲームの映画化としては破格のヒットを遂げ、ゾンビ映画としても最高の興行収入を記録しておりジャンル映画の大きな成功例として存在しています。そんな実写映画版「バイオハザード」がシリーズ完結後6年を経てリブート。新たな実写映画が登場です。監督は海中で逃げ場を失う恐怖を描いたパニック・スリラー「海底47m」などのヨハネス・ロバーツが手掛けています。
新作である「ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ」では前シリーズでは1度もやっていなかった、「ゲームのストーリーラインとキャラクターをベースにした映画」として製作されています。ゲーム原作として一番成功を収めた作品が原作から距離を置いた独自のビジョンの下で製作されている、というのはいささか皮肉めいた話でもありますが、結果的に「バイオハザード」には大きな鉱脈が残された格好になりました。
陰鬱なビジュアルと不穏なBGMで幕を開ける今作は、CG主体ではなくセットで以て組み上げられたラクーンシティの衰退しつつある街並みや、1998年という時代設定を十二分に活かすビデオデッキやポケベルなどのガジェット(インターネットもちゃんとダイヤルアップ接続である)などが醸し出す雰囲気はなかなかです。
また、監督が原作ゲームの大ファンなのか、全編に渡りかなりの数の小ネタが仕込んであるのも特徴です。予告編でも使われていた「振り向きゾンビ」だけでなく、ある場所には赤・青・緑のハーブが置いてありますし、ショットガンの弾薬の箱や部屋を開ける鍵の意匠などが原作に沿ったものになっていたり、「かゆい うま」のフレーズが登場するくだりがあったりします。この辺りを探してみるのも楽しいでしょう。
登場人物の造形についてもシリーズ初期のものに倣っているようで、クリスはマッチョゴリラではありませんし、レオンも後々の凄腕エージェント感は1㎜も無く、赴任初日にエグい目に遭う青年の頼りなげな右往左往ぶりが良く表現できていると思います。
ゲームに忠実な作品を仕上げようという姿勢に好感が持てる一方で、映画そのものの出来栄えとしては特に後半に行くほど多すぎる要素をまとめるのに手いっぱいの慌ただしさが目につき、序盤に成功した雰囲気作りも活用しきれておらずいささか弾んでいかないのが残念なところ。この辺り、作中のシーンがゲームへとフィードバックされたりもしたポール・W・S・アンダーソン監督版の方が勢いもパワーもあったと言わざるを得ません。
不満も少なくないのですが、個人的には何だかんだ楽しめてしまったので割と嫌いではありません。そこら中に潜んだ小ネタを探しつつツッコミを入れながら観る、そんなノー天気な楽しみ方するのが丁度いい一品。出来るなら仲間内でわいわい言いながら観るのが一番楽しいタイプの作品です。気になってる方は気楽な気持ちでどうぞ。
思わず見惚れてしまうようなパフォーマンスがバンバン飛び出す熱いライブで、実に見応えがありました。出演陣の中に最近声優としてよりもプロ雀士としての活躍が目覚ましい伊達朱里紗さんがいたのも多士済々なデレマスらしくて面白い。
こんばんは、小島@監督です。
ところでこのライブ、もともと落ち着いて観られるday2だけに絞るつもりでいたのですがday1の評判があまりに良かったのでそちらのチケットも買ってしまいました。ライブだけでなく一定期間のアーカイブ配信も常態化したお陰で公演のチケットを後追いでも買えると言うのは考えてみれば何だか不思議な気分。
さて、今回の映画は「バイオハザード:ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ」です。
1998年、アメリカ中西部ラクーンシティ。そこにはかつて製薬会社アンブレラ社の工場が存在したが今ではほとんどの施設が移転してしまい、残ったのは少ないスタッフと貧困層だけになっている。
かつてラクーンシティの養護施設で育ったクレア(カヤ・スコデラリオ)は、アンブレラ社が秘密裏に研究していた「何か」が街の住民に健康被害を及ぼしているというメッセージを受け取り、一度は飛び出したラクーンシティへ帰ってきた。今ではラクーン市警に所属する兄・クリス(ロビー・アメル)を訪ねるが、クリスはクレアの言うことを一笑に付して取り合わない。その時、街中に大きなサイレンが鳴り響いた…
ホラーゲームの金字塔「バイオハザード」、2002年から2016年までポール・W・S・アンダーソン監督、ミラ・ジョヴォヴィッチ主演のコンビで実写映画が6作品製作されました。ゲームの映画化としては破格のヒットを遂げ、ゾンビ映画としても最高の興行収入を記録しておりジャンル映画の大きな成功例として存在しています。そんな実写映画版「バイオハザード」がシリーズ完結後6年を経てリブート。新たな実写映画が登場です。監督は海中で逃げ場を失う恐怖を描いたパニック・スリラー「海底47m」などのヨハネス・ロバーツが手掛けています。
新作である「ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ」では前シリーズでは1度もやっていなかった、「ゲームのストーリーラインとキャラクターをベースにした映画」として製作されています。ゲーム原作として一番成功を収めた作品が原作から距離を置いた独自のビジョンの下で製作されている、というのはいささか皮肉めいた話でもありますが、結果的に「バイオハザード」には大きな鉱脈が残された格好になりました。
陰鬱なビジュアルと不穏なBGMで幕を開ける今作は、CG主体ではなくセットで以て組み上げられたラクーンシティの衰退しつつある街並みや、1998年という時代設定を十二分に活かすビデオデッキやポケベルなどのガジェット(インターネットもちゃんとダイヤルアップ接続である)などが醸し出す雰囲気はなかなかです。
また、監督が原作ゲームの大ファンなのか、全編に渡りかなりの数の小ネタが仕込んであるのも特徴です。予告編でも使われていた「振り向きゾンビ」だけでなく、ある場所には赤・青・緑のハーブが置いてありますし、ショットガンの弾薬の箱や部屋を開ける鍵の意匠などが原作に沿ったものになっていたり、「かゆい うま」のフレーズが登場するくだりがあったりします。この辺りを探してみるのも楽しいでしょう。
登場人物の造形についてもシリーズ初期のものに倣っているようで、クリスはマッチョゴリラではありませんし、レオンも後々の凄腕エージェント感は1㎜も無く、赴任初日にエグい目に遭う青年の頼りなげな右往左往ぶりが良く表現できていると思います。
ゲームに忠実な作品を仕上げようという姿勢に好感が持てる一方で、映画そのものの出来栄えとしては特に後半に行くほど多すぎる要素をまとめるのに手いっぱいの慌ただしさが目につき、序盤に成功した雰囲気作りも活用しきれておらずいささか弾んでいかないのが残念なところ。この辺り、作中のシーンがゲームへとフィードバックされたりもしたポール・W・S・アンダーソン監督版の方が勢いもパワーもあったと言わざるを得ません。
不満も少なくないのですが、個人的には何だかんだ楽しめてしまったので割と嫌いではありません。そこら中に潜んだ小ネタを探しつつツッコミを入れながら観る、そんなノー天気な楽しみ方するのが丁度いい一品。出来るなら仲間内でわいわい言いながら観るのが一番楽しいタイプの作品です。気になってる方は気楽な気持ちでどうぞ。
オミクロン株という新型コロナウイルスが席巻しており、
今までにない感染者数となり手がつけられない状況です。
ただ、重症化しにくいという理由でただの風邪では?と、
なんとなく楽観する雰囲気も出てきているのですが、
これもまたちょっと違うような気がするのですよね。
オミクロン株は感染力が高すぎるところが不安なところで、
マスクをしていても感染してしまう人が多い感じです。
重症化しないまでも、重症化する確率が存在するものが、
すごい感染力を持って感染していくとするならば、
結果として重症化する人数は増えてくるのではと思います。
いつになったら、コロナ前の日常が戻るのでしょうね。
さて、競泳で『自由形』というと暗黙の了解みたいな感じで、
『クロール』で泳ぐというのが当たり前になっています。
なんで『自由』と言っているのクロールしかしないの?
と思ったことがある人も多いのではないかと思いますが、
結局、クロールという泳法が現時点で人間ができる、
最速の泳法ということで自由形の最適解なんでしょう。
そんな自由じゃねぇじゃんといった自由形でしたが、
ついにその常識を覆しクロールじゃない自由形を、
実践してくれる選手を現実で見ることができました。
なんと池江璃花子選手が強豪集まる競技会の自由型予選で、
クロールの選手の中、1人でバタフライで泳ぎ予選2位。
ただ、これが結構周りでは叩かれてしまっているようで、
その選手でさえクロールで泳いだ方がやっぱり速いのに、
わざわざバタフライで泳ぐのは舐めているとの事です。
最速の泳法で最適解のクロールで泳ぐ他の選手に対して、
スピードで劣るバタフライは、舐めているとのこと。
実際、決勝ではクロールで泳いで優勝をしているので、
ここ一番では確実に結果を出せる泳法を選んでいます。
とは言え自由形という犬かきで泳いでもよいルールで、
他選手はクロールでも勝てないならそこまでですよね。
バタフライで予選落ちしたらそれこそ恥ずかしいですし。
ところで、点数を取り合う競技で相手が絶望するほどに、
点差がついてしまう実力のチーム同士の試合があると、
実力のあるチームがよく叩かれたりしています。
点を取り過ぎれば相手への配慮が足りないと言われ、
もう負けない点差になると、もう点を取りにいかないと、
全力でプレイしておらず相手への敬意が足りないといいます。
結局、ルールに従って競技をしているだけのところで、
見る側の都合でどうとでも取られてしまうのを見ると、
普通に試合をしているだけなのに大変だなと思います。
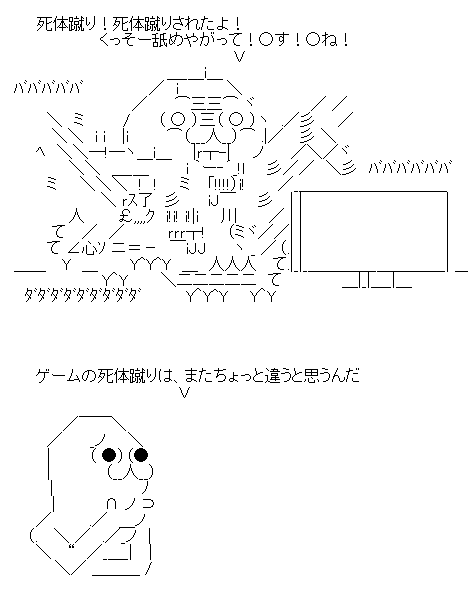
今までにない感染者数となり手がつけられない状況です。
ただ、重症化しにくいという理由でただの風邪では?と、
なんとなく楽観する雰囲気も出てきているのですが、
これもまたちょっと違うような気がするのですよね。
オミクロン株は感染力が高すぎるところが不安なところで、
マスクをしていても感染してしまう人が多い感じです。
重症化しないまでも、重症化する確率が存在するものが、
すごい感染力を持って感染していくとするならば、
結果として重症化する人数は増えてくるのではと思います。
いつになったら、コロナ前の日常が戻るのでしょうね。
さて、競泳で『自由形』というと暗黙の了解みたいな感じで、
『クロール』で泳ぐというのが当たり前になっています。
なんで『自由』と言っているのクロールしかしないの?
と思ったことがある人も多いのではないかと思いますが、
結局、クロールという泳法が現時点で人間ができる、
最速の泳法ということで自由形の最適解なんでしょう。
そんな自由じゃねぇじゃんといった自由形でしたが、
ついにその常識を覆しクロールじゃない自由形を、
実践してくれる選手を現実で見ることができました。
なんと池江璃花子選手が強豪集まる競技会の自由型予選で、
クロールの選手の中、1人でバタフライで泳ぎ予選2位。
ただ、これが結構周りでは叩かれてしまっているようで、
その選手でさえクロールで泳いだ方がやっぱり速いのに、
わざわざバタフライで泳ぐのは舐めているとの事です。
最速の泳法で最適解のクロールで泳ぐ他の選手に対して、
スピードで劣るバタフライは、舐めているとのこと。
実際、決勝ではクロールで泳いで優勝をしているので、
ここ一番では確実に結果を出せる泳法を選んでいます。
とは言え自由形という犬かきで泳いでもよいルールで、
他選手はクロールでも勝てないならそこまでですよね。
バタフライで予選落ちしたらそれこそ恥ずかしいですし。
ところで、点数を取り合う競技で相手が絶望するほどに、
点差がついてしまう実力のチーム同士の試合があると、
実力のあるチームがよく叩かれたりしています。
点を取り過ぎれば相手への配慮が足りないと言われ、
もう負けない点差になると、もう点を取りにいかないと、
全力でプレイしておらず相手への敬意が足りないといいます。
結局、ルールに従って競技をしているだけのところで、
見る側の都合でどうとでも取られてしまうのを見ると、
普通に試合をしているだけなのに大変だなと思います。
先週訃報が流れた野球漫画の第一人者だった水島新司さん、私も「ドカベン」や「あぶさん」などその著作をよく読んでいました。特にパ・リーグが今ほどの人気を獲得する遥か前から「あぶさん」において南海ホークス(現・福岡ソフトバンクホークス)を中心に丹念に取材を重ねて各球団の選手たちを実名で登場させるなど漫画を通しての野球界への貢献と影響が計り知れないほどです。パ・リーグの本拠地である球場ではほとんど顔パスだったと聞きます。訃報が流れた翌日、主要スポーツ紙がこぞって1面トップで報じ、全国紙でも社会面だけでなくスポーツ面でも報じられたのが何よりの証拠と言えるでしょう。
主要作品のほぼ全てを完結させ引退宣言をしてからのご逝去、まさに大往生だったのではと思います。
こんばんは、小島@監督です。
久しぶりに何か読んでみたくなってきた。
さて、今回の映画は「クナシリ」です。
北方四島の一つ、国後島。北海道の東端からわずか16㎞のところにあるその島は、日ロ間で領土問題が横たわる。そこには寺の石垣などの遺構が残り、シャベルで土から掘り起こせば醤油瓶や欠けた茶碗などかつて日本人が暮らしていた痕跡が残っている。1949年に日本人の退去が完了したこの島で現在暮らすロシア人たち。彼らにカメラとマイクを向けると、各々がそれぞれの立場で島の姿を語り始めた。
北方四島と呼ばれる島々があること、そこに領土問題があること、半世紀以上の長きにわたり返還のための交渉が続いていること、それらをご存じの方は多いと思います。ですがその一方でそこがどういう場所なのかを知っている方はほとんどいないのではないでしょうか。北方領土問題という言葉の下でだけその名を聞く島、私にとって国後島というのはその程度の印象でした。またロシア側から俯瞰すれば国後島はあくまで首都モスクワから遥か離れた最果ての一離島であり、そもそも関心を示す場所ですらないようにも思えます。そんな国後島に焦点を当てて取材を行った恐らくは初めてのドキュメンタリー映画です。手掛けたのはベラルーシ出身で現在はフランスを拠点に活動しているドキュメンタリー作家、ウラジーミル・コズロフ氏。
そもそもどんな風景をしているのかすら知らない国後島、普通に撮ってるだけの映像がもうそこから興味深い。実は温泉もあるらしいですよ、あの島。ある意味でチョロい客状態でした私(笑)もっともこの数十年日本人が未踏だったわけではなく1992年より始まった交流事業により7~9月のサマーシーズンにビザなしの訪問団が訪れたり鳥類などの学術研究で滞在する学者の方などもいるのですが、取材時期とは外れていたらしくこの映画には登場していません。
実際のところ、映画は数人の人物の生活とインタビューを淡々と綴っているだけの作品です。モチーフこそ刺激的ですが良くも悪くもフラットで、そこに大きなストーリーも無ければ何かを煽るようなことも無いのが特徴です。
ただこのインタビューが曲者。全体を通して老人が多いのですが人生の晩期をインフラの整備も今ひとつよろしくない最果ての地で暮らしているせいか愚痴っぽい方が多く、失くすものが無いのかロシア政府や役人への不満や批判もお構いなしなのがなかなかに驚きます。ちょっと笑えてしまうくらい。中には日本人とロシア人が共存していた1940年代を記憶している方もおり、思いがけない話が登場してきたりもします。
彼らの中には別にロシア政府のように北方四島を日本に返還することを頑なに拒むような強い主張はなく、むしろ温泉などの観光資源を活用して雇用を生み出して欲しくて日本人が再び来てくれることを望んでいる者さえいます。
作品の中で見え隠れするのは第二次大戦時に日本との戦いに勝利し住民を全員退去させ自国の領土の拡大に成功したことをプロパガンダしたい旧ソ連からのロシア政府の思惑と、更に色濃く目に留まるのは最果ての離島という地理的条件がそうさせるのか、住民の精神性がアップデートする環境に乏しい、つまり「時間が止まっている」ように見えることでしょう。
翻って、これほどロシアの風土に染まってしまった国後島を仮に日本の国土に引き戻せたとして、今、その島に生きる人はどうなるのか、そして島をどうしたいのか、その先を見つめるビジョンが日本にはあるのだろうかという思いも浮かんでは消えて、かなり複雑な思いを湧き立たせずにはおきません。
百聞は一見に如かずとはまさにこのこと。歴史と不和の果てに存在する島の在り様に現在を映し見る作品です。聞けばコズロフ氏は同じ題材を、今度は根室の側から撮影する映画を準備中とのこと。この合わせ鏡がどのような形で完成するのか、今から楽しみです。
主要作品のほぼ全てを完結させ引退宣言をしてからのご逝去、まさに大往生だったのではと思います。
こんばんは、小島@監督です。
久しぶりに何か読んでみたくなってきた。
さて、今回の映画は「クナシリ」です。
北方四島の一つ、国後島。北海道の東端からわずか16㎞のところにあるその島は、日ロ間で領土問題が横たわる。そこには寺の石垣などの遺構が残り、シャベルで土から掘り起こせば醤油瓶や欠けた茶碗などかつて日本人が暮らしていた痕跡が残っている。1949年に日本人の退去が完了したこの島で現在暮らすロシア人たち。彼らにカメラとマイクを向けると、各々がそれぞれの立場で島の姿を語り始めた。
北方四島と呼ばれる島々があること、そこに領土問題があること、半世紀以上の長きにわたり返還のための交渉が続いていること、それらをご存じの方は多いと思います。ですがその一方でそこがどういう場所なのかを知っている方はほとんどいないのではないでしょうか。北方領土問題という言葉の下でだけその名を聞く島、私にとって国後島というのはその程度の印象でした。またロシア側から俯瞰すれば国後島はあくまで首都モスクワから遥か離れた最果ての一離島であり、そもそも関心を示す場所ですらないようにも思えます。そんな国後島に焦点を当てて取材を行った恐らくは初めてのドキュメンタリー映画です。手掛けたのはベラルーシ出身で現在はフランスを拠点に活動しているドキュメンタリー作家、ウラジーミル・コズロフ氏。
そもそもどんな風景をしているのかすら知らない国後島、普通に撮ってるだけの映像がもうそこから興味深い。実は温泉もあるらしいですよ、あの島。ある意味でチョロい客状態でした私(笑)もっともこの数十年日本人が未踏だったわけではなく1992年より始まった交流事業により7~9月のサマーシーズンにビザなしの訪問団が訪れたり鳥類などの学術研究で滞在する学者の方などもいるのですが、取材時期とは外れていたらしくこの映画には登場していません。
実際のところ、映画は数人の人物の生活とインタビューを淡々と綴っているだけの作品です。モチーフこそ刺激的ですが良くも悪くもフラットで、そこに大きなストーリーも無ければ何かを煽るようなことも無いのが特徴です。
ただこのインタビューが曲者。全体を通して老人が多いのですが人生の晩期をインフラの整備も今ひとつよろしくない最果ての地で暮らしているせいか愚痴っぽい方が多く、失くすものが無いのかロシア政府や役人への不満や批判もお構いなしなのがなかなかに驚きます。ちょっと笑えてしまうくらい。中には日本人とロシア人が共存していた1940年代を記憶している方もおり、思いがけない話が登場してきたりもします。
彼らの中には別にロシア政府のように北方四島を日本に返還することを頑なに拒むような強い主張はなく、むしろ温泉などの観光資源を活用して雇用を生み出して欲しくて日本人が再び来てくれることを望んでいる者さえいます。
作品の中で見え隠れするのは第二次大戦時に日本との戦いに勝利し住民を全員退去させ自国の領土の拡大に成功したことをプロパガンダしたい旧ソ連からのロシア政府の思惑と、更に色濃く目に留まるのは最果ての離島という地理的条件がそうさせるのか、住民の精神性がアップデートする環境に乏しい、つまり「時間が止まっている」ように見えることでしょう。
翻って、これほどロシアの風土に染まってしまった国後島を仮に日本の国土に引き戻せたとして、今、その島に生きる人はどうなるのか、そして島をどうしたいのか、その先を見つめるビジョンが日本にはあるのだろうかという思いも浮かんでは消えて、かなり複雑な思いを湧き立たせずにはおきません。
百聞は一見に如かずとはまさにこのこと。歴史と不和の果てに存在する島の在り様に現在を映し見る作品です。聞けばコズロフ氏は同じ題材を、今度は根室の側から撮影する映画を準備中とのこと。この合わせ鏡がどのような形で完成するのか、今から楽しみです。
会社に協力会社の社内報が置いてあり、それを見ていたら、
「あれ?この名前、なんか覚えがあるぞ?」
その社内報には毎回社員の紹介をするページがあって、
そこに出ていた名前を見たら、なんとちゅうカラメンバー!
「ここで働くようになって、将来の人生に希望が!」
と、コメントがあり見ているこっちが恥ずかしくなるほど。
もちろん聞かれたから、空気を読んで応えたのでしょうが、
知ってる人が発言したということで読んでいるので面白いです。
でも、意外なところでちゅうカラメンバーを発見し楽しかった。
さて、ネットを見て「へー、なるほど!」と思ったことがありました。
災害時の非常持ち出し袋にオセロを入れておくといいらしく、
避難所生活はとにかく暇だから、暇潰しが必要らしい。
ひょっとしたら家が潰れて住むところが無くなったらとか、
そんな心配で避難上ではオセロどころではないかもですが、
とりあえず避難、みたいな時にはいいかもしれないですね。
避難先では電気が無かったり、停電していたりすると、
スマホや携帯ゲームは充電ができないとただの文鎮ですので、
そういった意味ではアナログなゲームがいいのでしょうね。
じゃあアナログゲームならオセロじゃなくてもとなりますが、
ルールも簡単で誰でも遊べるとのがいいのでしょう。
避難所で大オセロ大会とかになったら癒しになるかもですね。
ちゅうカラメンバーのようなオタクたちばかりが非常時向けに、
アナログゲームなんかを準備したら、マニアックになりすぎて、
スゴく異質なゲームに興じる避難所になってしまうのかな。
最近、地震が頻発しているので、避難をするということ自体が、
そんなに他人事では無くなってきたような気がします。
一番、大地震などが予想されている東海圏が意外と何もなく、
愛知県はいつもそれほどの災害は起こっていませんし、
それこそ最近はコロナの話題が前面に出過ぎている現状です。
それこそ、このオセロを準備する話題をきっかけにして、
キャンプ用の大容量バッテリーなどを準備しておかなきゃとか、
むしろ、災害時の準備をしておく必要を実感した次第です。
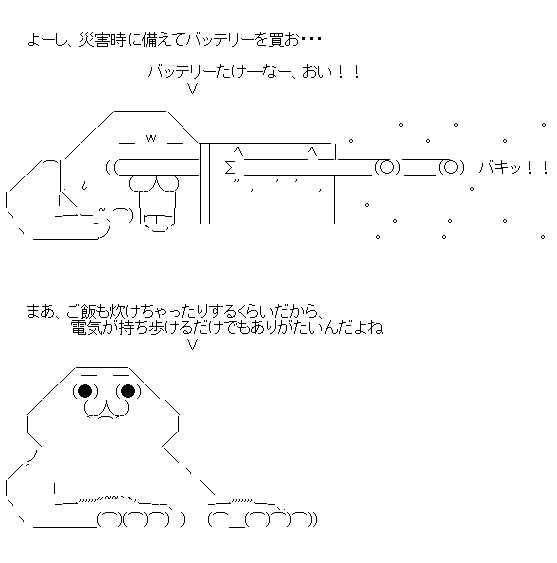
「あれ?この名前、なんか覚えがあるぞ?」
その社内報には毎回社員の紹介をするページがあって、
そこに出ていた名前を見たら、なんとちゅうカラメンバー!
「ここで働くようになって、将来の人生に希望が!」
と、コメントがあり見ているこっちが恥ずかしくなるほど。
もちろん聞かれたから、空気を読んで応えたのでしょうが、
知ってる人が発言したということで読んでいるので面白いです。
でも、意外なところでちゅうカラメンバーを発見し楽しかった。
さて、ネットを見て「へー、なるほど!」と思ったことがありました。
災害時の非常持ち出し袋にオセロを入れておくといいらしく、
避難所生活はとにかく暇だから、暇潰しが必要らしい。
ひょっとしたら家が潰れて住むところが無くなったらとか、
そんな心配で避難上ではオセロどころではないかもですが、
とりあえず避難、みたいな時にはいいかもしれないですね。
避難先では電気が無かったり、停電していたりすると、
スマホや携帯ゲームは充電ができないとただの文鎮ですので、
そういった意味ではアナログなゲームがいいのでしょうね。
じゃあアナログゲームならオセロじゃなくてもとなりますが、
ルールも簡単で誰でも遊べるとのがいいのでしょう。
避難所で大オセロ大会とかになったら癒しになるかもですね。
ちゅうカラメンバーのようなオタクたちばかりが非常時向けに、
アナログゲームなんかを準備したら、マニアックになりすぎて、
スゴく異質なゲームに興じる避難所になってしまうのかな。
最近、地震が頻発しているので、避難をするということ自体が、
そんなに他人事では無くなってきたような気がします。
一番、大地震などが予想されている東海圏が意外と何もなく、
愛知県はいつもそれほどの災害は起こっていませんし、
それこそ最近はコロナの話題が前面に出過ぎている現状です。
それこそ、このオセロを準備する話題をきっかけにして、
キャンプ用の大容量バッテリーなどを準備しておかなきゃとか、
むしろ、災害時の準備をしておく必要を実感した次第です。

