今年の私はどんな一年だったかと言えば、何だかとにかく忙しかったなぁという印象…になりそうだったところがアニカラ魂の一件で一気に全てがバラエティーと化したというか、これまでとは違うルートが開き始めた気分です(笑)
こんばんは、小島@監督です。
来年もこのノリで突き進めると良いなぁ。
さて、今年の私のブログは今回がラストということで、「今年の5本」を語ってみたいと思います。気が付けばこれももう5回目に。恒例行事になってまいりました。これまで同様、各作品には12月26日現在での視聴可能状況を記載しておきます。参考になれば幸いです。
1.この世界の片隅に
今年1本選ぶとしたらもうコレしかありません。いや10年に一つと言っても過言ではありません。まさに魂のこもった傑作。伏見ミリオン座、イオンシネマ名古屋茶屋ほかで現在公開中。当初全国65館での上映でしたが年明け以降も安城コロナシネマワールドなど公開館が増加中でロングランとなりそうです。
2.シン・ゴジラ
12年ぶりのゴジラ映画は作り手の矜持を感じさせる異色の傑作となりました。個性的なキャラクター達にファンが付いたり応援上映が各地で催されたり漫画家島本和彦氏が大暴走したりなどの盛り上がりぶりも記憶に新しいところ。7月に封切られた作品ですがミッドランドスクエアなどでしぶとく上映が続いています。来年3月22日にBlu-ray/DVDが発売予定。
3.聲の形
大今良時氏のコミックを京都アニメーションが映画化。少年と少女の繊細な機微の表現に胸が締め付けられるような感覚を覚える力作です。ミッドランドスクエアなどで現在も公開中。Blu-ray等のリリースについてはまだ未定のようです。
4.シリア・モナムール
SNSなどを介して集められた映像素材を基にシリアの現在を生々しく映し出すドキュメンタリー。名も無き巨匠たちの魂の叫びと祈りが胸を打つ。既に公開は終了し、現在は各地のイベントなどでの散発的な上映のみ。Blu-ray等のリリースの予定も今のところ無いそうです。
5.君の名は。
正直ここまでのムーブメントを巻き起こすことになろうとは思いませんでしたが、力作であることに疑いは無いです。ミッドランドスクエア、109シネマズ名古屋などで現在も公開中。年明けからはIMAX版の公開も決定し、8月公開作品なので本来ならばそろそろBlu-ray等のリリース情報が出てきてもおかしくないのですが、今のところ全くそんな気配がありません(笑)。
5本選ぶとしたらこんな感じです。1本を除き全てが邦画、3本がアニメという私にしては珍しいチョイスになりました。今年は特にアニメ映画が大豊作でした。
さて、ここからはベスト5とまでは行かなくとも印象深かった映画たちをご紹介。鑑賞順に紹介していきます。
・ガールズ&パンツァー劇場版
昨年公開の作品ですが、「音響で観る劇場を選ぶ」ということを鮮烈に印象付けたのは特に今年に入ってからだったので。Blu-ray/DVD/ダウンロード版発売中。ですが、現在も散発的に各地で上映が続いています。
・オデッセイ
マット・デイモン主演の火星サバイバル映画。かなり悲惨な状況なのにタフで明るい作りが印象的。Blu-ray/DVD/ダウンロード版発売中。
・仮面ライダー1号
圧倒的藤岡弘、。その雄姿に涙する。ただ一人の俳優にのみ捧げられる映画があっても良い。Blu-ray/DVD発売中。
・シビル・ウォー キャプテン・アメリカ
重厚的な物語にキャラクターの個性を活かしたアクションシークエンスと、アメコミヒーロー映画に求められる全てが高次元で詰まった傑作。Blu-ray/DVD/ダウンロード版発売中。
・ズートピア
ディズニーの新作長編はカワイイ絵柄して結構ポリティカルでクレバーな作り。ファミリー向け映画でこういうのをしれっと作ってしまうあたりやっぱりアメリカは強い。Blu-ray/DVD/ダウンロード版発売中。
・デッドプール
「シビル・ウォー」とは別の意味でアメコミヒーローの楽しさ全開。Blu-ray/DVD/ダウンロード版発売中。
・シチズンフォー スノーデンの暴露
スノーデン事件の内幕を本人が語る、というよりその瞬間を収めたドキュメンタリー。一級品のスリラーのような緊張感だ。ダウンロード版発売中。DVDは1月6日発売予定。
・AMY
夭折のシンガー・エイミー・ワインハウスの生涯を綴るドキュメンタリー。突出した才能に過度に群がる者たちに潰されていくエイミーの姿が切ない。Blu-ray/DVDは1月11日発売予定。
・ちえりとチェリー
高森奈津美と星野源主演の日本では珍しい長編パペットアニメーション。柔らかな画面と繊細な物語が特徴。既に主要上映館での公開は終了し、現在はイベント上映のみ。Blu-ray/DVDの発売予定は今のところ無いようです。
・ライト/オフ
照明を消すと現れる怪異と戦う家族を描くホラー。とにかくアイディアが秀逸。Blu-ray/DVD/ダウンロード版発売中。
・高慢と偏見とゾンビ
英国恋愛純文学+ゾンビ!ボンクラすぎる組み合わせがとてもズルい。ドレスを翻し放たれるハイキックに震えろ!Blu-ray/DVDは4月4日発売予定。
・ローグ・ワン
「スターウォーズ」EP4の開幕10分前までの事件を語るスピンオフ。歴史に残らず消えていく名も無き者たちの儚い戦いと祈り。全ては、ルーク・スカイウォーカーへと繋がっていく。ただいま絶賛公開中。
実は今年は数年ぶりに鑑賞本数が50本を切ってしまうような状況だったのですが、それでも次々と傑作、力作に巡り会える大当たりの年でした。来年はどんな作品に巡り会えるでしょうか。というか来年は50本ペースに戻したい!
こんばんは、小島@監督です。
来年もこのノリで突き進めると良いなぁ。
さて、今年の私のブログは今回がラストということで、「今年の5本」を語ってみたいと思います。気が付けばこれももう5回目に。恒例行事になってまいりました。これまで同様、各作品には12月26日現在での視聴可能状況を記載しておきます。参考になれば幸いです。
1.この世界の片隅に
今年1本選ぶとしたらもうコレしかありません。いや10年に一つと言っても過言ではありません。まさに魂のこもった傑作。伏見ミリオン座、イオンシネマ名古屋茶屋ほかで現在公開中。当初全国65館での上映でしたが年明け以降も安城コロナシネマワールドなど公開館が増加中でロングランとなりそうです。
2.シン・ゴジラ
12年ぶりのゴジラ映画は作り手の矜持を感じさせる異色の傑作となりました。個性的なキャラクター達にファンが付いたり応援上映が各地で催されたり漫画家島本和彦氏が大暴走したりなどの盛り上がりぶりも記憶に新しいところ。7月に封切られた作品ですがミッドランドスクエアなどでしぶとく上映が続いています。来年3月22日にBlu-ray/DVDが発売予定。
3.聲の形
大今良時氏のコミックを京都アニメーションが映画化。少年と少女の繊細な機微の表現に胸が締め付けられるような感覚を覚える力作です。ミッドランドスクエアなどで現在も公開中。Blu-ray等のリリースについてはまだ未定のようです。
4.シリア・モナムール
SNSなどを介して集められた映像素材を基にシリアの現在を生々しく映し出すドキュメンタリー。名も無き巨匠たちの魂の叫びと祈りが胸を打つ。既に公開は終了し、現在は各地のイベントなどでの散発的な上映のみ。Blu-ray等のリリースの予定も今のところ無いそうです。
5.君の名は。
正直ここまでのムーブメントを巻き起こすことになろうとは思いませんでしたが、力作であることに疑いは無いです。ミッドランドスクエア、109シネマズ名古屋などで現在も公開中。年明けからはIMAX版の公開も決定し、8月公開作品なので本来ならばそろそろBlu-ray等のリリース情報が出てきてもおかしくないのですが、今のところ全くそんな気配がありません(笑)。
5本選ぶとしたらこんな感じです。1本を除き全てが邦画、3本がアニメという私にしては珍しいチョイスになりました。今年は特にアニメ映画が大豊作でした。
さて、ここからはベスト5とまでは行かなくとも印象深かった映画たちをご紹介。鑑賞順に紹介していきます。
・ガールズ&パンツァー劇場版
昨年公開の作品ですが、「音響で観る劇場を選ぶ」ということを鮮烈に印象付けたのは特に今年に入ってからだったので。Blu-ray/DVD/ダウンロード版発売中。ですが、現在も散発的に各地で上映が続いています。
・オデッセイ
マット・デイモン主演の火星サバイバル映画。かなり悲惨な状況なのにタフで明るい作りが印象的。Blu-ray/DVD/ダウンロード版発売中。
・仮面ライダー1号
圧倒的藤岡弘、。その雄姿に涙する。ただ一人の俳優にのみ捧げられる映画があっても良い。Blu-ray/DVD発売中。
・シビル・ウォー キャプテン・アメリカ
重厚的な物語にキャラクターの個性を活かしたアクションシークエンスと、アメコミヒーロー映画に求められる全てが高次元で詰まった傑作。Blu-ray/DVD/ダウンロード版発売中。
・ズートピア
ディズニーの新作長編はカワイイ絵柄して結構ポリティカルでクレバーな作り。ファミリー向け映画でこういうのをしれっと作ってしまうあたりやっぱりアメリカは強い。Blu-ray/DVD/ダウンロード版発売中。
・デッドプール
「シビル・ウォー」とは別の意味でアメコミヒーローの楽しさ全開。Blu-ray/DVD/ダウンロード版発売中。
・シチズンフォー スノーデンの暴露
スノーデン事件の内幕を本人が語る、というよりその瞬間を収めたドキュメンタリー。一級品のスリラーのような緊張感だ。ダウンロード版発売中。DVDは1月6日発売予定。
・AMY
夭折のシンガー・エイミー・ワインハウスの生涯を綴るドキュメンタリー。突出した才能に過度に群がる者たちに潰されていくエイミーの姿が切ない。Blu-ray/DVDは1月11日発売予定。
・ちえりとチェリー
高森奈津美と星野源主演の日本では珍しい長編パペットアニメーション。柔らかな画面と繊細な物語が特徴。既に主要上映館での公開は終了し、現在はイベント上映のみ。Blu-ray/DVDの発売予定は今のところ無いようです。
・ライト/オフ
照明を消すと現れる怪異と戦う家族を描くホラー。とにかくアイディアが秀逸。Blu-ray/DVD/ダウンロード版発売中。
・高慢と偏見とゾンビ
英国恋愛純文学+ゾンビ!ボンクラすぎる組み合わせがとてもズルい。ドレスを翻し放たれるハイキックに震えろ!Blu-ray/DVDは4月4日発売予定。
・ローグ・ワン
「スターウォーズ」EP4の開幕10分前までの事件を語るスピンオフ。歴史に残らず消えていく名も無き者たちの儚い戦いと祈り。全ては、ルーク・スカイウォーカーへと繋がっていく。ただいま絶賛公開中。
実は今年は数年ぶりに鑑賞本数が50本を切ってしまうような状況だったのですが、それでも次々と傑作、力作に巡り会える大当たりの年でした。来年はどんな作品に巡り会えるでしょうか。というか来年は50本ペースに戻したい!
昨日の忘年会に参加された皆さん、お疲れ様でした!
あまりに楽しかったので「この電車で帰ろう」と思ってた時間をブッちぎってしまい、帰宅したのは日付変わる直前だったよ(苦笑)!
楽しい時間はホントすぎるのが早い。
こんばんは、小島@監督です。
それにしても物凄い勢いで件の旅行に対するハードルが上がってるんだが私はこのハイパーインフレに耐えられるんだろうか…?
さて、今回の映画は「ローグ・ワン」です。
辺境の惑星で家族と共に隠棲する科学者ゲイレン・アーソ(マッツ・ミケルセン)。しかしその平穏は帝国軍のオーソン・クレニック長官(ベン・メンデルソーン)のシャトルが来訪したことにより終わりを告げる。
クレニックは建造が思うように進まない「デス・スター」の完成のためにゲイレンの頭脳を欲したのだ。妻子を人質に取ろうとするクレニックに対し、何とか娘を隠すことには成功するものの妻は殺され、ゲイレンは連行されてしまう。
数年後、強制労働収容所へ移送されようとしていた女性が一人、同盟軍に救出され反乱軍基地へと連れられた。女性の名はジン・アーソ(フェリシティ・ジョーンズ)。ゲイレンの娘である。
「スターウォーズ」EP4のオープニングロールに断片的に触れられ、レイアによってルークにもたらされる「デス・スター」の設計図に絡むエピソードをより詳細に翻案し製作された作品です。
公開の約半年前に大規模な再撮影を行ったことが報じられ、ファンを不安にさせましたが、完成した作品はなかなかどうして骨太な一本に仕上がっていました。
主人公ジンの道程の中で少しずつ増えていく仲間たち。シニカルな軍人キャシアン・アンドー(ティエゴ・ルナ)や盲目ながら武術の達人チアルート・イムウェ(ドニー・イェン)など個性的なキャラがジンの下へ集っていく様はどこか「七人の侍」を彷彿とさせます。
そもそも「スターウォーズ」が「隠し砦の三悪人」を始めとした黒澤映画への多大なリスペクトが込められていたことを思えばコレもある意味原典へのオマージュとも言えるでしょう。
また、物語が進むにつれて明かされる「デス・スター」に隠された謎やその「設計図」のデータに込められた希望が願いがやがて託されるべき人物へと繋がっていく様はシリーズのファンにはストレートに熱く迫るものがあります。序盤のちょっともっさりした話運びなど帳消しにしてしまう後半の熱さが堪りません。
また、この映画、良く揃ったなというか、マッツ・ミケルセン、フォレスト・ウィテカー、ドニー・イェンというまるで方向性の違う名優たちの演技を一度に楽しめる奇妙な贅沢さがあります。苦み走った渋いマッツ・ミケルセンの演技を楽しんだ直後にドニー・イェンの体裁きを堪能できるというこの謎の豪華さも割と推したい。
物語の性質上基本的にファン向けの作品ではありますが、EP4への繋がりになる部分の描き方が巧みでこれをきっかけに「スターウォーズ」の世界に飛び込んでみる、というのも面白いかもしれません。いずれにしても興味のある方は是非映画館で。やっぱりスケールの大きい映像はスクリーンで観ると楽しいですよ。
あまりに楽しかったので「この電車で帰ろう」と思ってた時間をブッちぎってしまい、帰宅したのは日付変わる直前だったよ(苦笑)!
楽しい時間はホントすぎるのが早い。
こんばんは、小島@監督です。
それにしても物凄い勢いで件の旅行に対するハードルが上がってるんだが私はこのハイパーインフレに耐えられるんだろうか…?
さて、今回の映画は「ローグ・ワン」です。
辺境の惑星で家族と共に隠棲する科学者ゲイレン・アーソ(マッツ・ミケルセン)。しかしその平穏は帝国軍のオーソン・クレニック長官(ベン・メンデルソーン)のシャトルが来訪したことにより終わりを告げる。
クレニックは建造が思うように進まない「デス・スター」の完成のためにゲイレンの頭脳を欲したのだ。妻子を人質に取ろうとするクレニックに対し、何とか娘を隠すことには成功するものの妻は殺され、ゲイレンは連行されてしまう。
数年後、強制労働収容所へ移送されようとしていた女性が一人、同盟軍に救出され反乱軍基地へと連れられた。女性の名はジン・アーソ(フェリシティ・ジョーンズ)。ゲイレンの娘である。
「スターウォーズ」EP4のオープニングロールに断片的に触れられ、レイアによってルークにもたらされる「デス・スター」の設計図に絡むエピソードをより詳細に翻案し製作された作品です。
公開の約半年前に大規模な再撮影を行ったことが報じられ、ファンを不安にさせましたが、完成した作品はなかなかどうして骨太な一本に仕上がっていました。
主人公ジンの道程の中で少しずつ増えていく仲間たち。シニカルな軍人キャシアン・アンドー(ティエゴ・ルナ)や盲目ながら武術の達人チアルート・イムウェ(ドニー・イェン)など個性的なキャラがジンの下へ集っていく様はどこか「七人の侍」を彷彿とさせます。
そもそも「スターウォーズ」が「隠し砦の三悪人」を始めとした黒澤映画への多大なリスペクトが込められていたことを思えばコレもある意味原典へのオマージュとも言えるでしょう。
また、物語が進むにつれて明かされる「デス・スター」に隠された謎やその「設計図」のデータに込められた希望が願いがやがて託されるべき人物へと繋がっていく様はシリーズのファンにはストレートに熱く迫るものがあります。序盤のちょっともっさりした話運びなど帳消しにしてしまう後半の熱さが堪りません。
また、この映画、良く揃ったなというか、マッツ・ミケルセン、フォレスト・ウィテカー、ドニー・イェンというまるで方向性の違う名優たちの演技を一度に楽しめる奇妙な贅沢さがあります。苦み走った渋いマッツ・ミケルセンの演技を楽しんだ直後にドニー・イェンの体裁きを堪能できるというこの謎の豪華さも割と推したい。
物語の性質上基本的にファン向けの作品ではありますが、EP4への繋がりになる部分の描き方が巧みでこれをきっかけに「スターウォーズ」の世界に飛び込んでみる、というのも面白いかもしれません。いずれにしても興味のある方は是非映画館で。やっぱりスケールの大きい映像はスクリーンで観ると楽しいですよ。
昨日のアニカラ魂に参加された皆さん、長時間のイベントお疲れ様でした!楽しんで頂けましたか?私は良い感じ満喫してまだ体が疲れてます。今日を休みにしておいて良かった(笑)
プレゼント交換会では今回は1985年~95年にかけてイギリスで製作・放送されたドラマ「シャーロック・ホームズの冒険」のDVD-BOX第1巻を用意しました。まさかハドソン夫人のコスプレした方に渡るとは思いませんでしたが(笑)頂いたのは映画「妖怪ウォッチ」第1作目のDVDでした。どなたのチョイスか分かりませんがありがとー!妖怪ウォッチは実はまだちゃんと観た事無かったけど、この機会に観てみます。
こんばんは、小島@監督です。
さて、今回は昨日の今日で映画の話するのも何なので、昨日のアニカラ魂の話を。
そもそもそれまでほとんど接点の無かった私とほなみんさんのあのユニット、実は仕掛け人がいます。
エロス人さんです。
発端は8月7日の歌会。ドリンクバーに飲み物を取りに行った私をエロス人さんが呼び止め、
「小島さん、アニカラ魂出る予定?」
「今のところそのつもりだけど」
「相方決まってる?」
「いや、まだ決まってない」
「このほなみんさんが相方探してるんだけど組んでみない?」
「………は?ぃ…良い…よ…!?」
と、いう流れ。ええ。あまりの急展開に軽くパニックでした。今思えば良く引き受けた私(笑)
取り敢えずまずは双方のやってみたい曲をリストアップするところから始め、チーム名も2人とも水樹奈々の甲子園ライブに行く事だけは分かっていたので「NANA☆MIZUKI」、実に安直です(笑)
初回練習の際にはリストアップした曲をまずは片っ端から歌ってみました。本番では無かった水樹奈々の曲もトライしてみてるのですがイマイチしっくりこなくて選曲から外れたりしています。
1回戦で披露したのは「アライブファクター」、「アイドルマスターミリオンライブ!」のキャラクターソングの一つです。
私と関わらなければ全く知らなかったであろうアイマスのキャラソンをしかもコスプレして歌ってくださったことに驚いた方も多かったのではないでしょうか。あと、ちゅうカラアイマス部の皆さんもあの選曲は意外だったはず。コレ、アイマスの中でも結構マイナーな部類の曲です。ライブでも1度か2度しか歌われたこと無いですし。
ほなみんさんと組むことが決まった時、歌会が終わる前にほなみんさんがどういう風に歌う人なのか聞きに行ったら、えらい上手いわ声量が良いわで「ツインヴォーカルで聴ける曲」をと考えていたらフッと思いついたのがこの曲です。きっちり形にできれば曲を知らない人にも届くはず、とぶつけてみました。
イベント1週間前にほなみんさんがアイマスの衣装を着てステージに立つことを提案してくれ、その時点でギリギリでしたが「もし衣装が間に合うなら私プロデューサーってことでスーツ着て出ます」と宣言し、結果あのような形に。
当初2回戦用に準備していた曲ですが、1回戦の結果次第では衣装がお蔵入りになってしまうのがもったいなく、前日に曲順を入れ替えました。トータルで皆さんの予想の上を行けたようで内心ガッツポーズでした(笑)
2回戦で披露したのは「What's Up Guys?」、1995年に放送されたアニメ「爆れつハンター」のOPです。
昨日のイベント中や食事会の場でコレを話すと結構皆さん驚かれたのですが、この曲、実はほなみんさんからの提案です。正直私も最初に曲をリストアップした際にこの曲のタイトルがあったのを見た時には驚きました。アニサマで栗林みな実と谷山紀章がカバーしたのを聴いて感激したとのことで、思いもよらぬ引き出しの持ち合わせに私も感激。一番最初に決まったのがこの曲でした(笑)
実はこの曲の時ほなみんさんが着ていた衣装は奥井雅美がかつてPVで使っていた衣装の色違いだそうですよ。
決勝で披露したのは「7-seven-」、2014年に放送されたアニメ「七つの大罪」のEDです。
コレについては発案は私。「知名度高めで単純にノリやすい曲を」というかなり率直な理由で選んでみました。本来はトリプルヴォーカルの曲なのでパート分けのバランスにちょっと苦労しましたが結構いい感じにまとめられたかなと思ってます。
最終的に結果は準優勝!ほとんど小細工の無いストロングスタイルのユニットとしては堂々の結果!…は、良いのですが、賞品が…賞品が…(苦笑)
この4か月だけでも充分バラエティーだったのに「まだもうちょっとだけ続くんじゃ」状態。
私のアニカラ魂はまだまだ終わらないぜ!
プレゼント交換会では今回は1985年~95年にかけてイギリスで製作・放送されたドラマ「シャーロック・ホームズの冒険」のDVD-BOX第1巻を用意しました。まさかハドソン夫人のコスプレした方に渡るとは思いませんでしたが(笑)頂いたのは映画「妖怪ウォッチ」第1作目のDVDでした。どなたのチョイスか分かりませんがありがとー!妖怪ウォッチは実はまだちゃんと観た事無かったけど、この機会に観てみます。
こんばんは、小島@監督です。
さて、今回は昨日の今日で映画の話するのも何なので、昨日のアニカラ魂の話を。
そもそもそれまでほとんど接点の無かった私とほなみんさんのあのユニット、実は仕掛け人がいます。
エロス人さんです。
発端は8月7日の歌会。ドリンクバーに飲み物を取りに行った私をエロス人さんが呼び止め、
「小島さん、アニカラ魂出る予定?」
「今のところそのつもりだけど」
「相方決まってる?」
「いや、まだ決まってない」
「このほなみんさんが相方探してるんだけど組んでみない?」
「………は?ぃ…良い…よ…!?」
と、いう流れ。ええ。あまりの急展開に軽くパニックでした。今思えば良く引き受けた私(笑)
取り敢えずまずは双方のやってみたい曲をリストアップするところから始め、チーム名も2人とも水樹奈々の甲子園ライブに行く事だけは分かっていたので「NANA☆MIZUKI」、実に安直です(笑)
初回練習の際にはリストアップした曲をまずは片っ端から歌ってみました。本番では無かった水樹奈々の曲もトライしてみてるのですがイマイチしっくりこなくて選曲から外れたりしています。
1回戦で披露したのは「アライブファクター」、「アイドルマスターミリオンライブ!」のキャラクターソングの一つです。
私と関わらなければ全く知らなかったであろうアイマスのキャラソンをしかもコスプレして歌ってくださったことに驚いた方も多かったのではないでしょうか。あと、ちゅうカラアイマス部の皆さんもあの選曲は意外だったはず。コレ、アイマスの中でも結構マイナーな部類の曲です。ライブでも1度か2度しか歌われたこと無いですし。
ほなみんさんと組むことが決まった時、歌会が終わる前にほなみんさんがどういう風に歌う人なのか聞きに行ったら、えらい上手いわ声量が良いわで「ツインヴォーカルで聴ける曲」をと考えていたらフッと思いついたのがこの曲です。きっちり形にできれば曲を知らない人にも届くはず、とぶつけてみました。
イベント1週間前にほなみんさんがアイマスの衣装を着てステージに立つことを提案してくれ、その時点でギリギリでしたが「もし衣装が間に合うなら私プロデューサーってことでスーツ着て出ます」と宣言し、結果あのような形に。
当初2回戦用に準備していた曲ですが、1回戦の結果次第では衣装がお蔵入りになってしまうのがもったいなく、前日に曲順を入れ替えました。トータルで皆さんの予想の上を行けたようで内心ガッツポーズでした(笑)
2回戦で披露したのは「What's Up Guys?」、1995年に放送されたアニメ「爆れつハンター」のOPです。
昨日のイベント中や食事会の場でコレを話すと結構皆さん驚かれたのですが、この曲、実はほなみんさんからの提案です。正直私も最初に曲をリストアップした際にこの曲のタイトルがあったのを見た時には驚きました。アニサマで栗林みな実と谷山紀章がカバーしたのを聴いて感激したとのことで、思いもよらぬ引き出しの持ち合わせに私も感激。一番最初に決まったのがこの曲でした(笑)
実はこの曲の時ほなみんさんが着ていた衣装は奥井雅美がかつてPVで使っていた衣装の色違いだそうですよ。
決勝で披露したのは「7-seven-」、2014年に放送されたアニメ「七つの大罪」のEDです。
コレについては発案は私。「知名度高めで単純にノリやすい曲を」というかなり率直な理由で選んでみました。本来はトリプルヴォーカルの曲なのでパート分けのバランスにちょっと苦労しましたが結構いい感じにまとめられたかなと思ってます。
最終的に結果は準優勝!ほとんど小細工の無いストロングスタイルのユニットとしては堂々の結果!…は、良いのですが、賞品が…賞品が…(苦笑)
この4か月だけでも充分バラエティーだったのに「まだもうちょっとだけ続くんじゃ」状態。
私のアニカラ魂はまだまだ終わらないぜ!
最近何故だか無性にB級映画が観たくなりちょっくら衝動買いしてしまいました。買ったのはコレ。
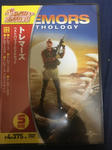
「トレマーズ」DVD-BOX!地中を這い回り音や振動に反応して人間を襲う「グラボイズ」というモンスターと、それと戦う人々を描くシリーズです。1作目のみ、大作からインディペンデント映画まで幅広く出演する名優ケビン・ベーコンが主演しているので名前くらいはご存知の方もいらっしゃると思います。
基本的にノー天気なモンスター映画なのでべらぼうに面白い、というワケでもないのですが妙に愛されてるシリーズで、1990年に第1作目が公開されて以降昨年までに5本の映画が作られたほか、日本では未リリースですが2003年には全13話のTVシリーズも製作されています。
変に勢いづいてここ1週間くらいで5本一気に観たのですが、ま~いい感じに知能指数が下がるような感じを覚えます(笑)
こんばんは、小島@監督です。
急にこんなボンクラ映画マラソンしちゃったのはきっと「この世界の片隅に」リアリティショックが半端無かったせいだ(笑)
さて、今回の映画は「ブルゴーニュで会いましょう」です。
父フランソワ(ジェラール・ランヴァン)に反抗して郷里を飛び出し、繊細な舌と豊富な知識でワイン評論家として名を成した男シャルリ・マレシャル(ジャリル・レスペール)。新刊の出版記念パーティーの翌日、妹のマリー(ローラ・スメット)から実家の窮状を聞かされる。フランス革命以来の実績を持つ実家の「ドメーヌ・マレシャル」は多額の負債を抱え売却寸前だった。
父を案じる妹の願いを聞き入れ、シャルリはドメーヌを再生させるためワイン造りを始めるのだった。
フランスの伝統的な銘醸地を舞台にワインの醸造と共に家族の再生を描く物語です。
パリでのいくつかのシーン以外はフランス映画史上初の全編ブルゴーニュロケ!ということでどこまでも広がるブドウ畑やブルゴーニュワインのシンボル的な建築物であるオスピス・ド・ボーヌやクロ・ド・ヴージョ城などの名所も登場し、ため息が出そうなほど美しい風景が楽しめます。というかこの映像自体で相当元が取れる映画です。
原題は「PREMIERS CRUS」、直訳すれば「一級畑」という意味で、ブルゴーニュでは「GRAND CRUS(特級畑)」の下に位置する格付けです。作り手次第で特級畑を凌ぐ品質のワインを生み出せる畑で、古くから伝わる区画名が付いています。また、ブルゴーニュでいう「ドメーヌ」とはブドウの栽培から醸造、瓶詰までを一貫して行う生産者を言い、ボルドーの「シャトー」とほぼ同義語と捉えていただいて構いません。対義語として、契約農家からブドウを購入してワインを醸造するメーカーを「ネゴシアン」と言います。
ワインがテーマの一つとなっている作品とあって、「協力」としてロマネ・コンティやボノー・デュ・マルトレイなど名立たる生産者がクレジットに名を連ねているのも大きな特徴で、作中に登場するワイン醸造に関するトピックの数々に嘘は無いのもポイントです。ワインを学んでいる私としても「ブドウを一粒食べてみて種を嚙んだ時にリコリスの味がしたら収穫時(近年は糖度以上にタンニンの成熟を重視しているため)」や原点回帰を図りステンレスタンクや樽ではなく古代ローマ時代に用いられた「アンフォラ(陶製の甕)」をワインの熟成に利用する生産者が出ている事など、テキストや雑誌で読んだことはあるが、というトピックが映像で出てきてくれるのは非常にありがたいくらいでした。
ワイン絡みが熱い反面物語自体はいささか平板…というか平凡な印象を拭えないため「ワイン」というテーマに食いつけなければイマイチ乗り切れない印象は否めません。ただ見方を変えれば「分かりやすい」という事でもあり、普段フランス映画を観ない方にはむしろ逆に抵抗無く観ることができるのではないでしょうか?
まあでも一番はやっぱりワインに興味がおありの方にこそ観ていただきたい。観ればきっと何か一杯飲みたくなりますよ(笑)
「トレマーズ」DVD-BOX!地中を這い回り音や振動に反応して人間を襲う「グラボイズ」というモンスターと、それと戦う人々を描くシリーズです。1作目のみ、大作からインディペンデント映画まで幅広く出演する名優ケビン・ベーコンが主演しているので名前くらいはご存知の方もいらっしゃると思います。
基本的にノー天気なモンスター映画なのでべらぼうに面白い、というワケでもないのですが妙に愛されてるシリーズで、1990年に第1作目が公開されて以降昨年までに5本の映画が作られたほか、日本では未リリースですが2003年には全13話のTVシリーズも製作されています。
変に勢いづいてここ1週間くらいで5本一気に観たのですが、ま~いい感じに知能指数が下がるような感じを覚えます(笑)
こんばんは、小島@監督です。
急にこんなボンクラ映画マラソンしちゃったのはきっと「この世界の片隅に」リアリティショックが半端無かったせいだ(笑)
さて、今回の映画は「ブルゴーニュで会いましょう」です。
父フランソワ(ジェラール・ランヴァン)に反抗して郷里を飛び出し、繊細な舌と豊富な知識でワイン評論家として名を成した男シャルリ・マレシャル(ジャリル・レスペール)。新刊の出版記念パーティーの翌日、妹のマリー(ローラ・スメット)から実家の窮状を聞かされる。フランス革命以来の実績を持つ実家の「ドメーヌ・マレシャル」は多額の負債を抱え売却寸前だった。
父を案じる妹の願いを聞き入れ、シャルリはドメーヌを再生させるためワイン造りを始めるのだった。
フランスの伝統的な銘醸地を舞台にワインの醸造と共に家族の再生を描く物語です。
パリでのいくつかのシーン以外はフランス映画史上初の全編ブルゴーニュロケ!ということでどこまでも広がるブドウ畑やブルゴーニュワインのシンボル的な建築物であるオスピス・ド・ボーヌやクロ・ド・ヴージョ城などの名所も登場し、ため息が出そうなほど美しい風景が楽しめます。というかこの映像自体で相当元が取れる映画です。
原題は「PREMIERS CRUS」、直訳すれば「一級畑」という意味で、ブルゴーニュでは「GRAND CRUS(特級畑)」の下に位置する格付けです。作り手次第で特級畑を凌ぐ品質のワインを生み出せる畑で、古くから伝わる区画名が付いています。また、ブルゴーニュでいう「ドメーヌ」とはブドウの栽培から醸造、瓶詰までを一貫して行う生産者を言い、ボルドーの「シャトー」とほぼ同義語と捉えていただいて構いません。対義語として、契約農家からブドウを購入してワインを醸造するメーカーを「ネゴシアン」と言います。
ワインがテーマの一つとなっている作品とあって、「協力」としてロマネ・コンティやボノー・デュ・マルトレイなど名立たる生産者がクレジットに名を連ねているのも大きな特徴で、作中に登場するワイン醸造に関するトピックの数々に嘘は無いのもポイントです。ワインを学んでいる私としても「ブドウを一粒食べてみて種を嚙んだ時にリコリスの味がしたら収穫時(近年は糖度以上にタンニンの成熟を重視しているため)」や原点回帰を図りステンレスタンクや樽ではなく古代ローマ時代に用いられた「アンフォラ(陶製の甕)」をワインの熟成に利用する生産者が出ている事など、テキストや雑誌で読んだことはあるが、というトピックが映像で出てきてくれるのは非常にありがたいくらいでした。
ワイン絡みが熱い反面物語自体はいささか平板…というか平凡な印象を拭えないため「ワイン」というテーマに食いつけなければイマイチ乗り切れない印象は否めません。ただ見方を変えれば「分かりやすい」という事でもあり、普段フランス映画を観ない方にはむしろ逆に抵抗無く観ることができるのではないでしょうか?
まあでも一番はやっぱりワインに興味がおありの方にこそ観ていただきたい。観ればきっと何か一杯飲みたくなりますよ(笑)
先日馬術のコンペティション、競技会に出場してきました。と言っても大層なものではなくクラブ内コンペなので参加人数も少ない小さなものですが。
自分が出場したのは「ジムカーナ」と言って、当日に発表されたコースを、所定のポイントで「巻き乗り(小さく円を描くように馬を動かすこと)」やスラローム等をしながらゴールを目指しそのタイムを競う種目です。
結果は98秒で8人中5位。1位の方は76秒なので20秒以上遅い結果に。ま、初めてなのでこんなものです。
こんばんは、小島@監督です。
なかなか乗る機会取れないけど早いところ障害跳べるランクに行きたいものよ。
さて、今回の映画は「劇場版艦これ」です。
数々の激戦を潜り抜け、南進を続ける鎮守府の艦娘たちは拠点であるショートランド泊地の戦力拡充を図っていた。
「鳥海」(声・東山奈央)達第八艦隊は敵である深海棲艦の輸送船団を強襲、その撃滅に成功する。帰路、第八艦隊を援護しながらショートランド泊地に向かう「吹雪」(声・上坂すみれ)や「睦月」(声・日高里菜)達は少しずつ赤く変色しながら艤装を腐食させてゆく奇妙な海域で、艦娘たちを呼ぶ謎の「声」を聞くのだった。
2013年にブラウザゲームとしてリリースされ人気を博し、2015年にはTVシリーズも製作・放送された「艦これ」が角川映画40周年記念作品唯一のアニメタイトルとして映画化されました。
と、言う沿革くらいは知っているものの、それ以外は数人キャラを知っている程度でゲームはプレイした事無いわTVアニメは観た事無いわで例によって徒手空拳で突貫です。
第二次大戦期の艦船を美少女キャラに擬人化した作品なので、戦闘シーンが海面を滑る彼女たちによる水雷戦と艦隊戦が基本で、特に「赤城」や「加賀」などの空母は撃ち放つ矢が艦載機に変わる、というギミックが初めて観る身にはなかなか新鮮です。劇場版だけあって作画のキレや迫力がなかなかで、スケールの大きなバトルシークエンスが楽しめます。ですがせっかく擬人化してるのなら砲撃戦だけでなく近接格闘戦のような肉体的なアクションも観てみたかった、というのは少し贅沢でしょうか。
物語についてはTVシリーズからそのままの続きであるようでさすがに一見さんには少々厳しく、ガルパンのように初心者にも強烈なインパクトを与えるフックが用意されてるワケでもないところに40人以上もいるキャラの見分けがつくハズもなく、いい感じに置いてけぼりを食ってしまってあまり入り込めなかった、というのが正直な印象です。
そんなビギナーな私でも驚いたのは声優さんの演技です。主人公・吹雪を演じた上坂すみれさんで5役を演じているほか多くの方が複数の役を演じており、特に作中重要なポジションを担う睦月と如月を見事に演じ分ける日高里菜さんや実に9役を演じ分ける東山奈央さんの2人は強烈な印象を残します。この声優陣の幅広い演技は間違いなくこの作品の強みで、まさに「聞きどころ」と言って差し支えない部分ですね。
誰に薦めていいものかちょっと迷う感じではありましたが、TVシリーズからのいくつかの要素に対して解答を用意しているような展開だったのでゲームやTVシリーズからのファンはマストで押さえておいた方が良いのは確かでしょう。ファンアイテム的なプログラムピクチャーとしては充分な出来栄えなので、気になってる方は是非スクリーンで楽しんでみてください。
自分が出場したのは「ジムカーナ」と言って、当日に発表されたコースを、所定のポイントで「巻き乗り(小さく円を描くように馬を動かすこと)」やスラローム等をしながらゴールを目指しそのタイムを競う種目です。
結果は98秒で8人中5位。1位の方は76秒なので20秒以上遅い結果に。ま、初めてなのでこんなものです。
こんばんは、小島@監督です。
なかなか乗る機会取れないけど早いところ障害跳べるランクに行きたいものよ。
さて、今回の映画は「劇場版艦これ」です。
数々の激戦を潜り抜け、南進を続ける鎮守府の艦娘たちは拠点であるショートランド泊地の戦力拡充を図っていた。
「鳥海」(声・東山奈央)達第八艦隊は敵である深海棲艦の輸送船団を強襲、その撃滅に成功する。帰路、第八艦隊を援護しながらショートランド泊地に向かう「吹雪」(声・上坂すみれ)や「睦月」(声・日高里菜)達は少しずつ赤く変色しながら艤装を腐食させてゆく奇妙な海域で、艦娘たちを呼ぶ謎の「声」を聞くのだった。
2013年にブラウザゲームとしてリリースされ人気を博し、2015年にはTVシリーズも製作・放送された「艦これ」が角川映画40周年記念作品唯一のアニメタイトルとして映画化されました。
と、言う沿革くらいは知っているものの、それ以外は数人キャラを知っている程度でゲームはプレイした事無いわTVアニメは観た事無いわで例によって徒手空拳で突貫です。
第二次大戦期の艦船を美少女キャラに擬人化した作品なので、戦闘シーンが海面を滑る彼女たちによる水雷戦と艦隊戦が基本で、特に「赤城」や「加賀」などの空母は撃ち放つ矢が艦載機に変わる、というギミックが初めて観る身にはなかなか新鮮です。劇場版だけあって作画のキレや迫力がなかなかで、スケールの大きなバトルシークエンスが楽しめます。ですがせっかく擬人化してるのなら砲撃戦だけでなく近接格闘戦のような肉体的なアクションも観てみたかった、というのは少し贅沢でしょうか。
物語についてはTVシリーズからそのままの続きであるようでさすがに一見さんには少々厳しく、ガルパンのように初心者にも強烈なインパクトを与えるフックが用意されてるワケでもないところに40人以上もいるキャラの見分けがつくハズもなく、いい感じに置いてけぼりを食ってしまってあまり入り込めなかった、というのが正直な印象です。
そんなビギナーな私でも驚いたのは声優さんの演技です。主人公・吹雪を演じた上坂すみれさんで5役を演じているほか多くの方が複数の役を演じており、特に作中重要なポジションを担う睦月と如月を見事に演じ分ける日高里菜さんや実に9役を演じ分ける東山奈央さんの2人は強烈な印象を残します。この声優陣の幅広い演技は間違いなくこの作品の強みで、まさに「聞きどころ」と言って差し支えない部分ですね。
誰に薦めていいものかちょっと迷う感じではありましたが、TVシリーズからのいくつかの要素に対して解答を用意しているような展開だったのでゲームやTVシリーズからのファンはマストで押さえておいた方が良いのは確かでしょう。ファンアイテム的なプログラムピクチャーとしては充分な出来栄えなので、気になってる方は是非スクリーンで楽しんでみてください。
昨日の歌会に参加された皆さん、お疲れ様でした。
今回は最近にしては参加者が少なかった(それでも70人超!)こともあり、ガッツリ歌えた方も多かったのではないでしょうか。ハイルさんご提供によるPSVR体験部屋もあったりなんかして普段とは一味違う場ができていたのも楽しかったですね。
また今回はじゃんけん大会に酒の提供多数!私もボジョレー・ヌーヴォーを1本進呈させていただきました。もともと毎年自分飲み用や親戚などに振る舞う分として1ケース買っておくのですが、今年は1本余ったものでして。せっかくですしたまにはと提供いたしました。
何だかんだ私も日本酒「千代の光」をゲット出来てホクホクでした(笑)
こんばんは、小島@監督です。
ところでヌーヴォーの代名詞的なキャッチコピーとなっている「何年に一つ」という言い回しは、あまりに多用され過ぎた反省から、一昨年辺りから使われなくなっています。では今年はどんなフレーズだったかというと、「エレガントな味わい」とまた分かりにく~い言葉が(苦笑)
詳細?新物なので果実味が強くて軽やかですね。ボジョレー地区は「ガメイ」という品種を使ってワインを醸造するのですが、そのガメイ特有の「イチゴキャンディのような香り」が良く感じられるのでは、と思います。これ以上は長くなるので割愛(笑)
さて、今回の映画は「この世界の片隅に」です。
昭和8年、広島に絵を描くのが好きな少女・すず(声・のん)はいた。兄・要一(声・大森夏向)と妹・すみ(声・潘めぐみ)と共に家業ののり養殖を手伝いながら暮らしていた。
時は流れ昭和19年、18歳になったすずに突如縁談が舞い込む。相手は軍港の街・呉に住む海軍文官の北條周作(声・細谷佳正)。すずは周囲の薦めるがままに祝言を上げ、呉で新しい生活を始めることになるのだった。
これから先、何年何十年か後に日本のアニメを紐解く時、2016年は特筆すべき年として記憶されることになるかもしれません。既に「君の名は。」「聲の形」と、年に一つあれば豊作と言えるレベルの作品が立て続けに公開しているというのに更にここに比類なき傑作が登場しました。
太平洋戦争時の物語でありながらここで描かれているのは最前線の酸鼻極める戦場で命をすり減らす男たちの物語でも、諜報や技術開発の分野で歴史の陰を描く物語でもありません。ただ毎日をご飯を食べ、家族と談笑し、あるがままに日々を過ごした人々の物語です。普遍的な人々の営みを丁寧に描き出したことで、そこに「生きている」人々の機微をより観る者の延長線上に感じられるようになっています。
柔らかな絵柄ながら、そこに「命」を感じられるという点で、この作品は正しく「アニメーション(本来の意味は「無機物に生命を吹き込む」ことである)」しています。
驚いたことにこの映画のキャラクターデザインと作画監督を務めたのは松原秀典氏。「サクラ大戦」「宇宙戦艦ヤマト2199」など端正なビジュアルの作品を多く手掛けた同氏のこれまでのフィルモグラフィーから大きく趣を異にするビジュアルですが、原作・こうの史代の独特の絵柄を見事にアニメートしています。
非常に綿密な時代考証が行われたことでも注目を集めた作品ですが、決してマニアックにそれだけを追求したわけではないでしょう。あくまでもそれは映画を構成する「要素」の一つにすぎません。が、実はこの「一要素に過ぎない」事がとんでもなく難しい事だったりもします。写真のように精密なビジュアルよりも、程よく省略されたものの方が人の記憶に訴えかける力を持っていたりするもの。この「省略」の度合いがこの映画、絶妙。というか神がかっているレベルです。
そうやって丹念に築き上げられた「日常」は、中盤以降戦局の悪化と共に次第に本土への空襲が行われるようになった(特に呉は軍港があったことで度々空襲を受けている)ことで次々と蹂躙され破壊されていきます。この描写をも極端な誇張無くヒロイン・すずの感じるがまま、日常の地続きのように描かれています。故にこの「喪失」のありようすら人によっては東日本大震災を始めとする近年の災害で何かを喪った方にはリアリティを持って感じられるのではないでしょうか。
この映画について語るならすず役を演じたのん(本名・能年玲奈)の演技にも触れておかねばならないでしょう。正直言って圧倒的です。確かに呼吸や間の取り方などに声の演技に対する経験不足を感じさせる部分もありはしますが「すず」という存在に命を吹き込むその最後のピースは、その演技あってこそ成し得たもののように思います。
製作資金の調達が危ぶまれ、その打開策にクラウドファンディングを募ったところ、邦画としては最高の人数と資金が集まったこの映画は、そのエンドクレジット(とパンフレット)に全員の名前が銘記されています。さらにそこには映画ならではのちょっとした趣向すら施されています。上映が終わり場内が明るくなるまで、この作品に収めるべき全てが最高の形でフィルムに収まっています。
多くの方の想いに支えられた、溢れんばかりの熱意を感じるまさに珠玉の逸品です。真に観るべき作品とはこういうものかもしれません。是非公開中にスクリーンでご覧になってみてください。
今回は最近にしては参加者が少なかった(それでも70人超!)こともあり、ガッツリ歌えた方も多かったのではないでしょうか。ハイルさんご提供によるPSVR体験部屋もあったりなんかして普段とは一味違う場ができていたのも楽しかったですね。
また今回はじゃんけん大会に酒の提供多数!私もボジョレー・ヌーヴォーを1本進呈させていただきました。もともと毎年自分飲み用や親戚などに振る舞う分として1ケース買っておくのですが、今年は1本余ったものでして。せっかくですしたまにはと提供いたしました。
何だかんだ私も日本酒「千代の光」をゲット出来てホクホクでした(笑)
こんばんは、小島@監督です。
ところでヌーヴォーの代名詞的なキャッチコピーとなっている「何年に一つ」という言い回しは、あまりに多用され過ぎた反省から、一昨年辺りから使われなくなっています。では今年はどんなフレーズだったかというと、「エレガントな味わい」とまた分かりにく~い言葉が(苦笑)
詳細?新物なので果実味が強くて軽やかですね。ボジョレー地区は「ガメイ」という品種を使ってワインを醸造するのですが、そのガメイ特有の「イチゴキャンディのような香り」が良く感じられるのでは、と思います。これ以上は長くなるので割愛(笑)
さて、今回の映画は「この世界の片隅に」です。
昭和8年、広島に絵を描くのが好きな少女・すず(声・のん)はいた。兄・要一(声・大森夏向)と妹・すみ(声・潘めぐみ)と共に家業ののり養殖を手伝いながら暮らしていた。
時は流れ昭和19年、18歳になったすずに突如縁談が舞い込む。相手は軍港の街・呉に住む海軍文官の北條周作(声・細谷佳正)。すずは周囲の薦めるがままに祝言を上げ、呉で新しい生活を始めることになるのだった。
これから先、何年何十年か後に日本のアニメを紐解く時、2016年は特筆すべき年として記憶されることになるかもしれません。既に「君の名は。」「聲の形」と、年に一つあれば豊作と言えるレベルの作品が立て続けに公開しているというのに更にここに比類なき傑作が登場しました。
太平洋戦争時の物語でありながらここで描かれているのは最前線の酸鼻極める戦場で命をすり減らす男たちの物語でも、諜報や技術開発の分野で歴史の陰を描く物語でもありません。ただ毎日をご飯を食べ、家族と談笑し、あるがままに日々を過ごした人々の物語です。普遍的な人々の営みを丁寧に描き出したことで、そこに「生きている」人々の機微をより観る者の延長線上に感じられるようになっています。
柔らかな絵柄ながら、そこに「命」を感じられるという点で、この作品は正しく「アニメーション(本来の意味は「無機物に生命を吹き込む」ことである)」しています。
驚いたことにこの映画のキャラクターデザインと作画監督を務めたのは松原秀典氏。「サクラ大戦」「宇宙戦艦ヤマト2199」など端正なビジュアルの作品を多く手掛けた同氏のこれまでのフィルモグラフィーから大きく趣を異にするビジュアルですが、原作・こうの史代の独特の絵柄を見事にアニメートしています。
非常に綿密な時代考証が行われたことでも注目を集めた作品ですが、決してマニアックにそれだけを追求したわけではないでしょう。あくまでもそれは映画を構成する「要素」の一つにすぎません。が、実はこの「一要素に過ぎない」事がとんでもなく難しい事だったりもします。写真のように精密なビジュアルよりも、程よく省略されたものの方が人の記憶に訴えかける力を持っていたりするもの。この「省略」の度合いがこの映画、絶妙。というか神がかっているレベルです。
そうやって丹念に築き上げられた「日常」は、中盤以降戦局の悪化と共に次第に本土への空襲が行われるようになった(特に呉は軍港があったことで度々空襲を受けている)ことで次々と蹂躙され破壊されていきます。この描写をも極端な誇張無くヒロイン・すずの感じるがまま、日常の地続きのように描かれています。故にこの「喪失」のありようすら人によっては東日本大震災を始めとする近年の災害で何かを喪った方にはリアリティを持って感じられるのではないでしょうか。
この映画について語るならすず役を演じたのん(本名・能年玲奈)の演技にも触れておかねばならないでしょう。正直言って圧倒的です。確かに呼吸や間の取り方などに声の演技に対する経験不足を感じさせる部分もありはしますが「すず」という存在に命を吹き込むその最後のピースは、その演技あってこそ成し得たもののように思います。
製作資金の調達が危ぶまれ、その打開策にクラウドファンディングを募ったところ、邦画としては最高の人数と資金が集まったこの映画は、そのエンドクレジット(とパンフレット)に全員の名前が銘記されています。さらにそこには映画ならではのちょっとした趣向すら施されています。上映が終わり場内が明るくなるまで、この作品に収めるべき全てが最高の形でフィルムに収まっています。
多くの方の想いに支えられた、溢れんばかりの熱意を感じるまさに珠玉の逸品です。真に観るべき作品とはこういうものかもしれません。是非公開中にスクリーンでご覧になってみてください。
この土日、名古屋の各所でアニメやゲームに絡んだ大小のイベントが催されました。小さなものでも多士済々で、土曜日には近鉄パッセの屋上で沼倉愛美のフリーライブが、日曜日にはアニメイトでいとうかなこのトーク&ライブがあったりしてました。ぶっちゃけそれらはどちらも行けずじまいだったのですが、昨日栄を歩いていたら思わぬ形で思わぬイベントに出くわしました。
それは「角田信朗&大西洋平フリーライブ」!今日からリリース開始というパチンコの新機種「CR花の慶次X雲のかなたに」のプロモイベントだったのですが、よもやこんな降って湧いた形で間近で本人の歌う「よっしゃあ漢唄」とか「傾奇者恋歌」とか聴ける機会が来ようとは。さらに大西洋平の方は「花の慶次」のタイアップ曲である「花よ、咲き誇れ」だけでなく「レッツ!ジュウオウダンス」まで歌ってくれたしでなんか大満足でした。
こんばんは、小島@監督です。
しかもほんとたまたまなのに間近で観れてしまった上、2人と握手までできてしまうとは。なんかホントびっくりするほど幸運でした。
さて、今回の映画は「アルジェの戦い」デジタルリマスター版です。
拷問に耐え兼ね仲間の居場所を自白させられた男がフランス兵に取り囲まれていた。男は泣きながら窓から飛び降りようとするが兵士たちに取り押さえられ、そのまま自白した場所へと連れられて行った。カスバの片隅で建物をフランス兵たちが包囲する。そこには子供と共に身を潜めるFLN(アルジェリア民族解放戦線)幹部がいた…
時は変わり、1954年アルジェ。カスバのヨーロッパ人地区を一人のアラブ系の青年が走っていた。男の名はアリ・ラ・ポワント(ブラヒム・ハギアグ)、やがてアルジェリア独立戦線に身を投じることになる若者である。
1966年にイタリアとアルジェリアの合作で製作され(日本では翌年公開)、アルジェリア独立戦争(1954~62年)を真正面から描きベネチア国際映画祭で金獅子賞に輝いた戦争映画の傑作が、製作50周年を機にデジタルリマスター版が製作され、全国で巡回上映を行っています。ずっと1度観てみたいと思っていましたが遂にその機会が巡ってきました。
物語の中心となっているのはアルジェリア独立戦争の内1957年に勃発した「カスバの戦い」です。暴力による抑圧と支配に耐え兼ねたアルジェリア国民たちがやがて連続爆破テロを起こしフランス軍との市街地戦が発生、その顛末を描きます。
監督ジッロ・ポンテコルヴォは、ジャーナリスト出身ながら映画製作にあたって記録映像を使うことを一切せず、膨大な資料を基にドキュメンタリータッチの劇映画として製作しました。映画には8万人に及ぶアルジェリア人が撮影に協力したほか、驚いたことにフランス軍空挺師団の指揮官フィリップ・マチュー中佐役で出演しているジャン・マルタン以外の主要人物はほぼ素人(しかも独立戦争実戦経験者多数!)を起用。さらに戦車や武装の類はアルジェ軍から借り受けカスバでオールロケを行うという方法で製作されました。
この映画、一応主人公はアリ・ラ・ポワントなのでしょうが、アルジェリア側とフランス側双方をどちらを擁護するでも弾劾するでもなく隔てなく描写し、名も無き一般市民が戦争に巻き込まれていく様やゲリラ的な市街戦の状況をリアリスティックかつ冷徹な視線で綴っていきます。冷徹であるが故に、次第に狂騒とした熱を帯びてゆく戦争の只中に放り込まれるような感覚を覚えます。
映画は終盤、カスバの戦いのその後、1960年に起きたある事件を描きます。この「1960年」という年が重要で、この年アフリカではフランス領だけでもセネガル、ニジェール、コンゴ、コートジボワール、マリなどが続々と独立した年で、実に17の国が独立を宣言し「アフリカの年」とも呼ばれています。
一つの国が産声を上げ、時代が移り変わってゆく。しかし独立戦争そのものは50年以上前に終結しはしたものの、両国間にできた溝は深く、象徴的な出来事として2001年にアルジェリア独立後初めてのフランス対アルジェリアのサッカー親善試合が開催されたものの、試合は途中で警備員の制止を振り切った群衆がスタジアムに押し寄せ中止になってしまい、それ以後1度も両国間の試合は実現していないそうです。
新たな時代の転換点やうねりを感じさせる昨今、暴力の連鎖と狂騒を徹底的に描き出したこの映画は単純な面白い/つまらないという枠を超えた輝きと熱を放ち観る者に迫ってくることでしょう。観る前は「有名な古い作品だから」観てみたかったのですが、実際のところ、この映画と向き合うことはただの懐古趣味ではなく、この映画を通して向き合っていたのは「今」なのだと感じました。50年を経ながらなお見通せる「今」がここにあります。ぜひ、目を開いて向き合ってみてください。
それは「角田信朗&大西洋平フリーライブ」!今日からリリース開始というパチンコの新機種「CR花の慶次X雲のかなたに」のプロモイベントだったのですが、よもやこんな降って湧いた形で間近で本人の歌う「よっしゃあ漢唄」とか「傾奇者恋歌」とか聴ける機会が来ようとは。さらに大西洋平の方は「花の慶次」のタイアップ曲である「花よ、咲き誇れ」だけでなく「レッツ!ジュウオウダンス」まで歌ってくれたしでなんか大満足でした。
こんばんは、小島@監督です。
しかもほんとたまたまなのに間近で観れてしまった上、2人と握手までできてしまうとは。なんかホントびっくりするほど幸運でした。
さて、今回の映画は「アルジェの戦い」デジタルリマスター版です。
拷問に耐え兼ね仲間の居場所を自白させられた男がフランス兵に取り囲まれていた。男は泣きながら窓から飛び降りようとするが兵士たちに取り押さえられ、そのまま自白した場所へと連れられて行った。カスバの片隅で建物をフランス兵たちが包囲する。そこには子供と共に身を潜めるFLN(アルジェリア民族解放戦線)幹部がいた…
時は変わり、1954年アルジェ。カスバのヨーロッパ人地区を一人のアラブ系の青年が走っていた。男の名はアリ・ラ・ポワント(ブラヒム・ハギアグ)、やがてアルジェリア独立戦線に身を投じることになる若者である。
1966年にイタリアとアルジェリアの合作で製作され(日本では翌年公開)、アルジェリア独立戦争(1954~62年)を真正面から描きベネチア国際映画祭で金獅子賞に輝いた戦争映画の傑作が、製作50周年を機にデジタルリマスター版が製作され、全国で巡回上映を行っています。ずっと1度観てみたいと思っていましたが遂にその機会が巡ってきました。
物語の中心となっているのはアルジェリア独立戦争の内1957年に勃発した「カスバの戦い」です。暴力による抑圧と支配に耐え兼ねたアルジェリア国民たちがやがて連続爆破テロを起こしフランス軍との市街地戦が発生、その顛末を描きます。
監督ジッロ・ポンテコルヴォは、ジャーナリスト出身ながら映画製作にあたって記録映像を使うことを一切せず、膨大な資料を基にドキュメンタリータッチの劇映画として製作しました。映画には8万人に及ぶアルジェリア人が撮影に協力したほか、驚いたことにフランス軍空挺師団の指揮官フィリップ・マチュー中佐役で出演しているジャン・マルタン以外の主要人物はほぼ素人(しかも独立戦争実戦経験者多数!)を起用。さらに戦車や武装の類はアルジェ軍から借り受けカスバでオールロケを行うという方法で製作されました。
この映画、一応主人公はアリ・ラ・ポワントなのでしょうが、アルジェリア側とフランス側双方をどちらを擁護するでも弾劾するでもなく隔てなく描写し、名も無き一般市民が戦争に巻き込まれていく様やゲリラ的な市街戦の状況をリアリスティックかつ冷徹な視線で綴っていきます。冷徹であるが故に、次第に狂騒とした熱を帯びてゆく戦争の只中に放り込まれるような感覚を覚えます。
映画は終盤、カスバの戦いのその後、1960年に起きたある事件を描きます。この「1960年」という年が重要で、この年アフリカではフランス領だけでもセネガル、ニジェール、コンゴ、コートジボワール、マリなどが続々と独立した年で、実に17の国が独立を宣言し「アフリカの年」とも呼ばれています。
一つの国が産声を上げ、時代が移り変わってゆく。しかし独立戦争そのものは50年以上前に終結しはしたものの、両国間にできた溝は深く、象徴的な出来事として2001年にアルジェリア独立後初めてのフランス対アルジェリアのサッカー親善試合が開催されたものの、試合は途中で警備員の制止を振り切った群衆がスタジアムに押し寄せ中止になってしまい、それ以後1度も両国間の試合は実現していないそうです。
新たな時代の転換点やうねりを感じさせる昨今、暴力の連鎖と狂騒を徹底的に描き出したこの映画は単純な面白い/つまらないという枠を超えた輝きと熱を放ち観る者に迫ってくることでしょう。観る前は「有名な古い作品だから」観てみたかったのですが、実際のところ、この映画と向き合うことはただの懐古趣味ではなく、この映画を通して向き合っていたのは「今」なのだと感じました。50年を経ながらなお見通せる「今」がここにあります。ぜひ、目を開いて向き合ってみてください。

